鉄道唱歌 奥州・磐城編の歌詞(勿来の関・八幡太郎などの歴史)について、鉄道に詳しくない方にもわかりやすく解説してゆきます!
まずは原文から!
世に芳ばしき名を留めし
八幡太郎が歌のあと
勿來の關も見てゆかん
さらに読みやすく!
世に芳ばしき 名を留めし
八幡太郎が 歌のあと
勿来の關も 見てゆかん
さあ、歌ってみよう!
♪よにこうばしきー なをとめしー
♪はちまんたろうが うたのあとー
♪なこそのせきもー みてゆかんー
仙台駅→(※注1)→岩沼駅→相馬駅(旧・中村駅)→原ノ町駅→浪江駅→双葉駅(旧・長塚駅)→富岡駅→木戸駅→広野駅→久ノ浜駅→いわき駅(旧・平駅)→内郷駅(旧・綴駅)→湯本駅→泉駅→勿来駅→大津港駅(旧・関本駅)→磯原駅→高萩駅→日立駅(旧・助川駅)→常陸多賀駅(旧・下孫駅)→水戸駅→友部駅→石岡駅→土浦駅→松戸駅→北千住駅→南千住駅→日暮里駅(※注2)
※鉄道唱歌に関連する主要駅のみ表記
※注1 仙台駅→岩沼駅は東北本線の区間
※注2 当時は田端駅が終端
いわき駅・泉駅から南下 勿来駅へ
泉駅(福島県いわき市)を過ぎて南下すると、
- 勿来駅(福島県いわき市勿来町)
を過ぎて、いよいよ福島県と茨城県の県境を通過し、再び関東地方へ戻ってくることになります。
長かった東北地方への滞在も、ここまでで終わりということになります。
奥州三大関所の1つ「勿来の関所」
その県境にあった関所のことを、いわゆる「勿来の関」といいます。
「来るなかれ」で、「勿来」
勿来は「来る勿れなかれ」、つまり「来るな」という意味になります。
勿来の関は、いわゆる
- 「磐城国」
- 「常陸国」
の国境をなす関所のことです。
「磐城国」は、現在の福島県の浜通り地域(太平洋沿岸)のことをいいます。
「常陸国」は、現在の茨城県の地域のことをいいます。
常磐線の名前は、常陸国と磐城国の頭文字からきています。つまり、茨城県と福島県の浜通りを結ぶ鉄道路線ともいえます。
「関所」とは?
今回の「勿来の関」を例とする関所とは、古くから国境(現在でいうところの県境)に置かれた、不審者を取り締まるための施設です。
すなわち、国と国を移動する者に対して、危険物は持っていないか、または犯罪を犯す心配はないかなどを調べられます。
また、江戸時代には神奈川県の箱根の関所においては、
- 江戸に鉄砲などの武器が持ち込まれないようチェックされたり、
- 参勤交代で、人質に取った嫁が、江戸から逃げたりしないか
を取り締まられました。
これらは、かつて関所の取り締まりの目的として「入り鉄砲に出女」といわれました。
箱根関所については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

「奥州三大関所」の一つ・勿来の関
勿来の関は、いわゆる「奥州三大関所」とよばれたうちの1つです。
白河の関(栃木県・福島県)
もう1つは「白河の関」で、栃木県と福島県の中通りの県境に置かれた関所です。
能因法子や、松尾芭蕉などの俳人から、その歌に詠まれてした歴史があります。
また、源頼朝がかつて平泉を平定するときも、その軍が白河の関を通過しました。
白河の関については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

鼠ヶ関(新潟県・山形県)
さらにもう1つは、「鼠ヶ関」といい、日本海側の新潟県と山形県の県境に置かれました。
松尾芭蕉も、「おくのほそ道」の旅において鼠ヶ関を通過したほか、源頼朝に追われた源義経が平泉に逃げる際にも、変装して(?)鼠ヶ関を通過したとされています(諸説あり)。
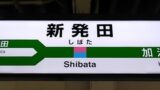
また、源義経が石川県の「安宅の関」を通過したのは知られている話です。
石川県小松市・安宅の関については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。
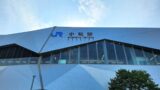
多くの詩人の詩に詠まれた、勿来の関
勿来の関も、これまで多くの歌人や俳人によって詠まれてきた関所ということになります。
そのため、「勿来の関」は多くの人々から、それらの歌によって存在が知られてきました。
歌詞にある「八幡太郎」、つまり源義家もその一人です。
勿来の関で詩を詠んだ、「八幡太郎」こと源義家
歌詞にある、「勿来の関」において歌を詠んだ「八幡太郎」とは、先述の通り、平安時代の武将である源義家のことをいいます。
源義家、通称「八幡太郎」は、平安時代の戦乱である、
- 1050年~1060年代の間に行われた「前九年の役」
- 1080年代に数年間にわたって行われた「後三年の役」
において戦った人物です。
なぜ「八幡太郎」というのか?
「八幡太郎」という通称は、源義家が幼少期に現在の京都府八幡市に存在する石清水八幡宮で、元服したことに由来するとされています。
元服とは、成人を迎える儀式をいいます。
石清水八幡宮は、源氏をはじめ数多くの武将に強く信仰されていた神社ということで知られます。
余談ですが、石清水八幡宮の竹は、トーマス・エジソンが電球を大量生産するのに用いられた竹(フィラメント)でもあります。
全国の八幡神社
なお「八幡宮」は、
- 鎌倉の鶴岡八幡宮
- 福岡の筥崎宮
- 大分県宇佐市の「宇佐神宮」
とともに知られます。
どの神社も、それぞれ鉄道唱歌にも登場しますね(それぞれ、以下の各記事において解説しています)。
鶴岡八幡宮(神奈川県・鎌倉)

筥崎宮(福岡県)

宇佐神宮(大分県)

「戦いの神様」としての「八幡の神様」
八幡の神様は、いわゆる「戦いの神様」のことで、多くの武家から信仰されました。
京都府八幡市は、京都府と大阪府のほぼ県境にある街です。
鉄道唱歌 東海道編 第54番で、
とありますよね。
あの「男山」は八幡市にある山です。
男山・石清水八幡宮については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

源義家が戦った、東北地方の様々な戦い
平泉のところでも説明しましたが、八幡太郎こと源義家について、少し復習しましょう。
ちなみに平泉(岩手県)については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

前九年の役
「前九年の役」では、源義家は東北の安倍氏に苦戦していた父親(源頼義)の命を間一髪で救うなどサポートしました。
そして、源頼義とともに、秋田の清原氏と協力して、安倍貞任をはじめとする安倍氏を滅ぼしました。
後三年の役
「後三年の役」では、清原氏の身内争いに介入し、「清原氏A」と「清原氏B」による清原氏同士の戦いを引き起こさせました。
※なお、清原氏A、Bという表現は便宜的な表現であり、正式な表現ではありません。ここ以外では通じないので気を付けてください。
源義家は清原氏Aの味方をして、秋田県横手市の城に籠城した清原氏Bを食糧不足に追い込み敗北させ、源義家のサポートによって勝利した清原氏Aが奥州藤原氏となるきっかけを作りました。
しかし、後三年の役はあくまで個人の身内争いに半ば勝手に介入した戦いであったのでした。
そのため(報酬と戦果目的で意図的・陰謀的に引き起こした戦いという説もあり)、源義家が本来期待していた朝廷からの報酬は得られなかったのでした。
その後、源義家は約10年ほど不遇な扱いを受けたといわれます。
歌詞「道もせに散る花」とは?
「道もせに散る花」とは、道も狭くなるほど花びらが散らかる、という意味です。「せ」は「狭」という意味になります。
そしてこれは、源義家(八幡太郎)がかつて勿来の関にかかったときに詠んだ歌でもあります。
そして、鉄道唱歌では
世に芳ばしい名前を轟かせた、
八幡太郎(源義家)が歌に詠んだ、
勿来の関も見ていこう」
と歌っているわけです。
茨城県に入り、ここからは関東地方へ
勿来の関を過ぎて、県境を越えると茨城県となり、再び関東地方に入ります!
次は、北茨城市の大津港駅(旧・関本駅)に止まります!

コメント