鉄道唱歌 東海道編の歌詞(焼津の観光・歴史)について、鉄道に詳しくない方にもわかりやすく解説してゆきます!
↓まずは原文から!
草なぎはらひし御劍の
御威は千代に燃ゆる火の
燒津の原はこゝなれや
さらに読みやすく!
草なぎはらいし 御剣の
御威は千代に 燃ゆる火の
焼津の原は ここなれや
さあ、歌ってみよう!
♪くさなぎはらいし みつるぎのー
♪みいつはちーよに もゆるひのー
♪やいづのはらはー ここなれやー
沼津駅→富士駅→富士川駅→興津駅→清水駅→静岡駅→安倍川駅→焼津駅→藤枝駅→島田駅→掛川駅→袋井駅→磐田駅(旧・中泉駅)→天竜川駅→浜松駅
※鉄道唱歌に関連する主要駅のみ抜粋
静岡を出て西へ進み、トンネルをくぐると、焼津駅へ
石部トンネルを過ぎて、かつての東海道の難所だった宇津ノ谷峠をも後にすると、やがて列車は焼津駅(静岡県焼津市)に到着します。

焼津駅(静岡県焼津市)

焼津駅(静岡県焼津市)
静岡県焼津市は、マグロの漁獲量がスゴい!遠洋漁業の拠点
静岡県焼津市は、マグロの漁獲量、また日本有数の水揚げ量を誇る街です。
水揚げ量とは、簡単に言うと魚を釣った量の合計のことです。
もっと厳密に言えば、船から陸に上げた魚の重さの総計を言います。
焼津港の水揚げ量は日本トップクラスになります。また、
- 千葉県の銚子港
- 北海道の釧路港
- 宮城県の石巻港
等と並んで、水揚げ量がトップクラスです。
遠洋漁業の拠点・焼津港
そして焼津市は遠洋漁業の拠点でもあります。
遠洋漁業とは、遠くの海に行かないと取れない魚を釣るための漁業であり、何ヶ月にもわたって、遠くの海に出て行います。
遠洋漁業は、マグロなどの採算性・利益率の高い魚を捕るため、遠洋漁業の漁師は沿岸漁業の漁師と比べて、年収が高くなる傾向にあります。
しかしながら、遠洋で作業するために何ヶ月も行うため、体力的にきつく、定年や引退も早い傾向にあります。
また日本では、昨今の少子高齢化により、全国的に農業・漁業など問わず全ての業界において人手不足になっており、漁業においてもそれは例外ではないようです。
UターンやIターンなどを利用して、漁業や農業に興味がある人たちの、地方移住促進が求められています。
「焼津」の地名の由来は、日本武尊(ヤマトタケルノミコト)にあり!この伝説を知れば、歌詞の意味がわかる
話がずれましたが、焼津市に話題を戻します。
今回の歌詞は一見するとかなり難解です。この歌詞は、焼津市の地名の由来となった、日本武尊(ヤマトタケルノミコト)の伝説からきています。
焼津市の地名は日本武尊(ヤマトタケルノミコト)に由来します。
焼津市に限らず、日本武尊に由来する地名は全国的に多いのです。
日本武尊は神話において、父の景行天皇に東国つまり関東地方を征伐せよと命じられます。
そして日本武尊は、現在の奈良県にあたる大和国のあたりから東へ東へと突き進んでいくのです。
そして焼津の地に差し掛かったところ、目の前に敵がたくさん現れました。まるでRPGのようですね。
そして日本武尊はその目の前に現れた敵を、なんと草薙剣で草をなぎ倒し焼き払ってしまうのです。
草薙剣は本来は天叢雲剣といい、まさにこの時に日本武尊が草を薙ぎ倒し焼いて払ったことから、草薙剣 と呼ばれます。
そして日本武尊が草薙剣で草を焼き払ったことから、「焼きはらった港町」などの意味で「焼津」の地名の由来になっています。
「御威」とは、天皇など尊い方の威厳のことを言います。この場合の威厳とは、つまり日本武尊のことをいいます。
「千代」とは、非常に長い期間や年月のたとえです。
草薙の剣とは?
草薙剣は、元々は素戔嗚尊(スサノオ)がヤマタノオロチと出雲国・島根県東部の斐伊川(木次線のある辺り)で戦った時に、ヤマタノオロチの尻尾から出てきた剣のことをいいます。
これは山陰線鉄道唱歌 第30番でも歌われていますね。
以下の記事でもわかりやすく解説していますので、ご覧ください。

焼津を攻略した後の、日本武尊
日本坂を攻略
日本武尊は焼津を攻略した後、日本坂を攻略します。
日本坂とは、宇津ノ谷峠の南にあり、また石部トンネルのあたりの地名を言います。
横須賀・走水へ 妻の犠牲のもと、東京湾を渡る
やがて、日本武尊は神奈川県横須賀市の走水に至ります。
しかし、東京湾が嵐で荒れていたため、それを嘆いた妻の弟橘姫が海の水に走って嵐を静めました。
それが、「走水」 という地名の由来になっています。
詳しくは、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

命からがら、房総半島へ上陸
やがて東京湾の海を渡った日本武尊は、房総半島に上陸します。
そして自ら犠牲になった妻のことを思って、そこからいつまでもその海から離れませんでした。
君(日本武尊)が離れなかった海のことを「君津」といい、千葉県君津市の由来となっています。
また、君(日本武尊)が離れなかった海のことを「君去らず」→「木更津」ということで、千葉県木更津市の地名の由来となっています。
詳しくは、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

船橋→茨城・群馬などを経て、大和国へ帰還
他にも、千葉県船橋市は日本武尊がかつて船で橋を作ったことに由来しています。
さらに、東国遠征を終えた日本武尊は、茨城県・群馬県・山梨県などを経て、大和国(奈良県)へ帰る途中でした。
山梨県に至ったときのエピソードについては、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

三重県・亀山の地で力尽きる 大和国まで、鶴になって飛んでいく
しかし、その途中、三重県亀山市の地で亡くなってしまいました。
その後、白鳥となって大和国(奈良県)の方へ飛んでいきました。
その日本武尊が、白鳥となってその羽を引く(曳く)野ということで、大阪府羽曳野市の由来になっています。
「曳く」とは「引く」の旧字体です。
全国に、日本武尊のゆかりの地は多い
上記はあくまで一例ですが、このように日本武尊に由来する地名は全国に多いことがお分かりいただけたでしょうか。
焼津市もその一つです。
そして、草薙剣(天叢雲剣)は、いわゆる「三種の神器」の一つとして、名古屋市熱田区の熱田神宮に祀られています。
詳しくは、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。
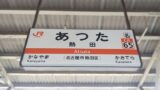
海と富士山の眺めが素敵な、焼津を楽しもう
歴史の話ばっかりで申し訳ありませんが 、焼津には「アクアス焼津」という施設があり、ここはもう海岸線に近いので、この辺りから美しい富士山を遠くに眺めることができます。

焼津の海岸から見た景色。写真ではわかりにくいが、天気が良ければ右奥に富士山を遠くに眺めることができる(静岡県焼津市)
次は藤枝・島田方面へ向かいます!

コメント