鉄道唱歌 東海道編の歌詞を、わかりやすく解説しています!
淀川・高槻の地理・歴史などを、やさしく解説してゆきます!
↓まずは原文から!
くだりし旅はむかしにて
またゝくひまに今はゆく
煙たえせぬ陸の道
さらに読みやすく!
くだりし旅は むかしにて
またたくひまに 今はゆく
煙たえせぬ 陸の道
さあ、歌ってみよう!
♪くだりしはなしは むかしにてー
♪またたくひーまに いまはゆくー
♪けーむりたえせぬ くがのみちー
米原駅→彦根駅→能登川駅→近江八幡駅→野洲駅→守山駅→草津駅→南草津駅→瀬田駅→石山駅→大津駅→山科駅→京都駅→山崎駅→高槻駅→茨木駅→吹田駅→新大阪駅→大阪駅→尼崎駅→芦屋駅→三ノ宮駅→神戸駅
※鉄道唱歌に関連する駅と、新快速列車が停車する駅などを表記
※この区間は「琵琶湖線」「京都線」「神戸線」などの愛称あり
山崎駅を出て、高槻・大阪方面へ
山崎駅を過ぎると、大阪府に入ります。
島本駅からさらに新大阪・大阪方面へ向かうと、
- 高槻駅(大阪府高槻市)
- 茨木駅(大阪府茨木市)
という風に過ぎていきます。
時速約130km 日本一速い新快速
この辺りでは新快速のスピードは時速約130kmにも達し、特急列車に匹敵するほどの速さになってきます。
事実、このエリア(京都線)の新快速列車は、日本一速いとも言われています。
なお、この地域は東海道線ではありますが、京都駅~大阪駅間は特に「京都線」と呼ばれています。
なぜこんなに新快速が速いのか?
なぜこの地域の新快速列車がとても速いのかというと、それは
- 京阪線
- 阪急線
と、JR西日本にとってはライバルとなる、私鉄の路線が2つもあるからです。
競合する大阪~京都間
阪急線・京阪線は、京都~大阪梅田(または淀屋橋)間を、わずか400円台前半で結びます。
そのため、料金が500円台後半とやや劣るJR線は、その反面で速度が圧倒的速い、という強みがあるというわけです。
しかし阪急線は、
- 大阪梅田の中心地
- 京都の中心地である四条河原町
を、それぞれダイレクトに結んで料金400円台前半です。
JR線が、これにも劣らないスピードアップを武器とせざるを得ない理由がわかるでしょう。
淀川
淀川は、滋賀県の琵琶湖から流れて、末は大阪湾に注ぐ、大きな川です。
昔は、淀川での「舟」が主流だった
現在において、滋賀県・京都方面から大阪府までの人々の移動は、鉄道又は車などが主流だと思います。
しかし昔は、
- 旧東海道や西国街道などの、徒歩または馬による陸路
- 淀川を使った水運
などが主流だったのです。

淀川(写真は新大阪駅~大阪駅間のものです)
水面に竿をさして、淀川を漕こいでいた
そう、歌詞にあるように、
そして竿を川の底につけて、
舟を漕いで移動する。
このような移動のやり方が主流だったというわけです。
淀川の「水運」の歴史
淀川は先ほど述べた通り、かつて水運として多く使われた川でした。
水運とは、舟に人や荷物を乗せて運ぶための交通の仕組みです。
昔は列車も(もちろん新幹線も)トラックも航空機もなかった時代だったため、舟に荷物を乗せて運ぶというやり方が、一番効率がよかったのです。
かつて奈良時代に聖武天皇が、
奈良県の加茂(関西本線加茂駅のあるあたり)に、恭仁京を移したのも、木津川を利用した淀川の交通の便が良かったからだ、と言われています。
木津川は淀川と通じているため、大坂(大阪)方面との物資の授受がしやすいからですね。
なお、恭仁京や加茂駅のことについては、鉄道唱歌 関西・参宮・南海編 第9番でも歌われています。
詳しくは、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

かつては「暴れる川」だった淀川 淀川の治水の歴史
また、淀川は古くから暴れる川してもよく認識されてきました。
つまり、嵐や大雨などが起きると川が氾濫してしまい、周辺の地域に甚大な被害をもたらしていたのです。
そのため、淀川は治水が昔から行われてきました。
治水とは、川が氾濫しないために、
- 堤防を造る
- 川の急カーブを無くすために、直線的なルートにする
- 放水路(水の逃げ道)を造る
- ダムを造る
- 川の水の量を調整する
などの工事などすることをいいます。
これによって、川の流れを豪雨のときも適切になるようにするわけです。
そして淀川の治水は、あの豊臣秀吉も尽力してきたことで知られます。
かつての「京街道」に沿った、京阪本線
京阪本線は、かつて
- 京都の山科にある髭茶屋追分
- 大阪の高麗橋
をそれぞれ結んでいた、京街道の宿場町に沿った路線でもあります。
京街道とは、かつて豊臣秀吉が整備した、京都の山科と大坂を結ぶための街道のことです。
東海道と京街道を分けた、山科の髭茶屋追分
髭茶屋追分とは、京都の山科にある、東海道と京街道の分かれ道のことです。
「追分」とは、分かれ道のことを意味します。
髭茶屋追分は、
- 西へ進めば、京都の三条大橋へ
- 南西へ分かれて進めば、淀・枚方・守口を経て、大坂の高麗橋へ
それぞれ至ります。
宇治川の堤防「太閤堤」がきっかけとなった、京街道
京街道は、元々は淀川の氾濫を防ぐために、宇治川に太閤堤という堤防を築いたことが発端でした。
この堤防の上の道路が(人が進むのに)通りやすかったため、京街道の発端となったともいわれています。
京阪本線は、
- 淀
- 枚方
- 守口
といった、かつての京街道の宿場町を多く経由します。
淀川の「舟」も昔の話 今は鉄道がたくさん走る道
話を戻しますが、歌詞にあるように、
のでした。
そんな話も、歌詞にあるように、もはや「昔の話」なのです。
そして今は、
というわけです。
今や、時速130kmの新快速・時速285kmの新幹線が走る道
そして現在は、時速130kmのJR・新快速が走り、さらに東海道新幹線が時速285kmで進んでいくのだから、とても凄いですよね。
さらには阪急列車も走るため、負けていません。
私が東海道新幹線に乗ったとき、GPSアプリで高槻周辺で新幹線の速度を測ったのですが、時速285kmと出ていました。
東海道新幹線は、大阪~名古屋間でにおいて近鉄線と競合している理由もあるからか、さすが速いです。
高槻駅
列車は間もなく高槻駅(大阪府高槻市)を過ぎます。
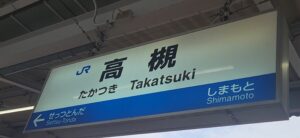
高槻駅(大阪府高槻市)
西国街道の宿場町・芥川宿
大阪府高槻市は、
かつて西国街道の、
芥川宿があった場所です。
西国街道とは、
- 京都の東寺を出発して、
- 山陽地方を経由して、
- 九州にまで至る
という、昔の人が徒歩または馬ではるばると旅をした道です。
かつて菅原道真公も左遷時に通った道
菅原道真公も、かつて九州の大宰府に左遷になったときに、西国街道を通ったと言われています。
その際、朝廷からの援助はほぼ無かったといわれています。
淀川のやや北を通っていた西国街道
西国街道は、淀川のやや北を通っていました。
高槻の芥川宿を出ると、
- 大阪の千里中央あたりを通り、
- 伊丹を南西に進んで、
- 西宮→加古川→姫路へと進んでいた
ようです。

芥川(東海道新幹線の車窓より)
次は、茨木・吹田・新大阪方面へ
やがて列車は、茨木・吹田・新大阪方面へ向かっていきます!

コメント