鉄道唱歌 山陽・九州編の歌詞(佐世保の観光と歴史)について、鉄道に詳しくない方にもわかりやすく解説してゆきます!
↓まずは原文から!
その名しられて大村の
灣をしめたる佐世保には
わが鎭守府をおかれたり
さらに読みやすく!
その名しられて 大村の
湾をしめたる 佐世保には
わが鎭守府を おかれたり
さあ、歌ってみよう!
♪そーのなしられて おおむらのー
♪わーんをしめたる させぼにはー
♪わがちんじゅふを おかれたりー
鳥栖駅→新鳥栖駅→吉野ヶ里公園駅→佐賀駅→鍋島駅→久保田駅→江北駅(旧・肥前山口駅)
(佐世保線)
江北駅(旧・肥前山口駅)→武雄温泉駅→有田駅→早岐駅→佐世保駅
※鉄道唱歌に関連する駅と、その他主要と思われる駅を筆者の独断と偏見でピックアップしたものを記載
現在の長崎本線は、鉄道唱歌当時のルートとは異なる
早岐駅(長崎県佐世保市)で佐世保線を北西へ進むと、佐世保線の終点・
- 佐世保駅(長崎県佐世保市)
に到着します。

佐世保駅(長崎県佐世保市)

佐世保駅(長崎県佐世保市)
かつて佐世保線は、長崎本線の一部だった
佐世保線は、かつての長崎本線の一部でした。
すなわち、
- 現在の江北駅(かつての肥前山口駅)
- 早岐駅
の区間は、もともとは長崎本線の一部でした。
後に、有明海沿い・肥前七浦駅経由が長崎本線に
しかし、後に江北駅から、有明海沿いに南下する
- 肥前七浦駅
経由で諫早駅まで結ぶ路線が、正式に長崎本線となりました。
すると、
- かつて長崎本線だった江北駅~早岐駅までは、佐世保線
- 早岐駅~大村駅~諫早駅までは、大村線
と改められました。
つまり、鉄道唱歌の時代と現代では、長崎本線のルートは違うのです。
逆にいえば、鉄道唱歌のルートは
- 佐世保線→大村線
と繋ぎ、諫早駅からは再び長崎本線、という流れになります。
そして現代では、
- 江北駅~早岐駅~佐世保駅
の間が、現代の佐世保線という扱いになっています。
以上のような理由が、早岐駅がスイッチバックの構造(先頭から突っ込んで、折り返す線路の構造)になっている理由です。
鎮守府が置かれた都市・佐世保市
「鎮西」とは?
鎮西とは、元々は「西を鎮める」という意味になります。
ここでいう「西」とは、「西国」、もっといえば「九州」のことをいいます。
ここでは、「鎮西=九州」のような意味合いで解釈しても問題ないでしょう。
「天然の良港」佐世保

佐世保の景色(長崎県佐世保市)
長崎県佐世保市は、かつて鎮守府と呼ばれる、海の守りの要が置かれた場所になります。
また、海外に近い外国からの入り口からの防衛の要として、発展してきた街であります。
佐世保市は非常に入り組んだ地形にある防衛に適した街であり、これは「天然の良港」という風に言われます。

佐世保の景色(長崎県佐世保市)

佐世保の景色(長崎県佐世保市)
「造船の街」として栄えてきた佐世保
佐世保は先述の通り、古くから多くのリアス式海岸・複雑な海岸線を持ち、その複雑な地形から海の防御力に優れていました。
佐世保には多くの造船工場やドックなどが存在します。
ドックとは、船の周りを取り囲んで、高い場所から造船作業を出来るようにした凹みのことです。船渠とも呼ばれます。
海軍工廠の造船所跡を引き継いで始まった、SSK(佐世保船舶工業)
佐世保には佐世保重工業(SSK)と呼ばれる工場・会社があります。
佐世保のSSKは、元々は「佐世保船舶工業」という社名だったため、SSKという略号となっています。
SSKは元々は海軍工廠の造船所から受け継つぎ、民間に引き渡されたところから始まりました。
海軍工廠とは、つまり海軍が船を作る造船所のようなもので、当時は非常に高い軍事機密によって守られていました。
鎮守府が置かれた街・佐世保
鎮守府とは、旧日本海軍における「海の守り神」のような存在です。転じて、海の防衛の拠点という意味合いになるわけです。
おもな鎮守府には、 佐世保の他に、
- 神奈川県横須賀市
- 京都府舞鶴市
- 広島県呉市
が挙げられます。
これらを総合して、「四大鎮守府」などのように呼ばれます。
横須賀鎮守府については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

呉鎮守府については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

舞鶴鎮守府については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

米軍によってもたらされた、ハンバーガーの文化
佐世保には戦後、アメリカ軍の海軍基地が置かれています。
そして、佐世保のアメリカ軍の方々によってハンバーガーの文化がもたらされました。
これが「佐世保バーガー」の始まりであるという風に言われます。
佐世保は海軍や、アメリカ軍の海軍と共に発展してきた町であるという風にも言われます。
海軍や軍人さん達が街にたくさん住めば、彼らをもてなすための商業施設も増えるので、人口が増えて街が発展していく、というわけですね。

佐世保の景色(長崎県佐世保市)
JR西日本最西端の駅・佐世保駅

佐世保駅(長崎県佐世保市)
佐世保駅は、JR線の駅としては日本最西端と言われます。
JR線の東西南北の最果て駅
以下に、JR線の東西南北の最果ての駅を列挙します。
- 最北端の駅 稚内駅
- 最東端の駅 根室駅
- 最西端の駅 佐世保駅
- 最南端の駅 西大山駅
なお西大山駅は鹿児島県の本当に南にある駅であり、北緯31度になります。
「あれ?最南端の駅は
- 枕崎駅(鹿児島県枕崎市)
じゃないの?」
というイメージもあるかもしれませんが、緯度的にいうとやや西大山駅の方が南となります。
西大山駅からは、開聞岳、通称・薩摩富士の眺めが最高です。
西大山駅については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。


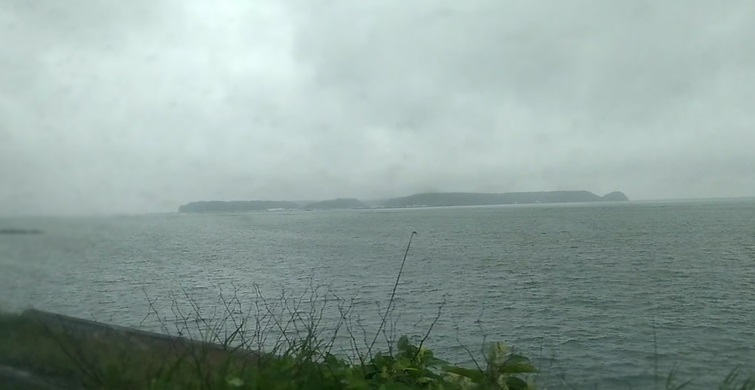
なお、モノレールも含めれば、日本最南端・日本最西端の駅は沖縄県になります。
さらに平戸方面へ向かう、松浦鉄道
佐世保駅からは、さらに北西の平戸方面へ向かう松浦鉄道が出ています。

松浦鉄道・佐世保中央駅(長崎県佐世保市)
次回は大村線で、大村・諫早方面へ
今回のメインであった佐世保の街や歴史、さらに先述の松浦鉄道の歴史などについては、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

次回は再び早岐駅まで戻り、大村線で南へ向かって、大村・諫早方面へ向かいます!

コメント