鉄道唱歌 北陸編の歌詞(妙高はねうまライン・妙高高原~直江津)について、鉄道に詳しくない方にも、わかりやすく解説してゆきます!
↓まずは原文から!
道をしへしも此のあたり
ふゞきの中にうめらるゝ
なやみはいかに冬の旅
さらに読みやすく!
道おしえしも 此のあたり
ふぶきの中に うめらるる
なやみはいかに 冬の旅
雪の上に道しるべの竿を立てて、
道を教えていたのも、この辺り(妙高高原駅~高田駅~直江津駅の区間)である。
吹雪の中に(線路が)埋まってしまうという、
悩みはいかにすべきか、冬の旅路よ。
長野駅→豊野駅→牟礼駅→黒姫駅(旧・柏原駅)→妙高高原駅(旧・田口駅)
(えちごトキめき鉄道妙高はねうまライン)
妙高高原駅→二本木駅→新井駅→上越妙高駅→高田駅→春日山駅→直江津駅
※鉄道唱歌に関連する主要駅と、その他主要と思われる駅を筆者の独断と偏見でピックアップ
妙高高原からは、一気に山を下り直江津方面へ
妙高高原駅(新潟県妙高市)からは新潟県に入り、ここからは第三セクター線の
- 「えちごトキめき鉄道 妙高はねうまライン」
に乗って山を下り、直江津方面へ向かいます。
この区間は、標高510mの標高差を一気に下ります。
冬には「はねうま」が浮かび上がる妙高山
なお、えちごトキめき鉄道のこの区間は「妙高はねうまライン」といいます。
「はねうま」とは、妙高山(標高2,454m)という山の中腹に、冬の雪景色になると、まるで「跳ね馬」のシルエットが浮かぶことから、このような名前が着いています。

妙高山(長野県・黒姫駅付近より)
妙高山とは?そもそも、「妙高」とは?
妙高山(標高2,454m)は、妙高高原駅の裏側にある神々こうごうしいルックスの山です。
いかにも神様が宿っていそうな形の山であり、昔は本当に山に神様が宿ると信じられていました(山岳信仰)。
妙高とは、インド神話において「世界の中心となる山」のことです。
確かに、妙高山はそれにふさわしい形をしているような気がしますね。
昔の人々からそう信じられてきても、無理はなかったでしょう。
「妙高はねうまライン」は、元々は信越本線の一部だった
北陸新幹線の開業により、第三セクターへと経営分離された区間
えちごトキめき鉄道妙高はねうまラインも、元々はJR信越本線の一部でした。
しかし、北陸新幹線の開業により、長距離移動の役割は、特急列車から新幹線に譲られたのでした。
このことにより、特急列車は廃止となってしまいます。
特急料金の存在は、JRにとって貴重な収入源という位置付けにもありました。そのため、特急列車廃止ということは、在来線の利益が減少することに繋がり、JR社としては在来線の存続は、大きな負担となってしまいます。
そのため、JR社の立場としては本来は在来線そのものを廃止したいところです。
しかし、在来線を廃止すると、今度は逆に地元住民が困ってしまうことになります。
そのため、地元住民のために配慮して、経営をJR社から(新たに発足した組織へ)移管されたものが、第三セクターの路線ということになります。
ここから先は、越後国・新潟県の旅
ここからは、えちごトキめき鉄道妙高はねうまラインに乗って、直江津方面へ向かって進んでいきます。
妙高高原駅の標高は、約510mとなります。
一方、海に近い直江津駅の標高は約4mですから、この500m差を一気に駆け下りてくることになります。

妙高高原駅にある、「標高510m」の表記(新潟県妙高市)
妙高高原駅を出て、とても長い新潟県の旅へ
そして、妙高高原駅を出ると、ここからは新潟県の旅になります。
新潟県は、南北が非常に広い県になります。
そのため、その旅は気の遠くなる長さになることもあり、それなりの気持ちの準備をする必要があります。
その距離は九州でいうと、なんと実に福岡から鹿児島までの距離に相当します。
このように、新潟県はとても広いため、新潟県は京都に近い順に、
- 上越
- 中越
- 下越
に分かれています。またそれぞれ、
- 上越の中心都市:上越市
- 中越の中心都市:長岡市
- 下越の中心都市:新潟市
になります。
第50番の「富山」までは、新潟県内の旅
鉄道唱歌・北陸編では、ここ(第32番)から第50番の富山に至るまでは、ずっと新潟県内の旅ということになります。
新潟県が、いかに広いかというのがわかりますね!
スイッチバックが残ることで有名な、二本木駅
山を一気に下りると、一旦上越市の市域に入り、二本木駅(新潟県上越市)に着きます。
二本木駅は、珍しいスイッチバックの駅として有名です。
スイッチバックとは、
- 一旦、枝分かれした路線にバックして入り、
- お客さんを乗り降りさせてから、
- 再び本線に戻って、坂を上っていくなどの方式の線路
をいいます。
昔の列車は、坂道や勾配にとても弱かったのでした。
そのため、少しでも列車の負担を軽減するために、この形式が用いられていました。
このスイッチバックは、
- これから列車が、急な坂を登るために、
- 一旦、枝分かれした線路に退避し、
- ここから加速のための助走をして、一気に登る
というステップを踏むために設けられました。
現在では、列車の性能も向上しています。そのため、スイッチバックは不要となり、廃止されていくのが一般的です。
しかし二本木駅の場合は、現在でも残る、数少ない貴重な「スイッチバック駅」として、もはや観光名所にも等しいような価値があります。
再び妙高市に戻り、新井駅へ 市境を二度通過する
二本木駅あたりの市境は複雑であり、二本木駅においては、一旦上越市に入ります。
しかしながら、すぐまた市境を過ぎてゆき、妙高市に戻ってくるという形となります。

えちごトキめき鉄道(妙高はねうまライン)・新井駅(新潟県妙高市)
新井駅(新潟県妙高市)は、妙高市の中心駅です。
かつては新井市の駅でしたが、合併により妙高市になったため、妙高市の中心駅となっています。
北陸新幹線も止まる駅・上越線妙高駅
やがて、再び上越市に入り、新幹線の停車する
- 上越妙高駅(新潟県上越市)
に着きます。
上越妙高駅は、上越市と妙高市がその駅名決定の際に、かなり論争になったようです。
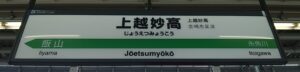
北陸新幹線・上越妙高駅(新潟県上越市)
なお、上越市や上越妙高駅の「上越」とは、上越新幹線が止まる駅、という意味ではありません 。
上越新幹線の「上越」 とは、あくまで
- 上野国(群馬県)
- 越後国(新潟県)
を結ぶという意味になります。
それぞれの頭文字をとって、「上越」というわけです。
上越妙高駅はあくまで北陸新幹線の駅であるため、上記のことを知らないと、
と疑問に思ってしまうことになります。
高田駅を過ぎ、春日山駅へ 上杉謙信の本拠地
高田駅(新潟県上越市)は、前回も説明した通り、高田市の中心だった駅です。
高田市は現在は無く、合併により上越市となっています。
やがて、上越市の中心地域ともいえる、
- 春日山駅(新潟県上越市)
に着きます。
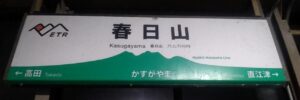
えちごトキめき鉄道(妙高はねうまライン)・春日山駅(新潟県上越市)
春日山城は、かつての上杉謙信の居城であります。
ちなみに、春日山の由来は、奈良県の春日大社から神様をお招きしたことに由来します。
上杉謙信は、戦国時代最強と言われた武田信玄と、川中島で互角に戦った人物として知られます。
また、上杉謙信は戦いの神様と言われ、生涯において無敗伝説をほこり、毘沙門天の化身と言われました。
あの織田信長も、「手取川の戦い」では上杉謙信に敗れたという風に言われています。
川中島の戦いについては、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

春日山駅の近くには、上越市の市役所があります。
そのため、この辺りがおおよそ上越市の中心であるともいえます。
春日山駅の近くには、青春18きっぷのユーザーの強い味方である「快活CLUB上越市役所前店」があります。
次回は、直江津駅に到着
いよいよ日本海沿岸も近くなり、列車はやがて直江津に到着します。

コメント