鉄道唱歌 関西・参宮・南海編の歌詞(亀山、関西本線、四日市)について、鉄道に詳しくない方にもわかりやすく解説しています!
↓まずは原文から!
左は尾張名古屋線
道にすぎゆく四日市
舟の煙や絶えざらん
さらに読みやすく!
左は尾張 名古屋線
道にすぎゆく 四日市
舟の煙や 絶えざらん
さあ、歌ってみよう!
♪ひだりはおわりー なごやせんー
♪みーちにすぎゆく よっかいちー
♪ふねのけむりやー たえざらんー
木津駅→加茂駅
(関西本線)
加茂駅→笠置駅→(木津川橋りょう)→大河原駅→月ヶ瀬口→伊賀上野駅→佐那具駅→柘植駅→(鈴鹿峠のトンネル)→関駅→亀山駅→四日市駅→桑名駅→長島駅(→至・名古屋駅)
※鉄道唱歌に関連する主要駅のみ表記
亀山駅を出ると、四日市・桑名・名古屋方面へ寄り道
亀山駅(三重県亀山市)からは現在の関西本線に従って、名古屋方面向かってゆきます。
今回の寄り道は名古屋までは行かず、「長島」まで
実際には名古屋までは行かないのですが、その少し手前の長島まで行くことになります。
長島とは、これより先・桑名の少し先にある、
- 揖斐川
- 木曽川
の間にある島(陸地)になります。
詳しくは次回解説します。
歌詞冒頭は、「掛詞」?
歌詞冒頭は恐らく、
と、
をそれぞれ掛けている、いわゆる掛詞と思われます。
石油コンビナートの街・四日市へ到着!
関西本線を名古屋方面へ向かってしばらくゆくと、四日市駅(三重県四日市市)に着きます。
窓の景色は、四日市ならではの石油化学コンビナートの工場や煙突などの景色が目立つようになります。
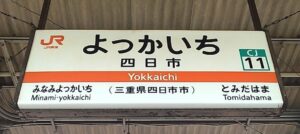
四日市駅(三重県四日市市)

四日市駅(三重県四日市市)
三重県の最大都市・四日市
三重県四日市市は、高度経済成長期の1950年代~1960年代において、石油化学コンビナートなどを中心に栄えてきた都市になります。
人口(約31万人)では県庁所在地の津市(人口約28万人)を上回っています。そのため、三重県の最大都市ということになります。
三重県の県庁所在地は津市であり、また1950年代頃までは津市が三重県最大の都市でありました。
ところが、1960年代の高度経済成長期になって四日市市が次々に石油化学コンビナート等を誘致してきた事などにより、人口が急速に増えてきたのでした。そのため、四日市市の方が人口や規模の面で大きくなったというイメージになります。
東海道の宿場町でもあった四日市
東海道「四日市宿」
四日市市には、東海道五十三次の宿場町である四日市宿がありました。
東海道とは、江戸時代のまだ鉄道や高速道路が無かった時代に、人々が(徒歩または馬で)約20日かけて江戸~京都間を移動するために整備された道路です。
その旅人たちが泊まるための町を、「宿場町」といいます。
この宿場町は、江戸~京都の間で全部で53箇所あったため、東海道五十三次と呼ばれます。
伊勢方面との分かれ道「日永の追分」も
また四日市には、東海道と伊勢方面への分かれ道である、日永の追分があります。
「追分」とは?
追分とは、昔の言葉で「分かれ道」のことです。
また、全国各地にそれに由来する地名や駅名などが、今でも残っています。
例:
日永の追分では、桑名方面から東海道を歩いて来た旅人たちにとっては、
- 左は、伊勢神宮方面
- 右へ向かうと、そのまま東海道(鈴鹿峠、京都方面)
ということになります。
高度経済成長期の四日市を震撼させた公害病「四日市ぜんそく」
四日市市というと、どうしても四大公害病の1つである「四日市ぜんそく」の話題とは切っても切れなくなります。
もちろん、四日市市としては自分たちの街に対して「ぜんそく」などの負のイメージは持たれたくないことは重々承知しております。
しかしながら、義務教育の社会科で習う以上、どうしてもこの話題は避けて通れませんことをご了承ください。
「四日市ぜんそく」は、いわゆる四大公害病の一つであり、他の三つとして
- 熊本県水俣市の「水俣病」
- 富山県の「イタイイタイ病」
- 新潟県の、新潟水俣病
があります。
上記は、各都市のイメージを損ねる意図は毛頭ありませんので、何卒ご賢察願います。
また、現在の四日市をはじめ、水俣市・富山県(神通川流域)、新潟県においても、現代における環境事情は地元の人々の長年の弛まぬ努力により大きく改善されているものと確信しております。
なぜ「四日市ぜんそく」が起きてしまったのか?
では「四日市ぜんそく」がどうして起きたのかというと、それは先述の通り、1960年代に石油化学コンビナートの大量誘致などが行われたことが一つの要因です。
日本人みんながウハウハだった、高度経済成長期
高度経済成長期の日本においては、現代の多くの高齢者世代がバリバリの若手だった時代でありました(団塊の世代)。
そのため、働く人(労働人口)も多く、今の人手不足が深刻な日本からすれば羨ましい限りのイケイケだった時期があったのです。
そんな時代でしたから、工場を作れば作るほど儲かって、またモノを造れば造るほど儲かる時代でもありました。
なぜなら、今の日本はスマホも自動車もテレビなども当たり前のように持ってますが、当時の日本人は自動車も洗濯機もテレビも持ってなかった時代なので(これらは「三種の神器」とも呼ばれた)、これらを大量生産して安く売れば儲かるという時代でした。
工場を次々に誘致 雇用も人口も税収も増えて、どこもウハウハ状態に
こうして工場が次々に増えていくと、街にとっても、働く人も増えて人口も増えると、税収アップも期待でき、街の発展にも繋がります。
こうして、高度経済成長期の日本ではある意味みんなウハウハでイケイケな状態でもありました。
そのため、地方自治体は次々に様々な企業や工場を地元に対して誘致してくるようになったのです。
当時どんどん伸びていた、新しいエネルギー「石油」
まだ高度経済成長期の当時は、エネルギーが従来の「石炭」から、新しく「石油」に移り変わる時期でもありました。
現在の我々がそうであるように、石油というものは電車や車や発電など、何を動かすにしても重要なエネルギーです。
そのため、みんな喉から手が出るように欲しいわけです。
そんな時代でしたから、石油コンビナートを造ればそれだけ儲かるという世の中の雰囲気になってもおかしくなかったでしょう。
ここからが問題 原油は「不純物」を取り除かないと、そのままでは使えない
しかし、問題はここからです。
石油は、自然のままで存在しているものではありません。「原油」という、不純物(本来の目的に必要のないもの)が混じった形で、自然の中に存在します。
石油をエネルギーや商品として使えるようにするには、原油から不純物を取り除かなければなりません。
不純物を取り除く「精製」のときに、有害物質が発生
この不純物を取り除いて石油をエネルギーや商品として使えるようにするには、高温に熱する必要があります。
高温に熱すると、有害物質(硫黄酸化物)とともに煙突から煙という形で大気に出ていってしまいます。
その煙突から出た(硫黄酸化物を含んだ)煙を人々が吸うことで、ぜんそく(喘息)という形で現れてくるのです。
石油は「黒い煙」が出ないため、初めは誰も大気汚染に気づかなかった
しかも、石油を燃やしても、石炭のように黒い煙が出るわけではありません。
黒い煙であれば「えっ、空が汚れてるぞ!!」といった具合にわかりやすそうなものですが、石油を燃やしても空が黒くならないため、空が汚れていることに当初は誰も気付かなかったのです。
石炭のように空が黒く汚れないことから、石油は当初、クリーンなエネルギーだという風に誤解・油断されていた部分もありました。
そして石油で汚れた大気は、黒くないため「白いスモッグ」と形容されるようになりました。
政治問題にもなった四日市ぜんそく 対策が急務に
四日市ぜんそくは、1960年代から1970年代にかけて、国会に取り上げられるレベルにまで政治問題となり、対策が急務になりました。
四日市ぜんそくへの対策と、不断の努力
石油の原料となるのは先述の通り原油ですが、当時輸入されてきた原油には硫黄酸化物を多く含んでいたのでした。
そのため、公害以降は硫黄酸化物が少ない原油を仕入れるという形で対処してゆきました。
「脱硫装置」で、大気中に硫黄酸化物を出さない仕組みへ
また、煙突から排出される煙突からも、「脱硫装置」と呼ばれる硫黄酸化物を取り除く仕組みを導入することで対処してゆきました。
これによって、四日市ぜんそくの原因となった硫黄酸化物の大気への排出は、劇的に改善されることになりました。
現在では、とても空気が綺麗な街に
四日市ぜんそくの話ばかりになって恐縮ですが、このように過去の反省と、人々の弛まぬ努力によって、現代の環境状況は大きく改善されています。
現代の我々の生活も、高度経済成長期の当時の恩恵を大きく得られているわけです。
しかし、その背後には公害という負の遺産、そして犠牲になった人々の無念や、公害を改善してきた人々の並々ならぬ努力があったことも忘れてはならないのですね。
近鉄四日市駅と、JR四日市駅の関係 桑名に向けて少し休憩もアリ
三重県最大の駅・近鉄四日市駅
現在の四日市市の中心地はJR四日市駅の周辺ではなく、西へ約1kmほど離れた近鉄四日市駅の周辺の方がより繁華街的に栄えています。
(近鉄四日市駅の方が、JR四日市駅よりもなんと10倍も利用者が多いとのこと。)
やはりこの地域ではJR線よりも近鉄線の方が優勢であり、仕方ない部分はあります。
そのため、JRの青春18きっぷで初めて四日市駅に来た人は、JR四日市駅で降りた瞬間に「アレッ!?」て思うかもしれません。
主な飲食店や商業施設などは、どちらかといえば近鉄四日市駅周辺の方に集中しています。
しかし、JR四日市駅の周辺にも、徒歩5分程度でファミマがあるため、そこで簡単な買い物を済ませることはできます。
桑名駅での休憩も視野に
JR四日市駅から近鉄四日市駅までは約1kmほどの距離であり、道が比較的真っ直ぐなため、歩いて行けなくもないです。
しかし青春18きっぷユーザーの方は、四日市駅からは桑名駅(三重県桑名市)が比較的近いため、買い物や飲食は桑名まで我慢するという選択肢もあります。
自身の旅の行程や、体力などに合わせて、ベストな選択肢を検討しましょう。
四日市の次は、桑名へ
次回は、桑名に止まります!

コメント