鉄道唱歌 関西・参宮・南海編の歌詞(橋本、九度山、高野山など)について、鉄道に詳しくない方にもわかりやすく解説してゆきます!
↓まずは原文から!
叫ぶ驛夫に道とへば
紀の川わたり九度山を
すぎて三里ぞ高野まで
さらに読みやすく!
叫ぶ駅夫に 道とえば
紀の川わたり 九度山を
すぎて三里ぞ 高野まで
さあ、歌ってみよう!
♪さーけぶえきふに みちとえばー
♪きのかわわーたり くどやまをー
♪すーぎてさんりぞ こうやまでー
高田駅→大和新庄駅→御所駅→掖上駅→吉野口駅→五条駅→隅田駅→橋本駅→粉河駅→舟渡駅→田井ノ瀬駅→和歌山駅
(南海高野線)
橋本駅→九度山駅→高野下駅→極楽橋駅
※鉄道唱歌に関連する主要駅のみ表記
橋本駅(和歌山県橋本市)に到着

五条方面から、橋本方面へ(関西本線)(和歌山県)
奈良県と和歌山県の県境を越え、隅田駅からは和歌山県に入ります。
やがて、
- 橋本駅(和歌山県橋本市)
に到着します。
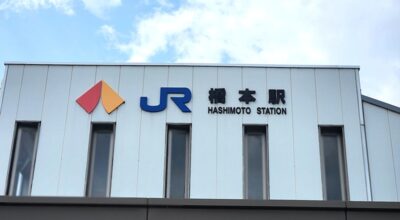
JR和歌山線・南海高野線・橋本駅(和歌山県橋本市)
東西南北への、交通の要衝・橋本市
和歌山県橋本市は、
- 大阪から高野山へ、南北に向かう街道
- 奈良から和歌山へ、東西に向かう街道
が、まさに十字に交差する場所にあります。
そのため、交通の要衝として、古くから多くの旅人で行き交うなどして栄えてきました。
現代でも、JR和歌山線と南海高野線が交差する場所でもあります。
また橋本市は、高野山へ登る1つ手前の重要な街でもあります。
紀ノ川の「水運」によって栄えてきた橋本 木材の集散地
橋本市は上記の交通の利便性に加え、紀ノ川という(和歌山方面へ向かう)川が、東西に流れています。
そのため、木材や織物などの産物の集散地として栄えてきました。
「集散地」とは?
集散地とは、例えば
- 山地で採れた木材を、一時的に集めて、保管・保存しておく
- 販売で必要になったときに、ストックから取り出して、出荷する
ための場所です。
集まる地・散る地と書いて、「集散地」です。
また、モノを保管するためには、
- 蔵
- 倉庫
- コンテナ
などが利用されます。
コンテナとは、いわば移動可能な倉庫のようなものです。
倉やコンテナの役割については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

橋本の南を流れる「紀ノ川」
和歌山県では「紀ノ川」 奈良県では「吉野川」
橋本駅の南側には、先ほど述べたように紀ノ川という川が、東西に流れています。
「紀ノ川」は、あくまで和歌山県での呼び名になります。
奈良県では、「吉野川」という名前になります。
このように、同じ川でも県ごとに名前が異なる川は、全国の他地域でもよくあります。
詳しくは、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

橋本駅からは、南の高野山へ
歌詞では、橋本駅で降りると、駅夫に道を聞いてから、高野山に登ることになっています。
今でいうと、駅員や観光案内所等に道をたずねるイメージでしょうか。
現代では、駅員に道を聞くよりは、むしろ駅前の観光案内所に聞く方が、無料かつより丁寧に教えてくれるため、安心です。
当時は、(橋本から)馬車か徒歩で高野山へ向かった?
鉄道唱歌の時代は、橋本駅から
- 馬車・人力車
- または(自力で)徒歩
などを使って、高野山まで行ったのかもしれません。
現代では、「南海高野線」で
しかし、現代では南海高野線という路線が出ています。
橋本駅から南海高野線で
- 九度山駅(和歌山県伊都郡九度山町)
を過ぎます。
50パーミル(‰)もの急勾配を登っていく
高野下駅(こうやしたえき、和歌山県伊都郡九度山町)を過ぎると、急な登りの山岳地帯となり、50パーミル(‰)という勾配になります。
「パーミル(‰)」とは、勾配を現す単位であり、20パーミルを越えると結構きつい坂になります。
なので、50パーミルは相当きつい坂になります。
詳しくは、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

東京スカイツリーの高さ(634m)も越えて、高さ800mの高野山へ
極楽橋駅(和歌山県伊都郡高野町)からは、東京スカイツリーの高さ(634m)を超えて、高野山の頂上へ向けて行くことができます。
九度山町や高野町のある「伊都郡」は「いとぐん」と読みます。
橋本→九度山→高野山
かつて女人禁制だった高野山
高野山は、明治時代までは女人禁制でした。
つまり、女の人は入ってはいけなかったのです。
これはなにも「女性差別」とか、そういう理由からではありませんでした。
例えば、男性が女性の体を見て性欲でムラムラしてしまい、修行に集中できないということにならないように、女人禁制ということになってたのでした。
これは弘法大師・空海のお母さんですら同じで、山には入ってはなりませんでした。
お母さんに9度会いに行っていた、九度山
空海は、香川県善通寺市の出身だったのですが、お母さんも和歌山県まで来ていたのでした。
つまり、お母さんも高野山に近いとこまで来ていたわけです。
そこで空海が(高野山に入れない)お母さんに9回も会いに行っていた場所が、高野山のふもとにある九度山だったわけです。
つまり弘法大師・空海がお母さんに9回会いに行った場所だから「九度山くどやま」というわけです。
九度山は高野山のふもとにあり、
- 南海高野線・九度山駅(和歌山県伊都郡九度山町)
が最寄駅となります。
真田(さなだ)親子が流されてきた、九度山
また、九度山は、
- 真田正幸
- 真田幸村
の父子が、織物を造って、生計を立てていた場所でもあります(ただし、これは諸説あり)。
長野県・上田に拠点を置いていた、真田家
もともと
- 真田幸村
- 父親の、真田正幸
は、長野県の上田市という場所の出身でした。
長野県上田市は、北陸新幹線の駅もある、長野県では長野市・松本市に次ぐ、第3位の街です。

信州・上田は、当時
- 甲斐国(現在の山梨県)
- 三河国(現在の愛知県東部)
などを中心に領土を持っていた「徳川家」と、越後(新潟県)の「上杉家」との間で、ちょうど地理的に中間地点にありました。
そのため、どっちにつけばいいかわからない板挟みの状態だったのでした。
結局、上田の真田家は、越後の上杉家につくことを決定したのでした。
そのため、徳川家の怒りを買ってしまいます。
上田城は徳川軍を二度も撃退
そして戦国時代末期に、これを気に食わない徳川家は、上田に対して2回も兵を向けて攻めています。
しかし、上田城はなんと徳川軍を2回ともはね除けて(撃退して)います。
そのため、上田城は「落ちない城」と言われ、受験生にとっても「落ちない」という響きが縁起が良く、上田城のそばにある「真田神社」は合格祈願のため多くの受験生が訪れています。
しかしこの真田家の二度にわたる撃退も、さらに徳川家の恨みを買ってしまいます。
「関ヶ原の戦い」で敗北
そして1600年の「関ヶ原の戦い」。
- 徳川家と、徳川家に味方にする全国の武将を中心とする「東軍」
- 徳川家に敵対する、全国の武将を中心とする「西軍」
の戦いでした。
真田家はもちろん徳川家に敵対する側なので、「西軍」として戦いました。
結果、東軍の勝利。
西軍についた武将や大名たちは、
- 死刑になった者(例えば、石田三成や小西行長など)が存在したり、
- それまでの領地や石高を大きく減らされて(減封)、遠隔地に飛ばされたり、
などの不遇・冷遇措置を受けたのでした。
真田家も、徳川家からかなり恨みと怒りを買っていましたので、死刑を言い渡されました。
助命嘆願により、刑をまぬがれ九度山へ流される
ただし、幸村の兄にあたる真田信之による助命嘆願によって、なんとか死刑だけは免れたのでした。
つまり、「命だけは勘弁してくださいませ」とお願いしたわけです。
しかし、その代わり和歌山の九度山に配流されてしまいました。
困窮をきわめた九度山の生活 父、無念の最期
そして親子二人の九度山での生活は、困窮を極め、なかなか過酷なものだったと言われています。
父親の真田昌幸は、晩年は病気に悩まされ、
という無念の遺志を残して、1611年に亡くなりました。
この真田親子は、この過酷な九度山での生活において「真田織」という織物を作って売り、生計を立てていたという風にも言われています。
「大坂の陣」で真田幸村の奮闘も、無念の最期
そして1615年、「大坂の陣」での徳川との決戦です。
江戸幕府を開いたにも関わらず、大坂ではいまだに豊臣秀吉の息子の秀頼と、妻の淀殿が支配していました。
これを気に入らない徳川家康は、大坂城へと兵を向けたのでした。これが「大坂の陣」です。
真田幸村は、秀頼と淀殿を守るため、徳川家康の軍に向かっていったのでした。
真田幸村は、徳川家康に対して二度も自害を覚悟させるほどの、まさしく大健闘をしたのでした。
しかし、大阪市の天王寺あたりで休んでいるところを、無念にも討たれてしまったのでした。
これが歴史上圧倒的人気を誇る、真田幸村の最期となってしまったのでした。
橋本→九度山の次は、高野山へ
次回は、高野山の話題となります!

コメント