鉄道唱歌 関西・参宮・南海編の歌詞(紀ノ川、吉野川、吉野)・観光・歴史について、わかりやすく解説しています!
↓まずは原文から!
水上とほく雲ならで
立てるは花の吉野山
見て來んものを春ならば
さらに読みやすく!
水上とおく(遠く) 雲ならで
立てるは花の 吉野山
見て来んものを 春ならば
さあ、歌ってみよう!
♪みなかみとおくー くもならでー
♪たてるははーなの よしのやまー
♪みてこんものをー はるならばー
高野山駅→極楽橋駅
(南海高野線)
極楽橋駅→高野下駅→九度山駅→橋本駅
(和歌山線)
橋本駅→吉野口駅
(近鉄吉野線)
吉野口駅→六田駅→(吉野川橋梁)→吉野駅
※高野山から、吉野山へ行く現代の行程を簡略化して表記
高野山を降りて、再び紀ノ川を渡り、吉野へ
高野山の観光を終わると、山を下りて、今度は紀ノ川(吉野川)上流にある吉野方面へ向かうことになります。
和歌山県では「紀ノ川」、奈良県では「吉野川」
「紀ノ川」は和歌山県における名前になります。
奈良県では、「吉野川」と名前を変えます。
このように、県ごとに川の名前が異なるというケースは、わりと存在しています。

橋本付近での「紀ノ川」(和歌山県)

上流部・奈良県での「吉野川」
紀ノ川(吉野川)は、奈良県の山奥からずっと西へ進み、末は和歌山の海に注ぐ川です。
その他の「県ごとに名前が異なる川」
一応、ほかにも「県ごとに名前が異なる川」の例を挙げておくと、
- 新潟県→信濃川、長野県→千曲川
- 神奈川県→相模川、山梨県→桂川
があります。
詳しくは、以下の各記事でも解説していますので、ご覧ください。


当時は、馬車か徒歩で吉野へ登っていった?
鉄道唱歌の時代は、恐らく紀ノ川(吉野川)沿いに、徒歩などで険しい山道を登り、上流の吉野山まで登って行ったのでしょう。
実際、1912年に吉野線(吉野鉄道)が開業されるまでは、人々は徒歩で山を越えて駅までやってきたそうです。
徳島県にもある「吉野川」
余談ですが、「吉野川」は四国の徳島県にも同名の川があります。
むしろこちらはかなり有名な川ですね。
徳島県を流れる「吉野川」はとても大きく、歴史的に何度も氾濫を起こしてきました。
そのため、「日本三大暴れ川」の一つとされ、「四国三郎」と呼ばれます。
- もう一つは利根川の「坂東太郎」
- そしてもう一つは筑後川の「筑紫次郎」
です。
徳島の「吉野川」については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

利根川については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

筑後川については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

現代では、吉野口駅から近鉄吉野線で、吉野へ
現代では、
- JR和歌山線・吉野口駅(奈良県御所市)
から近鉄吉野線に乗り換えて、吉野方面へと向かうのが、一番よい方法だと思われます。

吉野口駅(奈良県御所市)
吉野口駅から吉野駅までは、片道460円・約33分です。
特急に乗れば約28分で、追加で特急料金520円がかかります。
※全て2023年のダイヤ執筆時点の情報で、古くなっている可能性がございます。ご了承ください。
※2025年も一応確認しましたが、一応料金などは変わっていないようです。ただし、くれぐれもご自身でお調べになることをお勧めします。

和歌山線・近鉄吉野線:吉野口駅(奈良県御所市)
前回の高野山からは、再び橋本駅から戻る形に
前回の高野山の観光の後は、一旦、
- 橋本駅(和歌山県橋本市)
から和歌山線で吉野口駅まで戻る必要があります。
つまり、再び奈良県に戻ってくるということになります。
吉野川に沿って、吉野の山へ登ってゆく
吉野口駅を出て(近鉄吉野線で)吉野方面へ向かうと、吉野川沿いに険しい山岳地帯をどんどん登ってゆきます。
近鉄吉野線をずっと登って行くと、 初代吉野駅でもあった、六田駅(奈良県吉野郡大淀町北六田)に着きます。

近鉄吉野線・六田駅(奈良県吉野郡大淀町北六田)
かつては舟で吉野川を渡っていた、「六田の渡し」
ここで六田駅から紀ノ川には当初、橋がかかっていませんでした。
理由は恐らくですが、昔は橋をかけると何度も流されていたから?だと思われます。
昔の(工事を施されていない自然の)川は、現代と比べとても急で流れも速く、ひとたび洪水が起こると、橋が流されて大変だったのです。
ならばいっそのこと橋をかけずに、「渡し舟」という舟が運航されていました。
この渡し舟のことを、
- 「六田の渡し」
- 「柳の渡し」
といいます。
かつて初代吉野駅だった、六田駅
六田駅は明治時代終わりの1912年に開業しており、元々は「吉野駅」という駅名でした。
つまり六田駅は、「初代吉野駅」ということであり、現代の吉野駅は「二代目」ということになります。
それが1928年に吉野川に橋がかけられ(吉野川橋梁)、1928年に二代目吉野駅まで延伸したとのことでした。
「吉野への旅客」と「吉野杉」を運んでいた、吉野線
吉野線が建設された目的として、やはり1つに吉野へ参拝客・観光客を運ぶ(乗せる)ことが挙げられます。
かつての人々は、徒歩で参拝していた
それまで吉野へは(歴史的には)徒歩または馬で行くことが、ほぼ慣例だったのでした。
しかしながら、険しい山道にもかかわらず、桜の名所の吉野へ観光で行きたいという需要はあったのでした。
そこに鉄道を通せば、多くのお客さんに乗っていただけることがわかっていたからですね。
吉野の山奥地域から、南和鉄道(当時)の駅へは遠すぎた
そして、もう1つの理由として。
南和鉄道(当時:現代の和歌山線)の駅のみだと、吉野の山深い地域に住んでいる人々にとっては、歩いて(和歌山線の)駅に来るにはあまりにも遠かったのでした。
現在の近鉄吉野線は、そういった人々を救済する目的もあったのでした。
明治時代の当時は、自動車はまだ一般的ではありませんでした。
そのため、数キロも先にある最寄駅へ行くのはかなり険しい道で不便だったのでした。
一方、かつて大海人皇子・源義経・後醍醐天皇(後述します)も、そして歴史上多くの吉野山へやってきた人々も、当時は険しく遠い山道をはるばるやってきたので凄いなぁ、と思い知らされます。
「吉野杉」の名所 杉をあちこちに運んでいた貨物列車
さらにもう1つの理由として。
現在の近鉄吉野線が出来たのは、吉野山でたくさん採れる「吉野杉」とよばれる木材を運ぶためのルートとしての目的もあったのでした。
吉野は林業が盛んだったため、建築や家具など、木材を必要とする各地域へと出荷し、利益を上げるという仕組みでした。
吉野線ができた今から約100年前の当時も、貨車(※)に多くの木材を載せ、吉野口駅からそのまま国鉄・和歌山線に乗り入れて、各地に運んでいたのでした。
※貨車:鉄道車両のうち、動力がなく、荷物を載せる台を持ったものであり、機関車に引っ張られて動く車両のことです。
線路の幅を「狭軌」に統一し、国鉄との相互乗入れを可能に
国鉄の線路は約1.067mの「狭軌」であり、吉野線も同じ狭軌にしたことで、国鉄との直通運転が可能となったのでした。
その結果、木材をあちこちに運ぶ・出荷ができるようになったのでした。
ちなみに狭軌とはなにか?については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

吉野川を渡り、山奥深く・吉野に到着
話がかなり逸脱しましたが、「六田駅を過ぎて橋を渡り、吉野川を渡る」ところから話を再開します。

吉野川を渡る(奈良県)

吉野川(奈良県)
吉野川(紀ノ川)を渡ると、やがて山の奥深い吉野に到着します。
実際、吉野に着いたらとても深い山の中に着いたという実感が湧きます。

近鉄吉野線・吉野駅(奈良県吉野郡吉野町)
かつて吉野へ逃れてきた人々
吉野はとても険しく深い山奥にあるため、古くから政治の権力争い(政争)に負けた人達が、何度もここに逃げ込んできました。
なぜここまで皆が逃げてきたのかが、わかるような気もしますね。
吉野に逃げてきた代表的人物としては、
- 室町時代に、北朝や足利尊氏との政争に敗れた、後醍醐天皇
- 源平合戦の後に、兄の源頼朝と対立して政争に敗れた、弟の源義経
- 飛鳥時代に、天智天皇の息子である大友皇子に一時的に天皇の座を奪われた、大海人皇子(後の天武天皇)
などの存在が挙げられます。
後醍醐天皇については、次回以降に解説します。
源義経については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。
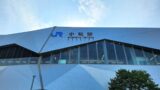
大海人皇子については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

桜の名所・吉野
そして、吉野は桜の名所として知られます。
吉野の山々には無数の桜の木々が生えています。そのため、春になると辺り一面桜の花が満開になり、山々がピンク色で染まります。
そのため、多くの人々が桜を見に訪れる、国内有数の桜の名所となっています。
その他の「桜の名所」
他にも桜の名所として、鉄道唱歌に関係するところでは、
- 茨城県桜川市の、岩瀬
- 東京都小金井市の、小金井公園
などがあります。
岩瀬については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。
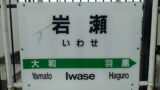
武蔵小金井については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。
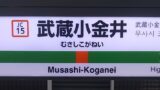
次は、後醍醐天皇と、吉野の吉水神社の話題へ
次は、その後醍醐天皇と、吉野の吉水神社の話題となります!

コメント