中央線鉄道唱歌の歌詞を、わかりやすく解説してゆきます!
都留市・(南北の)都留郡の地理や歴史などを、やさしく解説してゆきます!
↓まずは原文から!
人住む里は打ち拓け
南北都留の兩郡は
甲斐絹織の名産地
さらに読みやすく!
人住む里は 打ち拓け
南北都留の 両郡は
甲斐絹織の 名産地
さあ、歌ってみよう!
♪ひとすむさとはー うちひらけー
♪なんぼくつーるの りょうぐんは
♪かいきぬおりのー めいさんちー
高尾駅→相模湖駅→上野原駅→四方津駅→鳥沢駅→猿橋駅→大月駅→初狩駅→笹子駅→(笹子トンネル)→甲斐大和駅→塩山駅→山梨市駅→石和温泉駅→酒折駅→甲府駅
※鉄道唱歌に関連する主要駅のみ表記
山々を過ぎ、大月方面へ
鳥沢駅(山梨県大月市)を過ぎると、列車は大月市の中心へ向かってゆきます。
また、周りの山々はますます深いものになってゆきます。
歌詞には
人々の済む里(村や町)は、打ち開けてきている
と歌われています。
この辺りは、
- 「大月市」
- 「都留市」
- 「北都留郡」
- 「南都留郡」
などの町がメインとなってきます。
「川」が作る、深い谷と平野部
周囲の山々は深いですが、桂川や丹波川などの”川の水”によって地面が下へ削られる(侵食される)と、そこには”谷”と”平地”ができます。
つまり、
- この川の周辺に出来る、わずかな平地の周りに、
- 町や集落が出来て、
- 人々の生活や経済活動が行われている
というわけです。
明治時代に織物で栄えた、南北の都留郡
歌詞にあるように、明治時代にこの地域は、「織物」の工業で栄えたわけです。
そのため、出来上がった織物を(例えば甲府や東京などへ)出荷して購入してもらうことによって、人々は生計を立ててきたことが想像できます。
都留市、南都留郡・北都留郡
都留郡(つるぐん)とは
都留郡とは、山梨県大月市とその南の都留市の周辺のエリアのことです。
都留郡には、いわゆる「南北」があります。
大月市と都留市を境に、
- 南都留郡
- 北都留郡
というエリアに分かれています。
北都留郡
北都留郡は、大月市から北約5kmほどのエリアであり、小菅村や丹波山村といった2つの村があります。
南都留郡
南都留郡は、大月市の南の都留市よりも南のエリアをいい、富士河口湖町も含む計6つの町村からなります。
富士河口湖町へは、後述するように、大月駅から「富士急行線」に乗って向かうことができます。
また歌詞にある通り、この地域は甲斐絹織の名産地となります。
「甲斐絹織」の名産地
織物とは、昔の和服・着物のことです。
織物は職人の手によって手間を掛けて造るので、必然的に高価かつ高級なものになります。
しかし、明治時代になると産業革命により、大量生産され価格も安くなります。
そうなると、従来の高価な織物は必然的に衰退してゆきます。
しかし100年も経った現代では、その希少性から伝統工芸品という扱いとなります。
そうなると、今度は昨今の少子高齢化もあって、後継者問題や技術の継承などで悩むようになってきます。
そのため、全国的に地元の自治体によって保存の取り組みがなされています。
富士急線・大月線、河口湖
河口湖方面へは、富士急線・大月線で行くことができ、大月駅で乗り換えということになります。
こちらは次回解説します。
都留文科大学
山梨県都留市は、大月市の南にある自治体であり、都留文科大学が所在するため、20代前半の男女の人口の割合が多くなっています。
リニア実験線
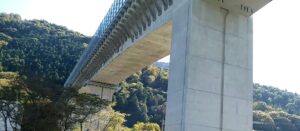
リニア実験線(山梨県都留市)
また、この地域には「リニア実験線」があります。
リニア実験線は山梨県のみならず、宮崎県にもあります。
宮崎県の実験線は現在では使用されていませんが、現在でもその線路跡があり、日豊本線の車窓から眺めることができます。
宮崎県のリニア実験線については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

「リニアモーターカー」とは
「リニアモーターカー」は、磁石の力で車両を浮遊させ、時速500kmでの走行を実現する仕組みです。
時速350kmが限界とされている従来の鉄道とは異なり、浮遊するリニア式では線路と車輪による「摩擦係数が小さい問題」がないため、さらなるスピードアップが期待できるわけです。
「摩擦」の問題が生じない、リニア方式
従来の鉄道では「摩擦係数」が小さく、車輪と線路(レール)が完全には(摩擦により)噛み合わずに、実際には微妙な「空転」や「スリップ」が起きながら進んでいます。これによって列車のスピードロスが起きるのです。
しかしリニアは浮遊させているため、このような「摩擦」の問題は起きずにスピードアップが可能となるというわけです。
2027年に「リニア中央新幹線」が開業できれば、山梨リニア実験線も”実際の線路”として利用される予定となっています。
諸問題により、延期されたリニア開業
しかし現在は様々な「リニア問題」により建設はかなり遅れており、2027年の開業は間に合わないことが確定してしまいました(リニア問題については、ここでは割愛させていただきます)。
「リニア問題」については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

次は、桂川・猿橋の話題へ
次回は、「桂川」「猿橋」の話題となります!

コメント