中央線鉄道唱歌の歌詞(名古屋、名古屋城の観光・歴史など)について、鉄道に詳しくない方にもわかりやすく解説してゆきます!
↓まずは原文から!
名古屋は人口四十萬
商工業の繁昌も
四方にかゞやく金の鯱
さらに読みやすく!
名古屋は人口四十万
商工業の 繁昌も
四方にかがやく 金の鯱
さあ、歌ってみよう!
♪なごやはじんこう しじゅうまん
♪しょうこうぎょうの はんじょうも
♪よーもにかがやく きんのしゃち
中津川駅→恵那駅→釜戸駅→瑞浪駅→土岐市駅→多治見駅→高蔵寺駅→春日井駅→勝川駅→大曽根駅→千種駅→鶴舞駅→金山駅→名古屋駅
※鉄道唱歌に関連する駅と、その他主要と思われる駅を筆者の独断と偏見でピックアップしたもの
今回の旅のゴール・名古屋
前回で、愛知県の県庁所在地である名古屋市の中心駅であり、また今回の旅のゴールである名古屋駅に到着しています。

名古屋駅(愛知県名古屋市中村区)
人口230万人の大都会・名古屋
愛知県名古屋市は、愛知県の県庁所在地であり、人口230万人の大都会です。
名古屋については、鉄道唱歌 東海道編でも歌われています。
詳しくは、以下の記事もご参照ください。

歌詞「三府」とは?
歌詞には、
とあります。
ここでいう「三府」とは、以下の三つの都市をいいます。
- 東京府
- 京都府
- 大阪府
東京は、戦時中の1943年までは「東京府」と呼ばれていました。
1943年に「東京都」に改められたわけです。
ちなみにこのとき東京都に改正された理由は、戦時中のコストダウン・一本化が目的でした。
というのも、「東京府」「東京市」との間で、二重行政という、仕事・税金面でのムダが生じていたからです。
なので「東京市」を廃止して、新たに「東京都」にしたわけですね。
名古屋は、その三つの大都市に続く大都会、と歌われているわけです。
当時は人口40万人
また、歌詞では人口40万人とあります。
しかし、明治時代の当時の日本の人口は、現代の約3分の1の約4,000万人でしたので、当初から人口は多かったことがわかります。
というか、鉄道唱歌の当時(明治時代)、日本のほとんどの街は、多くても人口10万人以下でしたから、当時で人口40万人がいかに多かったかがわかります。
また、今は「市」の自治体も、その多くは昔は「町」や「村」だったのでした。
人口が増えるにつれて「町」や「市」に変わっていったわけです。

名古屋・JRセントラルタワーズ(愛知県名古屋市)
熱田神宮の門前町・名古屋
名古屋は元々、熱田神宮の門前町として栄えました。
熱田神宮には、皇室にとっても大事なアイテムである「三種の神器」の1つである、草薙の剣が祀られています。
そのため、熱田神宮はとても尊い神社だということになります。
その熱田神宮を参拝するため、江戸時代までは東海道をはるばると(徒歩または馬で)旅してきたのでした。
すると、その旅人たちをもてなすための飲食店や茶店、宿場町などがたくさん、名古屋の町にできてくるようになります。
熱田神宮については、以下の記事でも解説していますので、ご参照ください。
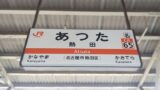
熱田神宮の宿場町・宮宿
名古屋には、かつて東海道最大の宿場町として栄えた宮宿があり、なんと230もの旅籠がありました。
旅籠とは、一般の旅人が泊まるための宿であり、現代の価値だと約3,000円~5,000円程度で泊まれたといいます。
旅籠は、他の宿場町では100件もあればかなり多い方でしたから、宮宿の230という数がいかに大きい規模だっかがわかります。
名古屋城の城下町・名古屋
そして名古屋は江戸時代には、名古屋城の城下町としても栄えました。
城下町では、城に勤務する武士(今でいう公務員)と、彼らをもてなすための商業施設で賑わうため、街の規模が大きくなっていくというわけです。

名古屋城(愛知県名古屋市)
尾張徳川家の支配下にあった、名古屋
名古屋には、江戸の徳川家のバックアップとしての家系(徳川御三家)の一つである「尾張徳川家」がありました。
そのため、名古屋という土地が、徳川家にとっていかに重要だったかがわかります。
その他の徳川御三家(ごさんけ)には、
- 和歌山県の「紀州徳川家」
- 茨城県の「水戸徳川家」
の二つがあります。
紀州徳川家については、以下の記事もご参照ください。

水戸徳川家については、以下の記事もご参照ください。

四方に輝く、金の鯱(しゃちほこ)
名古屋城は、金のシャチホコ(鯱)が印象的です。
シャチホコとは、城の頭に二つ輝く、荘厳な飾り付けのことをいいます。
名古屋の名物を堪能しよう
名古屋といえば、やはり「きしめん」「手羽先」です。そして名古屋で遊ぶ場所といえば、やはり栄です。
栄へは、名古屋駅から地下鉄東山線でわずか「2駅」で行けるため便利です。
- 「サンシャイン栄」の観覧車
- 久屋大通の名古屋テレビ塔
- オアシス21の壮観な景色
- SKE48劇場
- サカエチカ
などなど、たくさんの見所があります。

名古屋テレビ塔(現・中部電力MIRAI TOWER)(愛知県名古屋市)
未来のリニア駅・名古屋へ
名古屋は、リニアの未来の駅にもなります。
鉄道唱歌の歌詞も、いよいよクライマックスです!!

コメント