東京・羽村市の玉川上水の観光・歴史と、玉川兄弟の偉業などについて、初心者の方にもわかりやすく解説してゆきます!
- 今回は、羽村市・玉川上水の観光・歴史
- 江戸時代から人々の飲み水を提供してきた、玉川上水
- 四谷大木戸の水番所から、江戸の各地へ水を供給していた
- まずは羽村駅からスタート!多摩地域の街・羽村市へ 多摩川の羽村取水堰へGO!
- 玉川上水の礎を作った、玉川兄弟
- 日野での工事の失敗 平坦な関東平野では、水がうまく流れなかった!
- 福生からの工事に挑むも、またもや失敗
- 三度目の正直で、羽村からの掘削に成功 江戸の町に水が行き渡るように
- 玉川兄弟の功績と、その後
- 玉川上水はその水質を保つため、厳重に守られた
- 玉川上水の桜 桜の花びらが、水を綺麗にすると信じられていた!
- 多摩川は、末は東京湾に注ぐ川
- 社会見学や歴史探訪は、大人になってからでも楽しい!
- おまけ:筆者の自撮り写真
今回は、羽村市・玉川上水の観光・歴史
さて今回は、以前東京都羽村市の玉川上水取水口、通称・羽村取水堰に行ったときの話をしてゆきたいと思います!
それと同時に、江戸時代にある兄弟が、人々の水を供給するための苦難の工事の歴史を、わかりやすく解説します!

玉川上水・羽村取水堰(東京都羽村市)
江戸時代から人々の飲み水を提供してきた、玉川上水
玉川上水とは?
玉川上水は、江戸・東京の街に飲み水をはじめとする生活用水を提供するための、人工的な川のことをいいます。
上水とは、簡単にはいえば飲み水や洗濯・生活に必要な水のことをいいます。
対義語は、下水になります。
江戸時代にはたくさん人口が増え、江戸の町中では徐々に水不足に陥ってきました。
その水不足を解消し、江戸の人々に対して水を行き届けるようにするため、玉川上水の工事の必要性にせまられました。
玉川上水が通るルート
玉川上水は、今回紹介する羽村市において多摩川から水を取ってきて、東へ東へと進みます。
途中、
- 立川市
- 小平市
- 小金井市
- 三鷹市
- 武蔵野市
- 杉並区
などを経由し、新宿区の四ッ谷に至ります。
玉川上水は、全長約42kmにも及ぶ、長大な人工の川です。
現代でも、東京都水道局によって管理されています。
作家・太宰治の最期ともなった玉川上水
また、作家・太宰治が1948年6月13日に愛人とともに「入水自殺」を遂げたのも、太宰治の最後の自宅があった東京都三鷹市における、三鷹駅付近を流れる玉川上水でした。
太宰治は「自殺マニア」としても知られ、精神的にとて弱く、それまでにも4回もの自殺未遂を繰り返しています。
四谷大木戸の水番所から、江戸の各地へ水を供給していた
玉川上水は四ッ谷の四谷大木戸に至ると、水番所という場所で水質が綺麗に整えられたのでした。
そこからさらに水量を調節した上で、江戸の各家屋に対して流れ供給されていきました。
つまり一旦、水番所に集められ、そこから分散して各家屋に対して水が供給されるイメージです。
ちなみに、四谷大木戸とは、四ッ谷にあった江戸城に入ってくる不審者を取り締まるための場所です。
四谷大木戸の水番所は、上記のように江戸の生活水を扱う重要な役職でした(現代の水道局も同じ)。
羽村取水堰とは
羽村取水堰は、多摩川から玉川上水へと水を取ってくる場所です。
多摩川とは

多摩川。羽村取水堰付近。(東京都羽村市)
多摩川とは、東京都の西側を流れる大きな川です。末は、神奈川県川崎市と、羽田空港の近くの海(東京湾)に注ぎます。
江戸時代のはじめ、幕府からお金の支援を受けながら玉川上水の工事を行ったのが、今回紹介する、後述の玉川兄弟でした。
そして、玉川上水へと(江戸の人々の生活に必要な)水を多摩川から取ってくるための取水口が、ここ東京都羽村市にあるわけです。
まずは羽村駅からスタート!多摩地域の街・羽村市へ 多摩川の羽村取水堰へGO!
東京都羽村市
舞台はまず、
- 羽村駅(東京都羽村市)
から始まります。
東京都羽村市は、東京都の西部にあたる多摩地域の街となります。
東京都23区・多摩地域・島嶼部の違い
人口1,400万人を誇る東京都は大きく分けて、以下の三つの地域に分類されます。
- 東京都都区部(23区)
- 多摩地域
- 島嶼部
東京都都区部(23区)とは?
東京都都区部(23区)とは、東京都東部を占める、いわずと知れた日本の中心地です。
例えば、
- 皇居や国会議事堂などをはじめとする、国の中心機関がある千代田区
- 高年収層・裕福層の多い港区
- 東京都庁のある新宿区
- 若者とITの街である渋谷区
なども、みんな東京都23区に属します。
なので「東京都東京市千代田区」とは言いません。
あくまで「東京都千代田区」になります。
ちなみに「東京市」は、戦時中の1943年まで実際に存在した市になります。
「多摩地域」とは?
多摩地域は、東京都の西部にあたる地域になります。
このあたりは「市」が多くなり、主に
- 立川市
- 八王子市
- 福生市
- 青梅市
などの主要都市があります。
東京都だけあっていずれも立派な街なのですが、西にいけば行く程、自然にあふれるのどかな雰囲気になります。
新しい街並みが開発され家族でも住みやすくなっているため、多摩地域は東京都心へのベッドタウンとしても人気があります。
なかでも奥多摩町はとにかく自然に溢れ、ここが東京都なの?と言わんばかりです。
今回紹介する羽村市も、多摩地域に属します。
島嶼部とは?
島嶼部とは、いわゆる小笠原諸島などに代表される、離島部分になります。
沖縄県のはるか南にある「沖ノ鳥島」も、信じられないことに東京都に含まれます(しかし島といっても本当にわずかに突き出た岩のため、いわゆる「領土問題」あり)。
また、日本のはるか東の太平洋に浮かぶ「南鳥島」もなんと東京都であり、ここが日本最東端の地になります。
しかし南鳥島は、国の職員のみ上陸が許可されており民間人の立入りは禁止となっています。
そのため、民間人が立ち入れる場所での日本最東端の地は、北海道根室市の納沙布岬になります。
納沙布岬の向こうには、いわゆる「北方領土」があります。
玉川上水の礎を作った、玉川兄弟
話がだいぶズレてすみません。
羽村駅は、立川駅(東京都立川市)から青梅線に乗り換え、
- 拝島
- 青梅
方面へ向かうと、約20分ほどで着きます。

玉川兄弟の像。羽村取水堰より。(東京都羽村市)
ここには、玉川兄弟という、江戸時代に玉川上水を造った兄弟の銅像があります。
玉川兄弟は元々は「玉川」という苗字すらない農家でした。
しかし、彼らは6,000両(一両=約10万円のため、現在価値で約6億円)といわれる幕府からの支援金・工費を投入して、川越藩の監督のもと、玉川上水取水堰を作っていったわけです。

玉川兄弟の像と撮影!(東京都羽村市)

多摩川をバックにパシャリ!(東京都羽村市)
日野での工事の失敗 平坦な関東平野では、水がうまく流れなかった!
玉川兄弟による玉川取水口の工事は、少なくとも2度失敗したそうです。
日野での工事の失敗
最初は、日野の掘削に挑みます。
東京都日野市は、新撰組鬼の副長だった土方歳三の出身地です。
しかし日野市での掘削は挫折してしまいます。
なぜかというと、肝心の飲み水となるべき水が、地面にどんどん吸い込まれる現象が起こることが判明したからです。
これでは使い物になりません。
この「水を吸い込む地面」のことを、水喰土といいます。
「水喰土」によって、せっかくの水が吸われてしまった
この水喰土は、関東ローム層の、水を吸い込みやすい、独特の地層だったことが関係しているといいます。
水喰土の存在によって、せっかく流されてきた水が全部吸われてしまい、使い物になりませんでした。
高低差が無いため、水が流れなかった
しかも関東平野は基本的に平坦であり高低差があまりないため、せっかく掘っていざ水を流しても、平坦な流路では全然水が流れてくれません。
自然の川の水は、高低差があるからこそ、(高い方から低い方へ)流れていくのですね。
これによって、新たに測量・調査を行い直すことになり、次は後述する福生の地から工事することになりました。
工事の失敗と「かなしい坂」
こうして、日野での最初の上水の掘削・開発は失敗したのでした。
そして、その失敗の責任を問われた役人たちは、こともあろうに(東京都府中市の地において)処刑されてしまいました。
その処刑の現場で役人たちが「かなしい」と嘆いていたため、府中市の現場には「かなしい坂」という坂道が存在しています。
福生からの工事に挑むも、またもや失敗
日野が失敗したため、今度は羽村市のやや南東にある福生の地域で掘り進める作業を行うことにしました。
すなわち、現在の東京都福生市にあたり、横田米軍基地のあるところですね。
岩盤が固すぎて掘れず、またもや失敗
しかし、福生からの掘削では岩盤(=とても硬い岩の層)にぶつかってしまい、硬すぎて掘れなくなってしまいました。
「兄さん!ここは硬すぎて掘れないよ!」
「うむ・・・やむを得まい。福生を掘るのも諦めるか。これで二度の失敗か・・・幕府になんと説明すればいいのか・・・」
このように、ここは上水(川)を作るのには相応しい土地ではないという結論に至り、頓挫してしまっています。
福生の「みずくらいど公園」
また、福生においても先述の水喰土に水をみんな吸われてしまったため、現在の福生市には「みずくらいど公園」という公園・観光地があります。
そこに、玉川兄弟が掘り進めて失敗した水喰土の遺構が史跡として残っています。
横田米軍基地が存在する、福生市
ちなみに東京都福生市は、横田米軍基地が存在するてま、たくさんのアメリカ人の方がおられます。
私もよく、ランニング中の米軍・アメリカ人の方に、気さくに挨拶されます。
また、横田米軍基地の上空はアメリカ軍の領空のようになっており、基本的には民間の飛行機は飛ぶことができません。
そのため、羽田空港を離陸した飛行機は、より南の相模湾の上を飛んでゆくことが多いといえます。
三度目の正直で、羽村からの掘削に成功 江戸の町に水が行き渡るように
話を元に戻しますが、玉川兄弟はこれで二度にわたる失敗となりました。
三度目の正直で、今度は羽村からの掘削工事を開始しました。
しかし、現在の新宿のやや西にある高井戸という地域にさしかかったところで、お金が尽きてしまいました。
幕府から渡された約6,000両(約6億円)もの資金が底をつき、やむを得ず自身の畑や家を売ったりして、工事を続投したのでした。
玉川兄弟は、元々は苗字すらない農家だったため、農家の命ともいえる畑を売るのはなかなか断腸の思いだったと思います。
自身の財産を犠牲にしてでも玉川上水を完成させたのですから、銅像が建てられたりするのですね。
そうして江戸初期の1653年、不屈の精神で完成させたのが、今回の羽村市の玉川上水取水堰というわけです。
そして翌年の1654年に、実際に先述の四谷大木戸の水番所から、江戸の町に水が供給されていったのです。
玉川兄弟の功績と、その後

玉川兄弟の像(東京都羽村市)
こうした玉川兄弟の不屈の力と、諦めない力はすごいですね。
その功績をたたえ、玉川兄弟の像が建てられているわけです。
「玉川」の苗字を与えられる
玉川兄弟は元々農民の出身なので、苗字はありませんでした。
しかし、玉川上水を造った功績をたたえられ、幕府から「玉川」の苗字を名乗ることが認められたのでした。
以後は世襲制に その後・・・
しかも、その後の玉川上水の管理業務を、世襲することまで認められました。
世襲とは、親から子へとその職を引き継ぐ仕組みのことです。これにより、子孫の職業がずっと安泰になります。
しかしこれだと、たとえ親がどれだけ偉大だったとしても、子供にやる気なかったり、水道の管理業務に全然興味無くて、「画家になりたい!」などと言い出す可能性まであります。
そうなると、世襲制ではむしろ仕事がうまくいかなくなり、業務が崩壊していまうリスクもあります。
むしろやる気のない子供に任せるよりも、スキルの高い外部の人間を採用した方が、うまく業務が回る可能性もあります。
ましてや玉川上水は江戸の人々の生活水となる重要インフラですから、しっかりと仕事をしてもらわなければ困るわけです。
この玉川家による水道管理業務の世襲制はうまくいかなかったのか、約80年後の1739年にはその世襲制の権限を剥奪されてしまいました。
理由はよくわかりませんが、上記のような「世襲あるある」のために水道管理業務が崩壊してしまったからなのかもしれません(調べたら、実際に三代目のときに不祥事を起こしたことが原因のようでした)。
玉川上水はその水質を保つため、厳重に守られた
玉川上水は、東京・羽村から新宿区・四ッ谷にまで至る、約42kmに及ぶ人口の川であるわけです。
そんな立派な川にあって、江戸時代はここに汚物を流す・体を洗う・魚釣りをやる・ゴミを捨てるなどの行為は御法度として、厳重に取り締まられました。
人々(武士も含まれる)の生活にかかわる水なので、川を汚そうものなら「切り捨て御免」などとして命が助からなかったかもしれません。
また、玉川上水のあちこちには、「~をしてはならない」と書かれた高札場がありました。
玉川上水の桜 桜の花びらが、水を綺麗にすると信じられていた!
玉川上水の回り(土手や堤)には、たくさんの桜が植えられました。
これは昔、桜の花びらが水を綺麗にしてくれると人々に信じられていたからです。
また、桜を植えることによって観光名所になることや、お花見の客が土手(堤)の地面をたくさん踏んでくれることで、地面を固めて丈夫にしてくれることを期待したものです。
特に、東京都小金井市を流れる玉川上水の桜は、明治時代~大正時代にかけて関東の桜の名所となりました。
桜のお花見のために小金井で仮の駅が設置され、それが現在の武蔵小金井駅となりました。
また、その植えられた桜は奈良県の吉野や、茨城県桜川市から取り寄せたものであり、当時としては非常に珍しい桜であったことから、なお人々がお花見のためにやってきた、とのことです。
小金井については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。
中央線鉄道唱歌 第6番 武蔵小金井に到着 関東の桜の名所、小金井公園へ
多摩川は、末は東京湾に注ぐ川
多摩川は、末は神奈川県川崎市の東端と羽田空港のすぐ西横を通り、東京湾に注ぐ川になります 。
このあたりは東海道線も通る(川崎駅がすぐ間近)、下流部分になります。
多摩川(下流部分)には、六郷の渡しろくごうのわたしというものがありました。
いわゆる「渡し舟」と呼ばれるものです。
なぜ渡し舟があったのかというと、昔は軍事的な理由で橋をかけることができなかったからです。
また江戸時代当時の橋は、ひとたび川が氾濫するとすぐに橋が流されてしまっていました。
そのため、「だったら最初から橋なんかかけなくていい」ということで、代わりに「渡し舟」で川を渡っていたのでした。
社会見学や歴史探訪は、大人になってからでも楽しい!
羽村取水堰の見学を終えると、羽村駅まで戻ります。
帰りは福生駅・立川駅あたりで休憩して、帰宅しました!
とても勉強になった日でした。

社会見学とは、大人になってからも楽しいものですね!
おまけ:筆者の自撮り写真
最後に、その他撮った私(筆者)の写真を載せておきます!




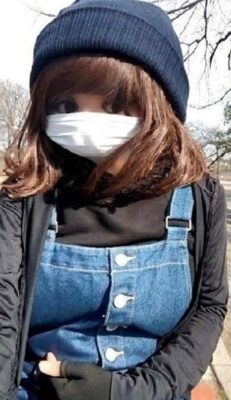

今回はとても多摩川の水の流れに癒され、飼い主に連れているワンちゃん(犬)にも癒されました!(^^;,

コメント