宇都宮線の旅行(東京→宇都宮まで)について、鉄道に詳しくない方にも、わかりやすく解説してゆきます!
今回から、私(筆者)が冬に東京から北海道へ行ったときの旅シリーズ!
今回からは、東北本線(および新幹線)を使って東京から北海道に向かって行く、という旅について書いてゆきます。
筆者が今冬実際に、北海道に行ったときのレポートになります。

冬の函館にて!(北海道函館市)
なにせ冬の時期の旅行であり、本当はもっと早く書きたかったのですが、さまざまな事情があって準備や執筆がかなり遅れてしまい、発表が今の時期(しかも夏)となってしまいました。
今の季節(執筆時点で7月)は思いっきり夏だと思いますが、登場する写真はみな冬の雪景色だったりすることを、どうかご了承ください(^^;)
東北本線(宇都宮線)で、東京をスタート!
まずは東北本線で、東京を出発ということになります。

東北本線(宇都宮線)で、出発!
東北本線(宇都宮線)で、宇都宮にまで出発
東京から宇都宮までは、東北本線(上野東京ライン、または宇都宮線とも)で向かいます。
しかし朝出発したばかりでまだテンション上がっておらず、しかもたくさんの通勤客に囲まれてしまうストレスを軽減するために、宇都宮駅まではグリーン車で行くことにしました。
グリーン車であれば追加料金がかかる分、座席の広さには余裕がありますから、居眠り・勉強・作業など車内の過ごし方に自由度が高くなります!

東北本線(宇都宮線)でいざ出発!
「上野東京ライン」は、必ずしも宇都宮線ではない!?高崎線も含まれる場合もある
なお、
- 上野東京ライン(東京駅~宇都宮駅の区間)
- 宇都宮線(東京駅~黒磯駅の区間)
- 京浜東北線(東京駅~大宮駅の区間)
- 山手線(東京駅~田端駅の区間)
は、実はこれらは全て「東北本線」の一部にあたります。
つまり東京駅~盛岡駅までは、本当はすべて東北本線の区間なのです。
「宇都宮線」は、あくまで愛称
「上野東京ライン」「宇都宮線」「京浜東北線」の名前はあくまで愛称になります。
山手線の場合は?
「山手線」は、厳密には品川駅~田端駅を「C」の字に結ぶ路線です。
これだと乗客・一般客にはわかりにくいため、便宜上「環状」の線路として扱われている、というわけです。
高崎線に乗り入れる列車に注意
「上野東京ライン」は、宇都宮線だけでなく、高崎線に乗り入れる列車も含まれるため注意です。
なので宇都宮方面へ行きたいのに、「上野東京ライン」が漠然と「=宇都宮に行く」みたいなイメージを持っていると、大宮から先、高崎方面へ行ってしまい後で気付くことになるため、気をつけたいところです。
宇都宮線が含まれる「東北本線」は、かつては日本最長の路線だった
東北本線は、日本で3番目に長い路線ともいわれます。
- 山陰本線 約673km
- 東海道本線 約589km
- 東北本線 約535km
現在の日本最長の路線は、山陰本線です。
京都駅を出発して、福知山・鳥取・島根・山口を経由し、はるか西の下関に至るのですから、めっちゃ長い路線ですね。
東北本線は、その昔は東京駅から青森駅までありました。
その距離は実に739.2kmにも及び、上述の山陰本線の長さ(約673km)をも凌いでいました。
東北新幹線の開業に伴い、距離が短くなった
しかし2010年に東北新幹線の新青森駅への延伸に伴い、
- 盛岡駅~青森駅
までの在来線区間は、第三セクター
- 「IGRいわて銀河鉄道」
- 「青い森鉄道」
による経営に移管されたため、現在の東北本線は東京駅~盛岡駅までの区間(約535kmの長さ)であり、全国3位の長さとなっています。
ではなぜ東北新幹線が延伸され、盛岡駅~青森駅の区間がJRではなく第三セクターに移管されたのか?については、以下の記事でわかりやすく解説していますので、ご覧ください。
-160x90.jpg)
宇都宮線の旅(東京→宇都宮)
大宮を過ぎると、朝日まぶしい北関東の、のどかな田園地帯を走る
東京を出て大宮駅(埼玉県さいたま市)を過ぎると、
- 東大宮
- 蓮田
- 久喜
- 栗橋
と過ぎてゆきます。

東北本線(宇都宮線)で、どんどん進もう!
この辺りまで来ると、それまでの大都会の様相は落ち着いてゆき、だんだんと北関東の素晴らしい田園地帯の景色になってゆきます。
なおこの時はまだ朝早く東京を出発したばかりだったので、朝日がすごく綺麗でございました。
栗橋駅を過ぎて、利根川を渡る
栗橋駅(埼玉県久喜市)を過ぎるとほどなくして、利根川を渡ってゆきます。
利根川は、群馬県・みなかみ町の山奥から流れ出てきます。
やがて、末は東の太平洋・銚子の海に注ぐ川です。

利根川(東北本線・埼玉県と茨城県の県境より)

利根川の河口・千葉県銚子市(からの利根川の景色)
利根川についての詳細は、以下の記事でもわかりやすく解説していますので、ご覧ください。


茨城県最初の鉄道駅が来た街・古河市
利根川を渡ると茨城県に入り、やがて古河駅(茨城県古河市)に着きます。
ただし古河駅を出るとすぐに栃木県に入るため、茨城県を走るのはほんの一瞬となります。
古河市は茨城県の本当に西に突き出た領域に存在するためですね。
茨城県古河市は明治時代、茨城県で初めて鉄道が通った場所でもありました。
※先述の古河駅こそが、まさに茨城県最初の駅でした。
当時はまだ橋がかかっていなかった利根川
古河駅は明治時代の1885年に開業しましたが、当時はまだ利根川には橋がかかっていませんでした。
そのため、この時はまだ舟で利根川を渡るしかありませんでした。
翌年の1886年に利根川に橋がかかるまでは、「房川の渡し」といって、対岸の中田宿の場所まで舟で渡っていたのでした。
代わりに舟で渡るための仕組み「渡し舟」
「渡し舟」とは、橋がかけられなかった昔に、代わりに舟で渡るための仕組みです。
中田とは、古河駅の南にある、利根川のすぐ北の地名です。
房川の由来は、現在ではあまりわかっていないそうです。
1886年には利根川橋梁が完成し、大宮駅~宇都宮駅の直通列車が走るようになったのでした。
新幹線が通る古河市 茨城県唯一の新幹線駅は実現しない?
茨城県古河市は、茨城県では唯一、新幹線の線路が通る場所となっています。
しかし残念ながら線路が通るのみで、茨城県に新幹線の駅は存在していません。
もちろん古河市には新幹線駅を建設する案があり、実際に茨城県や古河市も自治体としてJR東日本に対して(駅建設の)要望書を提出しているようです。
しかし今のところ(茨城県・新幹線駅の)実現には至っていません。
理由は色々あると思いますが、やはり大宮駅~小山駅の間に駅ができるとなると、さすがに駅間距離が短くなります。
すると、
- 新幹線が充分に加速できなくなる
- 東京~福島~仙台までの所要時間も、長くなる
のが主な理由でしょう。
室町時代・戦国時代に、「古河公方」の拠点となった古河市
ここからは、ガチガチの歴史の話になります。
興味がない方は、こちらからページの下部へお進みください。
古河市には、かつて古河公方という、室町幕府・足利家のお偉いさんがいました。
古河公方は、鎌倉府とよばれる、神奈川県鎌倉市に存在した武士の拠点のトップ・長(鎌倉公方)から、なんと分裂してしまって出来た組織のトップ・長です。
なぜ分裂したのかは、後述する内部分裂や内輪揉めなどによるものです。
室町関東の様々なキーワード これを押さえれば室町時代の関東地方がわかる
とはいえ、上の説明だけだととてもややこしいので、以下にまとめます。
室町幕府:京都にあった武士の政府。将軍(いちばんエラい人。
現代の内閣総理大臣に該当)は、足利家。
鎌倉:鎌倉時代に、鎌倉幕府があった地域。現在の神奈川県鎌倉市にあたる。
横浜市の南西に位置する。
鎌倉府:室町幕府が、その鎌倉を監視するために置いた機関。
トップ(長)は、鎌倉公方とよばれる。
鎌倉公方:鎌倉府のトップ(長)。
室町幕府から任命された足利氏の一族が世襲した。
しかし後に、京都にいる室町幕府の足利氏と対立してしまう。
関東管領:上記の鎌倉公方を補佐(手伝い)するための役職。上杉氏が世襲した。
後に上杉氏と鎌倉公方・足利氏は対立してしまい、享徳の乱というとんでもない反乱を起こす。
永享の乱:1439年に、室町幕府・足利氏と、鎌倉公方・足利氏の対立(身内争い)によって起こった争い。
結果は、鎌倉公方・足利氏が敗北し、敵・室町幕府の味方である関東管領・上杉氏に対して復讐していくようになる。
結城合戦:上記で戦死した鎌倉公方・足利氏の息子たちが、(室町幕府の味方である)関東管領・上杉氏に対して怒りを持ち、茨城県結城市の結城城に立てこもり、関東管領・上杉氏に兵を派遣されて征伐された争い。
享徳の乱:上記の結城合戦で関東管領・上杉氏にやられた鎌倉公方・足利氏がとうとう怒りMAXになり、鎌倉公方・足利氏と関東管領・上杉氏の対立が極限状態に。
ついに前者が関東管領・上杉氏を謀殺・暗殺したことに始まり、それがきっかけで関東地方全体を巻き込む戦乱に発展した、室町時代を代表する関東地方の大乱。
関東地方における戦国時代の幕開けとなった、歴史的にも重要なターニングポイントとなる一連の戦い。
古河公方:享徳の乱がきっかけで、鎌倉公方から分裂して茨城県古河市の位置に出来た、鎌倉公方・足利氏が就く組織の長。
鎌倉公方と関東管領の対立がすごかった、室町時代中期
上記うまくまとめたつもりですが、それでもややこしくてわかりにくいですよね。
日本史に詳しい人でも、なかなか室町時代の関東地方についてわかりやすく説明できる人は、そんなには多くないのではないでしょうか(^^;)
私(筆者)も、勉強するのにかなり苦労しました。
多くの鎌倉幕府・北条氏などの残党もたくさん残っていた鎌倉
「鎌倉」は言うまでもなく、室町時代のひとつ前の鎌倉時代に、「鎌倉幕府」という巨大な武家勢力があった場所です。
そうなるともちろん、鎌倉幕府や北条氏に対して忠実だった武士の残党もたくさん残っていることでしょう。
その残党武士たちが室町幕府に対して抵抗しないように、監視の目的で鎌倉府を置いていたのですね。
その鎌倉府のトップを鎌倉公方といい、その職の座は室町幕府から指名された足利氏の世襲となりました。
鎌倉公方の下に存在した、関東管領
その鎌倉公方の下には、関東管領という組織があって、鎌倉公方を補佐する役割がありました。
関東管領は、上杉氏の世襲でした。
上杉氏とは、のちに
- 新潟県・越後国の上杉謙信
- 山形県・米沢の上杉鷹山
などで、有名になる一族です。
室町時代は、三代目・足利義満というスーパースターが政治をしていた頃には、そのカリスマ性を発揮してうまくまとまっていました。
室町時代中頃になると、政権争いが多発
しかし室町時代中頃になると、そういったカリスマ性ある人がいなくなって、みんな「俺が一番だ!」といわんばかりに政権争いが多発するようになります。
やがて、上記の
- 室町幕府・足利氏
- 鎌倉公方・足利氏
が対立するようになりました。
それはやはり、お互いが遠隔地(京都府と神奈川県)にあって、なかなか思うように意志疎通が取れていなく、不満が溜まりやすい環境となっていたのも原因の一つです。
お互い遠くに離れていると信頼関係の維持も難くなり、幕府の意向がなかなか鎌倉まで伝わるのも難しかったでしょう。
江戸時代には、室町時代のような問題は起きなかった
ちなみに江戸時代には参勤交代という制度によって、遠隔地の大名は定期的に(幕府のある)江戸へやってきていました。
その際に、将軍と大名が意志疎通と信頼関係・主従関係を再確認していたのでした。
そのため、室町時代に起こっていた上記のような問題は解消されていました。
鎌倉府の中でも、権力争いで対立
話を戻しますが、鎌倉府の中でも、権力争いで対立してしました。
いわゆる、内輪揉めというやつです。
それは鎌倉公方・足利氏と、それを補佐するはずの関東管領・上杉氏が対立するというものでした。
戦国時代をはじめとする戦乱の世の中では、基本的に「敵の敵は味方」になります。
したがって、
- 室町幕府・足利氏
- 関東管領・上杉氏
は、(ともに鎌倉公方が敵なので)味方同士になります。
鎌倉公方・足利氏が敗北した「永享の乱」
まずは1439年に、鎌倉公方と関東管領が対立し、鎌倉公方・足利氏が敗北しました。
この争いを、
- 永享の乱
といいます。
これに対して、鎌倉公方・足利氏が室町幕府・足利氏と関東管領・上杉氏に対して怒りの感情を持つのは当然のことです。
足利持氏の子、結城城に立てこもる
その鎌倉公方・足利持氏の子である
- 足利春王丸
- 足利安王丸
が、茨城県結城市にあたる結城城に立てこもったのでした。
そして、これを関東管領・上杉氏が征伐に向かうという、結城合戦が起こりました。
関東管領・上杉氏と鎌倉公方との間で、無限ループの争いに
すなわち、これによって、
- 関東管領・上杉氏が、鎌倉公方の残党を討伐し、
- さらに鎌倉公方勢が関東管領・上杉氏に対して、復讐を企てる
・・・みたいな無限ループの応酬が繰り広げられるわけです。
こうして鎌倉公方と関東管領の対立は決定的なものになり、やっては仕返し、やっては仕返しの連続になります。
享徳の乱 ついに関東地方の戦国時代の幕開けへ
そして決定打となったのが、鎌倉公方・足利氏が関東管領・上杉氏を謀殺・暗殺したことを発端に、関東地方全体に広がった戦乱が、1455年に勃発した
- 享徳の乱
です。
この享徳の乱がきっかけで、関東地方の戦国時代の幕開けとなってしまいました。
鎌倉公方が内部分裂して出来た古河公方・堀越公方
こうして鎌倉府の鎌倉公方が内部分裂して出来たのが、
- 古河公方
- 伊豆の国の堀越公方
などでした。
室町時代の終わりには、「応仁の乱」の京都だけでなく、関東地方も戦乱が激しかったのです。
応仁の乱については、以下の記事でもわかりやすく解説しているので、ご覧ください。

今も残る、古河公方公園
茨城県古河市の古河駅の南・古河市役所のさらに南の地には、現在でも古河公方の本拠地の跡として、古河公方公園があります。
足尾銅山事件をきっかけに造られた、渡良瀬遊水地
古河駅の近くには、渡良瀬遊水地という、明治時代の足尾銅山事件の時に渡良瀬川で流れてきた有害物質を含む水を、洪水などで溢れさせないためにできた、人工的な湖があります。
渡良瀬遊水地と足尾銅山事件については以下の記事でわかりやすく解説していますので、ご覧ください。

両毛線と水戸線の分岐駅・小山駅(栃木県小山市)
小山駅(栃木県小山市)からは、両毛線で西の栃木市方面へと別れてゆきます。
栃木県栃木市は、水郷の景色が広がり、巴波川の景色が特に美しいです。
私(筆者)が栃木市に行ったときのレポートについては、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

小山駅から東へ分かれる「水戸線」
また、小山駅からは水戸線にて、東の
- 友部
- 水戸
方面へと別れてゆきます。
水戸線は小山駅~友部駅までを結ぶ線路であり、水戸駅まで行かないのに「水戸駅」という名称になっています。
水戸駅まで行かないのになぜ「水戸線」と呼ぶのか?については、以下の記事にて解説してますので、ご覧ください。
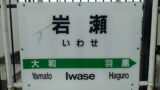
下野(しもつけ)エリアを過ぎ、やがて宇都宮駅へ
小山駅を出てさらに北上していくと、やがて
- 小金井駅(栃木県下野市小金井)
- 石橋駅(栃木県下野市石橋)
を過ぎます。
下野市は「しもつけし」と読みます。
それは栃木県が昔、下野国と呼ばれていたことに由来します。
下野市のエリアについては、以下の記事でもわかりやすく解説しているので、ご覧ください。
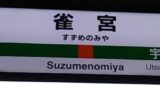
やがて
- 雀ノ宮駅(栃木県宇都宮市)
を過ぎて、やがて栃木県の県庁所在地である宇都宮市の中心駅・宇都宮駅(栃木県宇都宮市)に到着です。
朝早くから列車に乗っているため、宇都宮駅に着いたらここでひと休みです。
宇都宮駅は、日光や大谷石記念館などへの観光拠点
宇都宮駅からは、
- 日光線に乗り換えて、日光方面へ
- またバス等に乗り換えて、大谷石記念館へ
行くことが出来ます。
宇都宮の名物の石材「大谷石」
大谷石は宇都宮の名物といえる石材であり、古くから壁の石など様々な用途で使われてきた、宇都宮ならではの石です。
大谷石は昔の東京の重要な建物や、駅のプラットフォームの石材などにも使われてきた、貴重な石材になります。
宇都宮は餃子が名物なわけですが、宇都宮駅前の名物である餃子像も、なんと大谷石でできているのです!
筆者が日光や大谷石記念館に行ったときのレポートは、以下の各記事でも解説していますので、ご覧ください。


次回は、那須塩原・黒磯・新白河方面へ
次は、宇都宮駅を出て、
- 那須塩原
- 黒磯
- 新白河
方面へと向かってゆきます!
最後まで読んでくださってありがとうございます!
当サイトはリンクフリーであり沢山の人に読んでもらいたいので、ご自身のSNSやYouTube、ブログなどでどんどん紹介してくださいね。

コメント