伊豆・源頼朝ゆかりの地である蛭ヶ小島について、わかりやすく解説してゆきます!
初心者の方にも、やさしく解説してゆきます!
源頼朝公配流の地・蛭ヶ小島へ到着!

蛭ヶ小島からの富士山(静岡県伊豆の国市)

蛭ヶ小島(静岡県伊豆の国市)
蛭ヶ小島は、源頼朝にゆかりある場所です。
平安末期、武士の存在感が増大
平安時代の末期の1156年に、保元の乱という皇族同士の争いが起こりました。
ここで皇族・貴族たちは、朝廷のボディーガードともいうべき武士たちの力を借りることになります。
しかし、それまでは朝廷の言いなりになって働いていた武士たちの存在感が、この戦いを機に増してくることになります。
武士たちが、自分たちの強さに気付きだす
この頃になると、武士たちは徐々に力をつけ初めていたため、
などと、武士が感じ始めていた時期でした。
そして、その武士たちの中に平氏・源氏の一族がいました。
1160年「平治の乱」で、源氏の敗北・平氏の天下へ
この平氏と源氏の対立が決定的になり、1160年に平治の乱が起きます。
この戦いにおいて源氏は敗れ、平清盛率いる平氏は栄華を極めていくことになります。
そして、
「平氏にあらずんば人にあらず」
というレベルまでに驕り高ぶり、全国に平氏に不満を持つ人々が多くなっていました。
頼朝は、伊豆のこの地に流罪へ
先述の「平治の乱」にて敗れたわずか14歳の若き頼朝は、伊豆のこの地に流罪となってやってきたのでした。
なぜ流罪になったのかというと、当時は死罪よりも、
「あえて都から離れた不便な場所に追いやり、あえて惨めな思いをさせる」
ということが行われたからだと考えられています。
また、例えば負けた相手が「天皇」だった場合、さすがに「神様」と同じくらい尊い存在である天皇を殺してしまうのはさすがに畏れ多いということで、「流罪」という措置が取られたものと思われます。

伊豆・蛭ヶ小島・源頼朝と、北条政子の像(静岡県伊豆の国市)
戦いは、いつも「勝ちすぎない」ことが重要
源氏も先祖をたどれば清和天皇という天皇の子孫だったりして、良い血統の持ち主・良い家系の出身でした。
なので平氏としても、ここで負けた源氏を死罪にするのは憚られたのかもしれません。
もし死罪にすると他の源氏一族から恨まれたりして、復讐・反逆されるリスクが怖かった、という事情もあったことでしょう。
戦いとは、いつの時代も勝ちすぎないことが重要なのかもしれませんね。

伊豆・蛭ヶ小島・源頼朝と、北条政子の像(静岡県伊豆の国市)
20年間を、伊豆・蛭ヶ小島で過ごす 北条政子と出会う
話を本題に戻します。
先述の通り、伊豆の国市・蛭ヶ小島は、源頼朝が流れ着いた場所になります。
彼は平安末期の1160年~1180年までの約20年間もの期間をここで過ごし、このとき後の妻となる北条政子と出会いました。

伊豆・蛭ヶ小島・源頼朝と、北条政子の像の前にて(静岡県伊豆の国市)
元々は北条氏の拠点だった、伊豆一帯
現在の伊豆の国市の一帯は、元々は北条氏という一族の拠点でもあったのですね。
ちなみに後の戦国時代に、伊豆・相模(神奈川県西部)あたりを支配した一族である後北条氏と今回の北条氏は、血縁関係は無く無関係です。
以仁王の挙兵、源氏の逆襲劇
頼朝が伊豆に流れ着いてからの20年後、1180年の以仁王の挙兵によって、全国の源氏に対して平氏追討の命令が出されました。
木曽で旗揚げした、源義仲
このとき長野県・木曽にいた源義仲も、木曽・宮ノ越の南宮神社(南宮大社)にて、旗揚げを行いました。
源義仲は別名「朝日将軍」「旭将軍」「木曽義仲」とも呼ばれます。
義仲と木曽・宮ノ越の関係性については、以下の記事でも解説しておりますので、ご覧ください。

義仲と頼朝は、いとこ同士の関係でした。
しかし、お互いに全然協力しないばかりか、むしろ対立してしまいました。
そして、最終的に義仲は、頼朝によって滅ぼされてしまいました。
詳しくは、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

頼朝も、石橋山で敗れる
頼朝も「以仁王の挙兵」には応じましたが、伊豆よりやや北東の神奈川県・真鶴で行われた「石橋山の戦い」において、敗れてしまいました。
このときに頼朝に参戦に応じたのが、
- 湯河原駅(神奈川県足柄下郡湯河原町)
の前に銅像が建っている、土肥実平(または、どいさねひら)という人物です。
また、湯河原・真鶴には頼朝が逃げて隠れたという「ししどの窟」があります。
「石橋山の戦い」と湯河原については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。
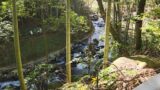
そして頼朝は、真鶴から相模湾・東京湾へと出港してゆきました。
房総半島へ上陸した頼朝
やがて頼朝は、房総半島の南西部にある安房勝山あたりに上陸します。
源頼朝は、その巧みな交渉力とカリスマ性で、房総半島にいた(平氏に不満を持つ)武士たちを次々に味方に率いれてゆきました。
その時、真っ先に頼朝に味方についたのが、現在の千葉県の由来になっている一族の千葉氏になります。
頼朝上陸の地・安房勝山のエピソードについては、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。


檀ノ浦で、平氏を滅ぼす
やがて勢い付いた源氏は、
- 「富士川の戦い(静岡県)」
- 「一ノ谷の戦い(兵庫県)」
にて勝利します。
そしてついには、1185年、山口県下関市の「檀ノ浦の戦い」において平氏を滅ぼします。
やがて源頼朝は、1189年に東北の奥州藤原氏をも滅ぼし、1192年、ここに鎌倉幕府を立ち上げたのでした。
源頼朝を支えた、北条政子

蛭ヶ小島で、富士山の方を向く源頼朝・北条政子の像(静岡県伊豆の国市)
そして源頼朝は平氏を打倒し、征夷大将軍に任命され、鎌倉幕府を開くに至ったのでした。
そして北条政子は、そんな偉大な大将軍の妻となったのです。
英雄の妻となる女性は、彼の苦労時代を支えた女性のみ
これは現代の婚活とは、「逆の関係性」を感じます。
ハイスペ男性を狙う婚活女性は、「既に完成された金持ちの男性」を最初から狙う傾向にあり、それが男性に敬遠されていく結果、上手くいかないわけです。
私の経験上、成功者の男性の妻となっている女性は、その男性が学生時代やまだお金が無かった時代から付き合っていた(支えてきた)彼女であるパターンが多いです。
なので、婚活において「既に完成された金持ちイケメン」と最初から出会える(結婚できる)わけがないのです。
例えば、男性がまだ若くてお金が無くて苦労している時には女性から見向きもされなかったのに、成功して金持ちになった瞬間に寄ってくる女性に対して、いい気分になる男性は恐らくいないでしょう。
当時は「犯罪者」同然だった頼朝を、必死に支えた政子
そう考えると、北条政子は素敵ですね。
頼朝がまだ「犯罪者」として落ちぶれて流れ着いた時代に、必死で頼朝を信じて支え続けたのです。
そうなれば、頼朝も政子に対して恩義を感じ、「自分が頑張っていけるこれたのは政子のおかげだ」と感じて結婚を決意するのは、当然といえば当然です。
いつの時代も、努力無くしていい相手との結婚は出来ないようになっているのですね。
今は富士山に向かって立つ夫婦
蛭ヶ小島の源頼朝と北条政子は、富士山を向いて立っています。
この地域は北条氏の拠点であり、また富士山の見えるとてもよい場所なので、実際の頼朝公は流罪の身分だったとはいえ、そこまで悪い生活は送っていなかったのではないか、とも推測されます。

北条政子の像(静岡県伊豆の国市)
承久の乱に勝利した、鎌倉幕府の御家人
鎌倉幕府が出来てしばらくした1221年、京都の朝廷にいた後鳥羽上皇は、鎌倉に向けて兵を挙げます。
再び、政権を朝廷に取り戻すためですね。
朝廷軍に怯える幕府軍
そんな攻めてくる天皇の兵を前に、鎌倉の御家人たちは恐怖してしまいます。さすがに御家人・武士とはいえ、天皇とは神様みたいに尊い存在です。
「天皇の軍」と戦うということは、いわゆる「朝敵(天皇・朝廷に対する敵)」とみなされることと同じであり、国家反逆にも等しい畏れ多い行為だったのです。
北条政子の言葉で勇気づけられる武士たち
そんな萎縮する鎌倉の御家人・武士たちに対して、北条政子が声をかけます。
それは
というものです。
なぜかというと、鎌倉幕府ができるまでの武士は「朝廷のいいなり」であり、いいように使われてきたに過ぎませんでした。
しかし、頼朝が鎌倉幕府を建ててくれたおかげで、武士達の身分は高くなり、朝廷の言いなりという冷遇ぶりもなくなりました。
これが北条政子の「山より高く海よりも深い」という、頼朝への恩というわけです。
朝廷軍を撃破した、鎌倉の武士たち
これによって御家人たちは一致団結して強くなり、後鳥羽上皇率いる朝廷軍を撃破してしまいました。
主にその戦場は、滋賀県大津市・琵琶湖の南の瀬田の唐橋でした。
承久の乱で敗れた、後鳥羽上皇と順徳天皇
この「承久の乱」に敗れた後鳥羽上皇は、島根県の北・隠岐の島に流罪となりました。
また、後鳥羽上皇の息子である順徳天皇は、佐渡島に流罪となってしまいました。
順徳天皇は、結局佐渡島から都(京都)に帰ることはできず、失意のうちに佐渡にてその生涯を終えることとなりました。
佐渡と順徳天皇については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

同じく隠岐に流された、後醍醐天皇
余談ですが、鎌倉時代の末期にも後醍醐天皇が、後鳥羽上皇も同じく島根県の隠岐に流されています。
以下の記事でもわかりやすく解説していますので、ご覧ください。

承久の乱に勝利した、御家人・武士達の末路 贅沢な暮らしで破滅に
「一生懸命」という言葉の由来に
北条政子による勇気付けの後に「承久の乱」に無事勝利した鎌倉の武士たちは、恩賞として西国の土地をたくさん得ることができました。
西国とは、今でいう西日本のことです。
鎌倉の武士たちの主な収入源は、その「土地」にありました。
土地から収穫される作物こそが、まさに収入源だったのでした。
なので武士たちは、自分達の土地を命をかけて守る必要がありました。
そのため「一所懸命(一つの土地に命をかける)」という言葉が生まれ、それが長年にかけて「一生懸命」という言葉に変化しました。
これがいわゆる「一生懸命」と言う言葉の語源となります。
栄光のあと、浪費で落ちぶれる武士たち
しかしその後、西国・京都で贅沢三昧の生活を送ってしまい、あっという間に散財して借金を重ねてしまうような武士もいました。
関東地方・神奈川県にある鎌倉よりも、はるかずっと昔から日本の中心として栄えてきた京都には、酒や女遊びができる場所が元々たくさんあったからですね。
二度にわたる「元寇」 自費での戦いで、御家人たちは困窮に
そして鎌倉時代の後半に入り、1274年と1281年の2回にわたってモンゴル襲来(元寇)にあい、鎌倉の御家人・武士たちは膨大な自費を投入して必死に戦ったものの、なにせ相手は外国。恩賞を貰えることができませんでした。
先述の通り、鎌倉時代の恩賞は「敵地から没収した領土・土地」だったからです。
外国である元を追い払うための「防衛戦」に勝利したところで、敵地の領土を恩賞としてもらうことはできません。
また、戦費も基本的に自費で投入していたため、恩賞無しで武士たちは大赤字になってしまい、借金をする武士が増えてしまいました。
武士達を救う「徳政令」 しかしかえって国内は混乱
そこで1297年、武士達を救うために永仁の徳政令が出され、借金がすべてチャラ(帳消し)にされました。
しかし「貸した人たちの生活」は、徳政令で借金を返してもらえなくなったことでめちゃくちゃになり、かえって国内が崩壊していくこととなります。
そして先ほど少し紹介した(隠岐島から脱出した)後醍醐天皇や楠木正成などの手により、1333年に鎌倉幕府は滅亡、室町時代へと繋がっていったのでした。
この鎌倉幕府の滅亡や楠木正成らの戦いについては、以下の記事でもわかりやすく解説していますので、ご覧ください。

伊豆箱根鉄道・伊豆長岡駅にて休憩 今回の旅も終わり
蛭ヶ小島の観光を終えた後、伊豆の修禅寺にも行ったのですが、こちらに関してはまた別の機会に書きます。
伊豆箱根鉄道・伊豆長岡駅にて、最近出来た「イズーラ(IZUーLa)」にて休憩~!
イズーラの名前の由来は、たぶん伊豆と静岡弁の「ずら」をかけたものだと思われます。
ちなみに「ずら」は結構有名な静岡弁だったりするのですが、残念ながら今では少し珍しい言葉になります。
ちょっと前であれば伊豆(や静岡県)の田園地帯あたりで、かなりご高齢の方々が「ずら」という言葉を使っていたそうなのですが、現在では高齢者であっても「ずら」という言葉は使わない、という印象となっています。
やっぱりラブライブ!サンシャイン!!国木田花丸ちゃんの「ずら」は可愛いです。
いずっぱこについては、また別の機会に書きたいと思います!
おまけ:筆者の自撮り写真エトセトラ
ここでは、本文のスペースの都合で載せきれなかった写真を載せてゆきます!

蛭ヶ小島より(静岡県伊豆の国市)

蛭ヶ小島より(静岡県伊豆の国市)
今回の旅でも、伊豆の素敵な気候と自然をたくさん満喫することができました!

コメント