釧網本線の鉄道旅と、川湯温泉・硫黄山(アトサヌプリ)の地理・歴史などを、旅行初心者の方にもわかりやすく解説してゆきます!

硫黄山(アトサヌプリ)(北海道川上郡弟子屈町)
川湯温泉駅からは、硫黄山(アトサヌプリ)へ
前回で、川湯温泉駅(北海道川上郡弟子屈町)に到着しました。

川湯温泉駅(北海道川上郡弟子屈町)
ここで、川湯温泉駅からは、バスで硫黄山(アトサヌプリ)へ向かうことになります。
川湯温泉駅から硫黄山(アトサヌプリ)までのバスについて
川湯温泉駅から硫黄山へのバスに関しては、弟子屈町のホームページに情報があります。
弟子屈なび-2025年夏「弟子屈えこパスポート」でめぐる町内周遊バス

このフリーパスをうまく利用すれば、2,000円~3,000円程度の予算で、硫黄山・摩周湖・屈斜路湖・アイヌコタンなどの主要観光地をめぐることができます。
弟子屈町(てしかがちょう)
また、こうした硫黄山・摩周湖・屈斜路湖・アイヌコタンなどの主要観光地が存在する自治体を、弟子屈町といいます。
- 弟→「師弟」のように、「てい」とも読む
- 子→「第一子」のように「し」とも読む。
- 屈→「屈 む」とも読む。
後述する通り、これはアイヌ語の「テシカ・ガ(岩盤の上)」という言葉に由来しています。
アイヌ語で「岩盤の上」 硫黄山の溶岩の、「岩盤の上」に出来た土地
「てしかが」は、慣れるまでにはかなり読みにくい、いわゆる難読地名ではありますが、アイヌ語由来の地名です。
- 「テシカ」→岩盤
- 「ガ」→~の上に
に由来します。つまり、「岩盤の上」という意味です。
これは、硫黄山の火山噴火の溶岩によってできた「岩盤の上」というニュアンスが含まれています。
弟子屈町は、まさにその名の通り、硫黄山の溶岩の、岩盤の上にできた土地なのです。
硫黄をたくさん掘り出していた、アトサヌプリ(硫黄山)

硫黄山(アトサヌプリ)(北海道川上郡弟子屈町)
硫黄山は、アイヌ語で「アトサヌプリ」ともよばれます。「ヌプリ」とは「山」という意味です。
アトサヌプリからは、腐った卵の臭い、つまり腐卵臭がします。この臭いは、火山から出る硫化水素によるものです。
そして、アトサヌプリからは、明治時代にはたくさんの硫黄を掘り出していた歴史があります。

硫黄山(アトサヌプリ)より(北海道川上郡弟子屈町)
明治時代にたくさん堀り出された、硫黄山(アトサヌプリ)の硫黄
かつて、アトサヌプリの硫黄は、明治時代にたくさん堀り出されました。
硫黄は、さまざまな化学製品に用いられ、しかも「硫酸」などの化学薬品の原料にもなることから、色んな工場が必要とするようなとても重要な資源でした。
つまり、掘り出せば掘り出すほど、工場が買ってくれるため、利益につながるわけです。
火山には、「硫黄を含む成分」が含まれている
火山のマグマには、硫黄を含む、様々な成分が溶け込んでいます。
- 地下にあるドロドロ高温液体であるマグマが上昇してゆき、
- 地表に近づいてくると、
- 地下にいるときと比べて圧力が低下してくることに伴って、
- これらの成分がゆるくなり、膨れ上がってガス状になり、
- 火山ガスとして、大気中に放出される
というわけです。
そして、その火山ガスの中に、硫黄が含まれているというわけです。
マグマの圧力の低下により、マグマに含まれているガスが放出→硫黄も放出される
マグマは、火山の高温により融点を上回った、ドロドロの岩のことです。
このマグマは、地中のとても奥深くにおいては、
- 周囲の岩石
- マグマ自身の重さ
によって、ものすごく高い圧力を受けています。
つまり、マグマは地中では「ぎゅうぎゅう詰め」に押さえつけられている、というわけです。
マグマが地表に押し上げられると、周囲からかかる圧力が減る
しかし、火山の噴火によって上に登ってゆき、地表に近づいてくにつれて、周囲の岩石の量も減ってきます。
これによって、マグマにかかる圧力も低下してゆきます。
このマグマの圧力が空気中で低下していくことにより、
- マグマに含まれているガスが、急激に膨れあがってしまい、
- 大気中に火山性ガスとして放出されてゆく
ということになります。
これが、いわゆる「噴火」や「溶岩流」というような、我々人間にとっては怖い形で、地表に放出されるという原因となります。
そして、その(火山に含まれる)自然の硫黄を有効利用していくことによって、様々な工業資源として使われるというわけです。
硫黄は、自然の中にたくさん存在するエ資源である
特に、火山地域では自然硫黄として存在し、燃焼によって熱エネルギーを発生させることができます。
また、石油や天然ガスの精製をしていく過程で、いわゆる「副産物」として得られる硫黄も、重要なエネルギー源です。
硫黄の「精製」 不純物を取り除くのに、不可欠な作業
また硫黄は、自然の中にそのままで存在しているわけではなく、精製というものをして、不純物を取り除かないといけません。
硫黄は、火山活動や鉱床など、様々な形で自然界に存在しています。
しかし、これらの自然硫黄には、様々な不純物が混ざっていることが多いです。
そのため、そのままでは人間による利用に適していない場合があります。
そのため、硫黄を精製し、純度を高める必要があります。
硫黄が工業製品でよく使われやすい理由
硫黄は様々な酸化の状態を取ることができるた様々なバリエーションの化合物を形成さすることができます。
これが、工場にとってはとても好かれることになります。
これは、硫黄の他の物質には存在しないアドバンテージです。
また、硫黄は他の物質と反応しやすく、特に酸化剤と反応して、二酸化硫黄を生成します。
この性質を利用して、例えば、ゴムの加硫や、医薬品、農薬の製造に利用されます。
天然の中にたくさん存在し、手に入りやすい硫黄
さらに、硫黄は、天然に豊富に存在しています。
つまり、自然のなかにたくさん眠っているため、豊富にあるということです。

摩周湖方面からの、アトサヌプリ(硫黄山)(北海道・弟子屈町)
硫黄は火山からの他、原油から不純物を取り除く「精製」からも入手できる
また、硫黄は石油の原型である「原油」を精製して、より純粋で純度の高い石油を製造する過程でも、「副産物」として得られます。
そのため、硫黄は比較的容易に入手できます。
また、三重県四日市市では、四日市ぜんそくの反省を生かして、原油から精製する時に、硫黄を貴重な資源として取り出すことに成功しています。
これに加えて、公害の原因となった「硫黄酸化物(SOx)」を排除することにも成功したのでした。
そのため、四日市市はこの「一石二鳥」を実現することに成功したわけです。
詳しくは、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。
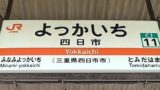
安い輸入品におされて衰退してしまった、国内の硫黄採掘業
昔は、確かに日本でも硫黄をたくさん掘っていました。
資源があまりない日本にとって、昔は硫黄は輸出するための商品としても、とても重要なものでした。
しかし、今ではほとんど安い輸入品におされてしまっており、国内の硫黄採掘は衰退しています。
火山大国の日本 昔は火山から採れる硫黄は、とても重要だった
20世紀前半まで、日本は火山大国である特性を生かし、硫黄を大量に産出していました。
特に、阿蘇山や硫黄島などが主要な産地でした。
国産の硫黄の衰退の原因としては、安価な海外からの硫黄の輸入が拡大したことで、国内採掘の硫黄では、コスト面での競争に勝てなくなったことが主な原因です。
また、国内採掘の現状として、現在、国内で硫黄を採掘しているのは、ごく一部の企業に限られています。
多くは、輸入品を加工して利用する形になっています。
また、日本は言うほどの無資源国家ではありませんが、それでもやはり主要な資源の多くを、輸入に頼っています。
先述の通り、硫黄は日本で採掘されており、過去には重要な輸出品でした。
しかし、現在では国内で十分に買われ使われるほどの需要を満たすレベルにまでは、採掘されていないが現状です(正直、儲からない+赤字になってしまうため)。
かつて大量の硫黄を運んでいた、福島県の「沼尻鉄道」
また、かつて硫黄を運んでいた代表的な鉄道の一つに、福島県の沼尻鉄道がありました。
この沼尻鉄道は、かつては福島県の磐梯山の裏側に大量に眠っていた硫黄を運び出していたのでした。
しかし、やはり戦後に海外の安い輸入品の硫黄に負けてしまい、衰退・廃止となってしまいました。
詳しくは、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

硫黄山から標茶(しべちゃ)まで出ていた、硫黄運搬のための鉄道
また、明治時代には後述する標茶までの鉄道(通称:硫黄山鉄道)が敷設されました。
標茶とは、硫黄山がある弟子屈町の、やや南にある町です。
この標茶までの鉄道が引かれたことによって、それまでは馬や舟などで運んでいた硫黄の運搬作業が、かなり効率化されたのでした。
さらに、機械を使った蒸気精錬器が導入され、それまでの非効率だった手作業による精錬作業(不純物を取り除ための作業)が大幅に改善され、コスパが良くなったのでした。
こうして、硫黄山では(当時としてはかなり進んだ)近代的な採掘事業を展開していくことができるようになっていったのでした。
また、現在の弟子屈町は、かつての硫黄山で働く人々や、川湯温泉で働く人たちによって賑わったのでした。
硫黄山(アトサヌプリ)における、硫黄採掘の歴史
過酷だった硫黄山での採掘作業
そして硫黄は、これまで何度も解説してきたように囚人による過酷な採掘労働によって掘り出されたものです。
つまり、以前解説した網走監獄などと同じ事情によるものです。
「言論の自由」が無かった明治時代
明治時代の当時は「言論の自由」がほぼなく、まだ国民の参政権は充分に確立されたものではありませんでした。
例えば、高額納税者しか選挙に投票することができず、大多数の国民の意見が政治に全く反映されない、というような状況でした。
こうなると、金持ちばかりに有利で、大多数の層や弱者に対する政治は行われにくくなる、ということにも繋がってしまいます。
明治時代は、15円以上の納税者(約1%程度)、つまり富裕層しか選挙権が無かったのでした。
つまり明治時代は富裕層にしか参政権が無かったちめ、
というような状況だったわけです。
こうした明治政府への不満のため、人々は「自由民権運動」を起こして、明治政府に反対してきました。
しかし当時は、先述の通り「言論の自由」が無かったため、政府に反対した人々は「国家に対する反逆者」として次々に逮捕されてゆき、北海道まで無理やり連れて来られたのでした。
標茶(しべちゃ)の町に存在した、「集治監」
この川湯温泉駅がある弟子屈町の南・釧路市の北に、
- 標茶町
という町があります。
この標茶に釧路集治監という監獄施設があり、ここに上記の囚人たちが収容されていました。
集治監とは、囚人たちを収容するための施設で、監獄の初期バージョンといった感じの施設です。
過酷すぎて、次々に倒れていった労働者たち
そして囚人たちは、アトサヌプリの硫黄採掘の労働に駆り出されたというわけです。
その労働は過酷で、囚人たちはどんどん倒れていったといいます。
「どうせ囚人なんだから、給料も与えなくていいや」
などのような雰囲気であり、ほぼ人権無視のような使役が行われていたわけです。
標茶・釧路まで運ばれた、硫黄山(アトサヌプリ)の硫黄
このアトサヌプリ(硫黄山)で掘り出された硫黄は、「釧路鉄道」と呼ばれる今や伝説的な明治時代の鉄道によって運ばれました(現在は廃止)。
山の中を、たくさんの硫黄を載せた蒸気機関車が走っていったわけです。
その釧路鉄道は、先述の標茶まで続いていたのでした。
しかし、当時は釧路湿原に鉄道建設することは、難易度が高かったのでした。
そのため、仕方なく釧路川の水運によって、釧路まで運び出されたというわけです。
つまり、船に大量の硫黄を載せて運んだわけです。
当時は高速トラック等存在しなかったので、この水運が最も効率が良かったわけですね。
次回は、摩周湖の話題へ

摩周湖(北海道川上郡弟子屈町)

コメント