
尾道・向島の景色(広島県尾道市)
今回は、個人的に広島県尾道市に行ったときの話をしてゆきます!尾道の歴史や文学、観光などについて、わかりやすく解説してゆきます!
【広告】
瀬戸内海に面した都市・尾道市
広島県尾道市は、広島県の東部に位置し、また瀬戸内海に面する都市になります。
詳しくは後述しますが、「坂の町」としても知られ、たくさんのドラマ・小説・映画・アニメなどのロケ地や舞台となってきました。
「福山都市圏」に属する尾道
尾道市は、東隣にあり広島県で第2の人口を誇る大都市である福山市とも距離的に近いため、「福山都市圏」にも含まれます。
つまり、尾道市と福山市は、経済の面でお互いに欠かせない存在であるという意味になります。
経済は、常に都市間で「つながっている」
すなわち、福山市へ通勤したり、また買い物に行かれる人が多いわけなので、いわゆる
- 「人」
- 「お金」
- 「モノ」
などがこの両都市間で動くことになります。
こうした「動き」も、いわゆる経済(economy)を構成する要素のうちの一つとなります。
経済でのつながりで、尾道と福山は不可欠な関係性
例えば、尾道市民の方が福山市で買い物をしたりご飯を食べたりすると、その利益は当然ですが福山市に入ります。
さらに、そこから福山市へ「住民税」「消費税」という形で、納められることになります。
一方、尾道市民の方が福山市の職場(会社など)まで出勤しているとすると、その稼いだお金(所得)に対して課せられる「住民税」は、尾道市(※)に対して、納められることになります。
※その年の1月1日時点で住んでいる自治体が、尾道市である場合です。
以上のような
- 「お金の流れ」
- 「人の流れ」
- 「モノの流れ」
があるため、福山市と尾道市は経済の面でとても切っても切れない(お互いに助け合う)重要な関係にあるわけです。
そのため、経済面で「福山都市圏」に属しているといえるわけですね。
向島むかいしまとの間にある「尾道水道」
尾道市は、先述の通り瀬戸内海に面している街になります。
また、対岸の向島との間は、その狭さから「尾道水道」と呼ばれています。

向島と尾道水道(広島県尾道市)
尾道市の(尾道水道を挟んで)向こう側にある向島へは、フェリーで100円、わずか5分の乗船時間で行くことができます。

向島ゆきのフェリーからの尾道市街地(広島県尾道市)
「水道」「海峡」とは?どう違う?
水道と海峡は、ちょっと似ている言葉ですね。
海峡と水道は、どちらも「2つの陸地によって狭められた海域」という意味であり、特に何か明確な違いというものはありません。
個人的なイメージ「内海」「海峡」などの大きさ
以下、個人的なイメージです。
の順に大きい(広い)気がしています。
※これは個人的な勝手なイメージです。もちろん例外もたくさんあると思います。過度に信用しないでくださいね!
したがって、海峡・水道・瀬戸・内海などの用語は、例えば「大きさ」や「幅」「広さ」などによる明確な「基準」や「定義」などがあるわけではありません。
モノの「集散地」としての尾道

尾道の港(広島県尾道市)
尾道の地は、古くから海運によるモノの集散地として、繁栄してきました。
「海運」とは?
海運とは、簡単にいえば船でモノを運ぶことです。
昔はトラックや貨物列車などは無かったので、船で大量の荷物を運んだ方が効率がよかったのです。
特に尾道水道や瀬戸内海に面したベスト立地な尾道は、まさにその海運のための拠点として歴史的に栄えてきました。
「集散地」とは?
集散地とは、商品や材料などのモノを集めて保管しておき、必要になったら、それに応じて運び出すための場所のことをいいます。
例えば、「倉庫」や「蔵」に保存しておき、いざ必要になったら(クライアントから発注されたら)そこから発送する、みたいなイメージです。
このように、モノが集まったり、散ったりする場所だから「集散地」というわけです。
そして「モノがたくさん集まってくる場所」ということは、そこで働く人も増えるわけなので、結果的に町全体が大きく発展していくことになります。
明治時代の鉄道開通 海と陸の「接続点」となり、より繁栄
明治時代になり日本でも鉄道がひかれるようになると、私鉄・山陽鉄道(現在のJR西日本・山陽本線)によって尾道の町にも鉄道が来るようになったのでした。
山陽本線は、明治時代に「山陽鉄道」という私鉄の会社によって作られました。
なぜ私鉄「山陽鉄道」が出来たのか
ではなぜ明治時代に私鉄会社がわざわざ鉄道を作っていったのか。
それは、1877年の西南戦争において国は多大な予算を使い果たしていったため、国に新しく鉄道を作る余裕が無かったためです。
そうした事情から全国各地に民間の鉄道が敷かれていったわけです。
1906年に「鉄道国有化」 戦後、国鉄からJR線へ
ところが、1906年に軍事力強化のために国有化され、戦後になって国鉄→JR社となり、現代に至っています。
今は「JR社の路線」であっても、元々は明治時代の「民間鉄道会社」をルーツとしている路線は他にも多いです。
(例:東北本線など)
「海運」と「鉄道」の接続点として栄えてきた、尾道
話を元に戻します。
こうして明治時代に尾道の町にも鉄道が来るようになったことにより、尾道は鉄道(線路)と海運(船)とが接続するという「接点」となりました。
つまり、鉄道で運んできた荷物を、船に載せ換えたりするわけです(逆もしかり)。
その結果、たくさんのモノや人が、尾道の町に集まってくるようになったのでした。
そうなると、先ほどと同じで、尾道の町や港で働く人も増えてくるわけなので、結果的に町全体が大きく発展していくことになります。
かつては広島県東部・第一の都市に
こうして、尾道市は広島県東部(備後地方)においては最大の人口を抱える都市となりました(しかし、後に福山市に抜かれてしまいます)。
「備後国」の都市としての尾道
尾道市は、飛鳥時代以降は「備後国」の一部でした。
- 備前国:岡山県岡山市を中心としたエリア
- 備中国:岡山県倉敷市を中心としたエリア
- 備後国:広島県福山市を中心としたエリア
これら3つの国(エリア)は、元々は吉備国という1つの大きな国だったわけですが、飛鳥時代に3つの国に分割されたため、
- 「備前」
- 「備中」
- 「備後」
と分かれているわけです。
高度経済成長期以降、福山市の発展
先述の通り、尾道は明治時代以降、広島県東部における最大の都市として発展してきました。
しかし1960年代の高度経済成長期になると、東隣の福山市が急速に発展してゆき、大規模な工業都市として成長してきました。
これにより尾道市は、福山市に抜かれてしまうことになります。
平地にめぐまれ、工場をたくさん建てるのに適していた福山
福山市はかつての旧・城下町であったことと、また工業に適した平地に恵まれているという好条件もあって、そのメリットを最大限に活かして恐ろしく発展してきたのでした。
平地が多ければ多いほど、たくさんの大きな工場を建てることができます。
坂道が多く、工場を建てるには不利だった尾道
逆に、坂道が多く平地の少ない尾道では、大規模な工場を建てることはなかなか難しいです。
何より、工場をたくさん建てると美しい尾道の景観が損なわれてしまいます。
これにより尾道市は、1960年代以降は福山市に、広島県東部における中心地の座を明け渡してしまったのでした。
ただし、現在でも尾道市は福山都市圏の有力都市の一つとなっています。
福山市が「商工業の街」であるならば、尾道市は「観光とロケの街」ともいえるでしょう。
瀬戸内の十字路・尾道市
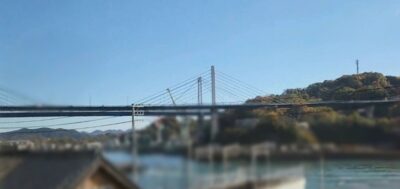
しまなみ海道・尾道大橋(山陽本線の車窓より)(広島県尾道市)
尾道市は1999年の「瀬戸内しまなみ海道」の開通によって四国の愛媛県今治市と、陸路で結ばれることになりました。
つまり四国とは「陸続き」になったわけです。
これは本当に大きな違いであり、本州~四国間の移動はそれまでの「船での移動」よりも圧倒的にスピーディーかつスムーズになったのでした。
「しまなみ海道」により、本州と四国の移動がスムーズに

しまなみ海道・遠景(広島県)
「しまなみ海道」は、本州と四国との間の交通・行き来をより円滑(スムーズ)なものにし、これによって経済の発展につながることを目的として建設された道路になります。
しまなみ海道は、瀬戸内海に浮かぶたくさんの島を橋で結んで、愛媛県今治市に至ります。
これによって物流面での利便性が、とても高まっていったのでした。
つまり、本州~四国との間でよりたくさんの荷物を素早く運んだり、また人々のスムーズな移動が可能になったわけです。
タオルと造船の、今治市
愛媛県今治市は、
- タオルの生産
- 船を作る「造船業」
で有名です。
今治市には、日本一の造船所があります。
「瀬戸内の十字路」東西南北の道路が交差する街に
また、2015年には尾道~松江(島根県)を縦(南北)に結ぶ「中国横断自動車道(尾道松江線)」が開通したことで、尾道は
- 「南北」と「東西」の交通が、それぞれクロスする位置付けの街となった
ため「瀬戸内の十字路」と呼ばれることもあります。
昔はこういった
- 十字路のことを「辻」、
- 分かれ道のことは「追分」
とも呼んでいました。
「坂の町」尾道 数々の作品のロケ地・舞台に登場

坂の町・尾道
尾道市には坂道がとても多く、
- 「坂の街」
- 「文学の街」
- 「映画の街」
などとしても知られて(呼ばれて)います。

尾道の街なみ(広島県尾道市)
文学の分野においては、明治時代の小説家である
- 林芙美子
- 志賀直哉
などといった作家が移住して住んでいたことでも知られています。
また、尾道を舞台とした作品をも発表していったのでした。
志賀直哉「暗夜行路」のモデルに
志賀直哉は代表作として「暗夜行路という作品がよく知られています。
ちなみに、この小説は彼が尾道に住んでいた時期に書いていた「時任謙作」という作品を原型としています。
なお時任謙作とは、暗夜行路の主人公になります。
私は昔ラブコメ系の漫画が昔好きだったので、「ぱすてる」という漫画が好きでした。
漫画では、尾道の景色が忠実に描かれていました。
幼少期は旅ばかりだった!?林芙美子さんの半生
旅そのものが人生だった、林芙美子さん
同じく尾道に移住していた、明治~昭和にかけての作家である林芙美子さんは、幼少期に行商(物売り)の親について各地を転々としていたという不遇な人生だったのでした。
そんな不遇な人生から、1928年~1930年にかけて「放浪記」という著書を出して、ベストセラーとなっています。
幼少期は、下関~九州北部を転々としていた
彼女は明治時代の1903年に、山口県下関市に生まれたと自身で発言しています。
しかし後の研究により、関門海峡を挟んで向こう側の地域である、福岡県北九州市門司区出身だったことがわかっています。
幼い頃は行商をやっていた親の影響で、九州~山陽地方のあちこちの地域を引っ越してばかりの生活を送っていたのでした。
ちなみに行商とは、自身の特定の店舗(お店)を持たずに、商品を「リアカー」や「軽トラック」などに載せてあちこちに移動して商売を行う人のことです。
例えば「Amazon」や「楽天」などのネット通販が存在しなかった、まさに昔ならではの商売といったところですね。
彼女はそんな「行商」を行う親について生活する中で、
といった順に、九州の北部地域を引っ越し続け、4年間で7回も学校を変わって(転校して)いたのでした。
そのために「親しい友達が一人も出来なかった」のだといいます。
そんな中、彼女は1916年・13歳のときに尾道に引っ越してきて、落ち着いています。
「旅そのものが、ふるさとだった」林芙美子さんの生涯
ちなみに著書「放浪記」によれば、
「私は、したがって旅が古里であった。」
という、なんとも衝撃的な冒頭文から始まっています。また、そんな不遇な人生だったことがわかります。
ちなみに私(筆者)の場合は、親が「大の旅行嫌い」だったのでした。
そのため、幼少期~高校生にかけて旅行に連れていってもらった経験がほとんどなく、別の意味で不遇な半生でした(^^;
林芙美子さんとは「足して二で割ればちょうどよい」人生だったのかもしれません。
尾道を舞台とした映画「東京物語」「尾道三部作」
映画では小津安二郎監督による「東京物語」(1953年)が、尾道をロケ地として撮影されています。
また、1980年代に流行った映画である
- 「転校生」(1982年)
- 「時をかける少女」(1983年)
- 「さびしんぼう」(1985年)
の3作品は「尾道三部作」として、当時とても有名になりました。
この「尾道三部作」は、若い世代に対して尾道の存在を知らしめ、有名にしたのでした。
そうなると、ドラマの「聖地巡礼」として、尾道を訪れる人も多かったことでしょう。
アニメの五大聖地・尾道
尾道市は、2000年代以降にはアニメの舞台としてもよく使われており、アニメファンからは「アニメ五大聖地」の一つとして数えられるようになりました。
2000年代のアニメ五大聖地
- 鷲宮神社(埼玉県久喜市):らき☆すた(2004年~)
- 木崎湖(長野県大町市):おねがい☆ティーチャー(2002年)、おねがい☆ツインズ(2003年)
- 豊郷小学校旧校舎群(滋賀県犬上郡豊郷町):けいおん!(2009年~)
- 城端(富山県南砺市):true tears(2008年)
- 尾道:かみちゅ!(2005年)、ぽんのみち(2024年)など
※筆者は「ラブライブ!」系以外のアニメにはあまり詳しくありません。一応かなり調べたのですが、間違っていたらごめんなさい。
けど「けいおん!」は昔ちょっと気に入っていた時期がありました。
みんなカワイイですよね!
「恋人の聖地」尾道
尾道には「恋人の聖地」があります。
なぜ「恋人の聖地」があるのか?
「恋人の聖地」というと、単なる「カップルの名所」とも思われそうですが、実は「NPO法人地域活性化支援センター」という非営利団体によってきちんとした目的を持って指定された場所なのです。
NPO(Non-Profit Organization)とは、いわゆる非営利団体のことをいいます。
つまり、ボランティアのための団体ということです。
「プロポーズにふさわしい景色」を国が選定
そして国は、この非営利団体による活動を、法律によって推奨しています。
なぜかというと、世の中を少しでも良くするために、いわゆる「ボランティア」とそれに関わる人たちを推進・応援していく目的があるためです。
また、この活動は観光庁という国の組織や、また旅行会社であるJTBからも応援されています。
つまり、「恋人の聖地」に指定された場所は「国からのお墨付きがある」も同然なので、知名度も上がりますし、指定されるメリットはとても大きいのです。
恋人の聖地とは、このNPO団体によって指定された、例えば「プロポーズをするのにふさわしい景色」を備えた、ロマンティックな景色を持つ観光スポットのことをいいます。
まぁ、夜景なんかはまさにカップルにとってベストですね。
少子化を改善するため、国が恋愛を推進する施策
ではなぜ「恋人の聖地」が指定されるのかというと、それは恋愛を推奨することにより少子化対策と、それに伴う(人口が増えることによる)地域の活性化を目的としているからです。
つまり、少子化対策の一環として、若者の「恋愛離れ」を止めさせ、若者の「恋愛」と「結婚」を促すわけです。
恋人の聖地には、プロポーズにふさわしいロマンティックなスポットであることが求められているわけです。
派生余談:「若者の恋愛離れ」「結婚離れ」について考察
しかし近年では、若者の「恋愛離れ」が進んでおり、深刻化しています。
もちろん、他にも
- 「結婚離れ」
- 「ビール離れ」
- 「車離れ」
など、いわゆる「離れシリーズ」が著しくなっています。
今や「恋愛はコスパの悪いエンタメ」に!?
特にZ世代(およそ1996年~2012年くらいにかけて生まれた世代)にとっては、恋愛とは「コスパ(コストパフォーマンス)とタイパ(タイムパフォーマンス)の悪いエンタメ」として認識されてしまっている模様です。
まあ確かに恋愛は、
- 初めは異性といちいち連絡とって、
- 好みのレストランを相手の好みを考えながら予約して、
- いざデート(食事)になるとお互い趣味が合うかすらわからない段階で気まずい会話をして、
- 最後にはレジ会計時に「おごり・奢られ論争」の気まずい雰囲気になったりして、
・・・などの様々な面倒臭い作業があるわけだったりします。
そのため、よくよく考えると恋愛って要素分解すると「様々なアクティビティ」があるため、心理的・時間的・金銭的にもとても負担になるわけですね。
恋愛よりも、趣味を優先・趣味に没頭する人が増加
つまり、そんなコスパ・タイパの悪いエンタメ(=恋愛)に縛られるよりも、むしろ趣味に没頭する方が楽しいというわけですね。
2026年4月からは、「独身税」が導入!?
しかしそうして皆が恋愛や結婚を敬遠してしまうと少子化につながってしまうリスクがあるため、政府としては困るわけです。
そのため2026年3月からは、ついに日本でも「独身税」が導入されます。
もちろんこれは「独身税」という名前ではなく、正確には「子ども・子育て支援金」という名前で徴収される税金なわけです(それで得られた財源はもちろん「子育て」のために充てられる)。
しかし、実質上は「独身税」と変わらない要素があるため、今ネット上ではかなり物議を醸していたりします。
独身を選択するのか、結婚を選択するのか
なお「独身税」といえばブルガリアという国での失敗事例が良く知られており、独身税の負担が若者にとって大きくなり、余計に結婚離れと少子化が進んでしまった、というエピソードがあります。
今後は「独身税」を払いたくないために結婚する人が出てくるのか、あるいは「独身税」を払ってでも独身を選択し、独身を謳歌するのか・・・など、様々な生き方・考え方をする人が出てくるのかもしれません。
こうした「恋愛」「結婚」「少子化」の問題って、なかなか難しいですね。
色々書きましたが、あなたがこうした問題に対して少しでも興味を持ってもらえるきっかけになればと思っております。
「倉敷地」としての尾道
最後に、ちょっと真面目な歴史の話を。
尾道は、平安時代末の1169年、大田庄という、現在の広島県・世羅町にあった荘園の倉敷地として指定されていたのでした。
そして、これこそがまさに、尾道の発展の基礎となってきたのでした。
現在の備後地域の内陸部に位置する世羅町にあった荘園である大田庄は、とても肥沃な地だったのでした。
そのため、たくさんの穀物が採れたのでした。
「荘園」とは?
荘園とは、平安時代にメジャーとなった、「巨大な田んぼの集合体」のようなものです。
なぜ荘園ができたのか
なぜそこまで「大きな田んぼ」に成長したのか。
それは、743年に制定された墾田永年私財法により、人々は国に遠慮せずに自由に田んぼを耕せるようになったためです
※それ以前は、耕した人が亡くなると、田んぼを国に返還するというルールがあったのでした(公地公民)。
そんな感じで自由に耕しまくって、大きくなった田んぼが「荘園」というわけです。
「倉敷地」の由来は?岡山県倉敷市の由来
倉敷地くらしきちとは、荷物・穀物などを一時的に保管していた場所のことをいいます。
つまり「倉」「蔵」が多くあったわけです。
例えば、水運に便利な「川」や「海岸」などがある地域には、上記の「荘園」などで採れた穀物などを運んできて、保存して貯めておく「倉敷地」があったのでした。
岡山県倉敷市は、かつてここが倉敷地だったことに由来している代表的な例です。
それは有名な倉敷美観地区にたくさん存在する「倉」「蔵」として残っています。
ちなみに「倉」と「蔵」は、ほぼ同じ意味の言葉であり、現代でいうと倉庫やコンテナなどになります。
尾道は荘園の「倉敷地」としても栄えてきた
話がズレましたが、平安時代の尾道はそんな荘園・大田庄でたくさん採れた穀物を保管しておくための「倉敷地」だったのでした。
このことで、多くの人がそこで働くようになり、現代の尾道の発展につながってきた、というわけですね。
以上・今回はここまで
以上、最後にちょっと真面目な歴史の話をしたところで、今回は終わりにしたいと思います!
お疲れ様でした!


コメント