奈良井宿(長野県・木曽路)の観光・歴史について、わかりやすく解説してゆきます!
旅行を楽しむためのノウハウを解説してゆきます!

中山道・奈良井宿(長野県塩尻市)
今回は、長野県塩尻市・中山道・奈良井宿の探訪・歴史についてです!
中山道・鳥居峠などの観光・歴史について、わかりやすく解説してゆきます!
【広告】
中山道・奈良井宿
今回は、長野県塩尻市にある、
- 中山道・奈良井宿
の探訪・歴史についてです。
奈良井宿は、長野県塩尻市にある、中山道34番目の宿場町です。

中山道・奈良井宿(長野県塩尻市)
「中山道」とは?
中山道とは、かつて江戸時代に人々が江戸(東京)~京都の区間を旅するときに、「徒歩」または「馬」で、約20日ほどかけて旅をしていた道路の一つです。
いわば、リニア中央新幹線の江戸時代バージョンです。
多くの人は「徒歩」で向かって旅をするために、何日も何日も宿場町に泊まりながら、時には険しい峠を越えながら、はるばると向かっていったわけです。
現在は東海道新幹線で約2時間ほどの距離であり、その気になれば日帰り旅行も可能です。
しかし、当時は約20日もかかっていたわけだす。
全部で69の宿場町が存在した
江戸~京都の途中には全部で69箇所の宿場町があったため、「中山道六十九次」と呼ばれたりもします。
奈良井宿は、その69箇所あった宿場町のうちの一つになります。

奈良井宿(長野県塩尻市)
木曽路には、全部で11の宿場町が存在した
さらに木曽路には、全部で11箇所の宿場町があったため、木曽十一宿とも呼ばれます。
奈良井宿は、その木曽十一宿における、江戸側(塩尻側)から数えて2番目の宿場町になります。
また奈良井宿は、木曽十一宿の中では、最も標高が高いところ(約900m)に存在しています。
奈良井宿への最寄駅は、中央西線「奈良井駅」
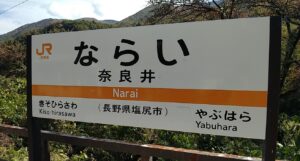
奈良井駅(長野県塩尻市)
奈良井宿へは、中央西線・奈良井駅が最寄駅になります。
「特急しなの」号では止まらないため、塩尻駅からのアクセスからが確実です。
塩尻駅~奈良井駅の鉄道行程については、以下の記事でもわかりやすく解説していますので、ご覧ください。

「重要伝統的建造物群保存地区」に指定されている、奈良井宿

中山道・奈良井宿(長野県塩尻市)
現在では「重要伝統的建造物群保存地区」として、かつて江戸時代に繁栄していた当時の町並みが保存されています。
つまり、江戸時代の建物がそのまま残っているという意味で、とても貴重なのです。
日本に江戸時代の建物が、ほとんど残っていない理由
現代の日本には、
- 江戸時代の木造建築
- 明治時代のレンガ造りの建物
がほとんど残っていないことは、なんとなくご存知だと思います。
一般的に、日本の昔の建物は
- 地震による倒壊
- 戦時中に、空襲などにより消失
- 新しいビルの再開発のために、取り壊してしまう
などの理由で、ほとんど残っていないことが多いのです。
地域の努力や国のサポートなどにより、現在でも残されている
そのため、奈良井宿のような伝統的な建物は、とても貴重であるというわけです。
それは地元の人々の努力によって懸命に残すための取り組みを行ってきたり、あるいは後述するように国のサポートを受けながら維持・管理を続けてきた結果、今でも残っているのです。
重要伝統的建造物群保存地区とは?
奈良井宿は、国から重要伝統的建造物群保存地区に指定されています。
重要伝統的建造物群保存地区とはとても難しい表現ですが、簡単にいうと
として指定されることです。
奈良井宿のような伝統的な建物は「日本の宝」であるため、風化されてはなりません。
なので「国がお金を払ってでも守っていきたい文化財」として、認められているという意味です。
なぜ「昔の建物」を、厳選して守っていく必要があるのか?
昔の建物は、雨風などによって簡単に痛んだり、老朽化したり、腐敗したりしてゆきます。
それらを防ぐには、人の手による維持・修復・清掃などが必要になってくるのです。
それにはお金(人件費や材料費など)がかかるため、国がお金を出してあげるということです。
しかし、国の予算には限りがあるため、何でもかんでも保存地区に指定するわけにはいきません。
ただ古い建物というだけでは、国がサポートするわけにはいかないのです。
なので厳しい審査を通った建物だけが、この保存地区として認められるというわけです。
国が厳選し、管理する必要があると認めた建物たち
重要伝統的建造物群保存地区とは、歴史的にとても重要であるとみなした建物たちを、文部科学大臣が指定している地域のことです。
日本の文化財保護法において規定されている、公費(国のお金)を使ってまで保護されるべき(守っていきたい)文化財のことをいいます。
「文化財保護法」によって決められる
文化財保護法は、
- 国や町などから指定された(厳しい基準・診査をクリアした)文化財については、
- これの保存・維持のために必要な経費の一部を、
- 公費(国や町のお金)で負担することができる
という法律です。
これらについては、以下の記事でもわかりやすく解説していますので、ご覧ください。

そもそも「木曽路」とは?
島崎藤村の小説「夜明け前」が詳しい
木曽路の南端部にあたる馬籠宿出身である小説家・島崎藤村という方がいます。
島崎藤村(1872年~1943年)は、木曽の南側の出口にあたる、岐阜県中津川市の馬籠の出身です。
彼の小説「夜明け前」によれば、木曽路の様子が以下のように記述されています。
- 木曽路は、すべて「山の中」である。つまりすべてのルートが、険しい山に囲まれている。
- 海側のルート「東海道」を通りたくない者は、否が応でもこの木曽路を通らなくてはならなかった。
- 新しく出来た道は、どんどん低い(木曽川がある)位置に移動してきた。
- 昔は険しい山道にあったが、どんどん切り開かれてゆき、低く通りやすい位置に移動してきた。
- 狭くて険しい道には、蔦を伝って移動するしかなかった。
- 木曽川がひとたび氾濫したときは、それぞれの宿場町で、再び通行可能になるまで、待つしかなかった。
などといった感じで、当時の地元民ならではの木曽路のリアルが、鮮明に書かれています。
なので小説「夜明け前」は、今となっては当時のことを知ることができる、とても重要な史料になります。
木曽路は、全て両端を高い山々に囲まれているため、日陰が多く、日当たりも基本的にあまりよくないような場所が多くなります。
中山道・木曽路が「山側」なら、「海側」は東海道
一方、海側の道を、東海道といいます。
今(現代)で例えると、
- 東海道→東海道新幹線
- 中山道→未来のリニア中央新幹線線
みたいなものです。
いずれも、今も昔も(未来も)、東京~京都・大阪を結ぶためには欠かせないルートです。
東海道は、とても規制や制約が厳しかった
東海道は、関所での取り締まりも厳しく、また静岡県の大井川をはじめ、軍事上の理由などにより、橋もまともにかかっていませんでした。
なので旅人たちは、ひとたび豪雨と川の氾濫が起きたりすると、それらが収まるまでは、途中の宿場町で何日も待たされたりしたわけです。
そうなると滞在期間が長くなり、遅れるどころか予算も無駄に使っていたりしたのでした。
大井川については、以下の記事でもわかりやすく解説していますので、ご覧ください。

決まった時間に着く「定時性」に欠けていた東海道
そのため、東海道はいわゆる「定時性(決まった時間に発車でき、決まった時間に着けること)」に欠けていたのでした。
そのため、東海道は別の意味で、旅人たちからは敬遠されれるような街道でもあったのでした。
そんな「東海道を敬遠したい」人たちにとっては、中山道(木曽路)は否が応でも通らなければならなかった道だったというわけです。
奈良井宿の向こうの難所・鳥居峠

鳥居峠方面(奈良井宿側より)(長野県)
奈良井宿は、難所の鳥居峠を、この先に控えていました。
そのため、奈良井宿は、
- これから険しい鳥居峠に挑む前の旅人たち
- 険しい鳥居峠を降りてきて、一休みしたい旅人たち
にとっては、まさしく憩いの場になるような、多くの旅人で賑わうような宿場町だったのでした。
「鳥居峠」とは?
鳥居峠は、
- 長野県塩尻市・奈良井
- 木曽郡木祖村・藪原
とを、それぞれ結ぶ峠になります。
鳥居峠の標高は1,197mもあり、東京スカイツリー(634m)よりも全然高い位置にあります。
そのため、冬はかなり冷え込む場所にもなるでしょう。
そして鳥居峠は、やはり中山道における難所でした。
そのため昼は薄暗く、木の枝がからんでくるような狭い道でした。
現在ではトンネルで、簡単に鳥居峠を越える
現在は、
- 中央本線(中央西線)
- 国道19号
で、トンネルによっていとも簡単に鳥居峠を越えていくわけです。
そのため、そんな昔と比べたら、本当に恵まれた時代に生まれたものだなぁ、と実感させられますね。
鳥居峠については、以下の記事でも解説しているため、ご覧ください。

木曽の名物
木曽の木材
木曽地域はヒノキなど、たくさんの木材にめぐまれています。
その多くは、江戸の屋敷を建設するための木材としても使われていました。
江戸時代は、江戸の人口が爆発的に増えていったため、たくさんの木造家屋が建てられるようになりました。
そのため、木曽の木材はあっという間に不足してしまい、伐採をしすぎて山が大変なことになってしまいました。
尾張藩が厳しく伐採を取り締まった「木曽五木」
そのため、尾張藩は木曽の木を勝手に伐採することを、厳しく取り締まるようになりました。
といって、木をもし1本でも伐採したら斬首刑というような、厳しい取り締まりとなったのでした。
こうして尾張藩が特に伐採禁止とした木曽の五つの木材のことを、木曽五木といいます。
木曽五木の一覧
木曽五木は、以下の五つになります。
- アスナロ
- サワラ
- ヒノキ
- クロベ(ネズコ)
- コウヤマキ
木曽五木については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

櫛や漆器などの「お土産」
木曽では江戸時代から、そんな木曽のヒノキなどを材料として作った
- 櫛
- 木曽漆器
などの工業・製品などがとても盛んだったのでした(もちろん、今でも盛んです)。
こうした土産物は、険しい木曽路を行き交う旅人たちにとっても、とても人気がありました。
つまり、江戸へ帰るときのおみやげに、みんな買って帰ったわけですね。
「お土産」の起源とは?
なお「お土産」の起源は、江戸時代に伊勢神宮に参拝に行くのが庶民の夢だった、ということに由来しています。
詳しくは、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。
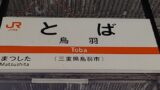
藪原の「お六櫛」
藪原宿のお六櫛が有名です。
木曽のヒノキの木でできた櫛ですね。
詳しくは、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

奈良井川
美しい流れ~奈良井宿のそばを流れる、奈良井川
奈良井宿は、奈良井川のほとりにある集落になります。

奈良井川(長野県塩尻市)
松本市・塩尻市・安曇野地方をうるおす、奈良井川の水
塩尻市・松本市の上水道(飲み水・生活のための水)のために用いられる水である「松塩水道用水」は、この奈良井川から水が取られてきています。

奈良井宿のそばを流れる、奈良井川(長野県塩尻市)
また奈良井川は、松本市よりもやや北の安曇野地域における代表的な農業用水である、拾ヶ堰の水源ともなっています。
つまり、安曇野地方における農業のために使われる水は、この奈良井川から取ってこられているというわけです。
木曽路・鳥居峠における、歴史上数々の戦い
源平合戦における「以仁王の挙兵」と義仲
平安時代後期の源平合戦のとき、1180年に行われた以仁王による、
という呼び掛けが行われていたのてわした。
そのとき、源頼朝のいとこにあたる源義仲(木曽義仲)も、この呼び掛けを受けたでした。
彼は、自身が育った木曽・宮ノ越において、平家を倒すための
をしたのでした。
源義仲(木曽義仲)とは?
源義仲は、木曽で育った源平合戦のときに活躍した武将です。
しかしその念願叶わず、悲劇の最期を迎えた武将でもあります。
義仲はまず越後(新潟県)・北陸方面へ向かうため、まずは北東の長野市方面へと進軍しようとしたのでした。
そのときに、鳥居峠へとさしかかったのでした。
義仲の挙兵については、以下の記事でもわかりやすく解説していますので、ご覧ください。

その後、北陸→琵琶湖→京都と攻めいったのですが、
義仲の最期については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

義仲の子孫!?木曽を支配した「木曽氏」
戦国時代の木曽地域を治めていた大名一族に、木曽氏がいました。
源義仲(木曽義仲)の子孫?
木曽義元は、戦国時代に木曽地域を支配していた人物であり、また源義仲の子孫であり(自称?)、また木曽氏の始祖であるともされています。
本当なのかについての真偽は、残念ながらわかりません。
木曽氏の「通り字」
ちなみに木曽氏には、名前に「義」がついた人物がとても多いです。
例えば、
- 木曽義元
- 木曽義康
- 木曽義昌
などですね。
これを、「通り字」といいます。
「通り字」とは、偉大な先祖にあやかる(縁起がいい)ために使われます。
偉大な先祖とは、言うまでもなく先述の義仲のことです。
義仲の名前を借りて、「義」の文字が代々受け継がれていくわけです。
子孫に受け継がれていく「義」の文字
また「義」の文字は、どこか源氏の名前っぽくなります(もちろん源義仲も、源氏です)。
我々は源氏の子孫だ!ということで、自分達に威厳を持たることができるわけです。
源氏はさらに清和天皇という天皇の子孫でもあるので、さらに威厳が増していくわけですね。
木曽義元が建てた「鳥居」が、鳥居峠の由来
木曽義元は戦勝祈願のために、峠に鳥居を建てて以来、鳥居峠と呼ばれるようになったといわれています。
武田勝頼による、木曽氏との戦い
1582年の鳥居峠の戦いでは、当時既にかなり衰退していた武田勝頼が、さらに木曽側から長野・山梨方面へ攻めてくる織田信長の味方である木曽氏の軍と戦うため、木曽を攻めていったのでした。
長篠の戦いで敗れ、勢いを失っていた武田勝頼
武田勝頼は、戦国時代の甲斐国(山梨県)で最強と呼ばれた武田信玄の息子です。
1573年に父の武田信玄が亡くなった後、その後を継いだ勝頼でしたが、1575年の長篠の戦いで織田信長に敗れてからは、その勢いを急速に失っていったのでした。
長篠の戦いについては、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

木曽軍に誘き出され、深入りで武田軍は劣勢に
このとき木曽軍を指揮していた木曽義昌は、大勢の兵士たちで鳥居峠を囲んで、武田軍を窮地に陥らせた上で、鳥居峠をわざと越えさせのでした。
これは武田側にとっては「深入り」になります。
その後、雪の深い場所へと武田軍をなんとか誘い込んで、木曽軍は武田軍を囲んで攻めたのでした。
これは、やはり地元民ならではの、地形を生かした戦いになります。
戦いにおいては、地形をいかに把握しているかというのはとても重要になります。
木曽軍は、自分達にとって有利な場所へ敵である武田軍を誘き寄せたわけです。
その結果、武田勝頼の部下は戦死・負傷してしまったのでした。
不利に陥った武田軍は、仕方なく北東の諏訪方面へと退却してしまっています。
織田信長の参戦 勝頼は一気に不利に
この乱戦の途中から織田信長の加勢があり、木曽軍側へと加わったことで、武田側はさらに不利になってゆきました。
こうして、織田+木曽の軍は、武田軍のリーダー格の武将たちを含めて、約150人を討取ったのでした。
この「鳥居峠の戦い」での負けにより、武田軍は一気に崩壊し、武田氏は滅亡へ向かってゆく事となったのでした。
武田勝頼の滅亡後 木曽義昌の出世
1582年に武田氏が滅亡した後、木曽義昌は織田信長より、ほうびとして木曽谷の領地を与えられたのでした。
そのほか、織田信長からは長野県の
- 筑摩郡(塩尻市のあたりの地域)
- 安曇郡(信濃大町あたりの地域)
といった領地をも与えられ、さらには深志城(現在の松本城の前身)城主となったのでした。
ちなみに木曽義昌は、元々は武田勝頼とは味方同士でした。
しかし「長篠の戦い」で敗北した武田勝頼がその後に衰退してゆき、自国(山梨県)の人々に対してありえないほどの税金を課して、それを戦費に充てようとしたことから不信感を抱き、武田勝頼を裏切り、織田信長側に寝返ったのでした。
まとめ
いかがだったでしょうか。以下に今回の要点をまとめておきます!
- 奈良井宿は、中山道の宿場町の一つである
- 宿場町とは、途中で旅人たちが止まる場所のことである
- 中山道には69の、木曽には11の宿場町があった
- 奈良井宿は、江戸時代のそのままの風貌を、地元の努力および国からのサポートにより維持・管理している
- 木曽の木材は、江戸時代に伐採されすぎたため、伐採を厳しく規制された
- 木曽には、かつて「木曽氏」という、義仲の子孫を自称する一族によって支配されていた
- 木曽氏の人々は名前に「義」がつく人が多かった。これは義仲にあやかろうとした「通り字」である
- 鳥居峠では、織田信長の側へ寝返った木曽義昌と、武田勝頼が戦った
- 武田勝頼は敗北し、その後に滅亡した
- 勝った木曽義昌は、織田信長から長野県の領土を与えられ、松本城の主となった
今回はここまでです。
お疲れ様でした!


コメント