群馬県みどり市の岩宿遺跡と、歴史をその熱意で覆した相沢忠洋について、初心者の方にもわかりやすく解説してゆきます!

岩宿遺跡・相沢忠洋の像(群馬県みどり市)
岩宿遺跡の解説:はじめに
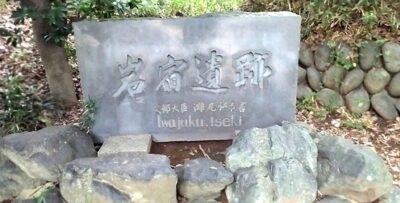
岩宿遺跡(群馬県みどり市)
今回は、群馬県みどり市にある岩宿遺跡の探訪・歴史と、相沢忠洋さんの、熱い情熱と、驚くべき発見の物語を学んでいきましょう!
彼の諦めない心と、たった一つの信念が、日本の考古学の常識を、根本から覆したのです。
この素晴らしい物語を知ることで、実際に岩宿遺跡を訪れた時の感動は、きっと何倍にも大きくなるはずですよ!
日本史を大きく変えた!岩宿遺跡の発見
岩宿遺跡は、群馬県みどり市にある、旧石器時代の遺跡です。
この日本の歴史を大きく変えた岩宿遺跡は、かの太平洋戦争が終わってから、たった1年後の1946年に、ある一人の、どこにでもいるような男性によって発見されたのでした。

岩宿遺跡・相沢忠洋の像(群馬県みどり市)
その男性の名前は、相沢忠洋さんという方です。
彼は、会社勤めをするのではなく、『納豆売り』をしながら、ずっと考古学の研究に情熱を傾けていました。
それは、会社員として時間に縛られるよりも、発掘作業を優先するためでした。
もはやこの時点で、普通の人には無いような、並々ならぬ情熱を感じます。
すなわち、彼は戦前から、納豆を売りながら、発掘作業にハマって、熱中しまくっていたのでした。
つまり、彼は
を送っていたというわけなのです。
自分の情熱だけを信じて、ひたすらに穴を掘り続けた相沢さん、本当にすごいことですよね!
普通の人では、なかなか出来ることではありません。
なぜ相沢さんは「納豆売り」を選んだのか?
ではなぜ相沢さんは、会社勤めではなく、納豆売りをしていたのでしょうか?
それは、もし会社勤めをしていたら、「穴掘り」すなわち、自分の大好きな発掘作業に対して、十分な時間を使うことができなかったからです。
いやむしろ、仮に会社勤めをしていても、彼の性格からして、勤務中も「穴掘り」のことばかり考えて、おそらくまともに仕事になっていなかったことでしょう(^^;)
それくらい、寝ても覚めても穴掘りを続けるような情熱の持ち主だったわけなので、歴史を変えるような大発見ができたというわけです。
したがって、彼は「穴掘り」を何よりも優先し、そして考古学者としての情熱を一番大切にしたかったので、時間に縛られない『納豆売り』という仕事を選んだのですね。
自分の仕事であれば、自分の責任において、
と急に思い立ったときに、いつでも発掘作業にとりかかれるわけです。
これは会社勤めをしていたら、とてもじゃないけど難しいことです。
自分の人生を賭けてまで、好きなことに向き合う彼の姿勢、本当に素敵でカッコいいと思いませんか?
岩宿遺跡・まさかの大発見!歴史を変えたのは、エラい「学者さん」じゃなかった!?
また、普通だったら、日本の歴史を変えるようなすごい遺跡は、おそらく大学の先生(教授)とか、とってもえらい学者さんが発見する、って思いますよね。
しかし、これが違うのです。
なんと、そんな大発見をした相沢さんは、いわゆる学者さんではなかったのです。
彼は先述の通り、誰にも負けないくらい歴史を愛する、
だったわけです。
すなわち、彼はたとえ「学者」「専門家」などの素晴らしい肩書きなどが無かったとしても、
ということを、私たちに教えてくれたのです。
とても勇気が湧いてくるような話ですね。
「旧石器時代」の存在を発見
先ほどお話しした岩宿遺跡から、実は、『旧石器時代』という、とても古い時代のが、相沢忠洋によって発見されたのでした。
すなわち、東京などの地面の下にある、「関東ローム層」という、赤土の層からこの石器が発見されたのです。
したがって、この発見によって、日本の歴史に、この『旧石器時代』が、確かに存在したことが、初めて証明されたのでした。
この出来事は、日本の考古学の歴史上、とても重要なものとされています。
すなわち、私たちが思っていたよりも、日本の歴史がずっと昔から始まっていた、ということが分かったのですね!
昔の日本では、「旧石器時代」は存在しないと思われていた
実は、相沢忠洋が、岩宿遺跡から石器を掘り出す前の時代にあたる戦前までは、
と信じられていたのでした。
すなわち、彼が石器を発見するまでは、日本の歴史は、私たちが習った縄文時代から始まる、と考えられていたのでした。
したがって、相沢忠洋の岩宿遺跡における発見が、
と考えると、本当にすごいことですよね!
岩宿遺跡のある街・群馬県みどり市とは?
岩宿遺跡のある街は、群馬県みどり市になります。
岩宿遺跡への行き方・最寄駅は?

両毛線・岩宿駅(群馬県みどり市)
岩宿遺跡がある群馬県みどり市には、JR両毛線という電車の駅で、岩宿駅があります。
両毛線・岩宿駅から
この「両毛線」という名前は、
- 「上毛国」
- 「下毛国」
という、昔の二つの国の名前から来ています。
すなわち、この2つの国を結ぶ路線、というわけなのですね。
したがって、この岩宿駅こそが、岩宿遺跡へ行くための、一番近い駅になります。
徒歩で岩宿遺跡まで行くのは大変?
しかしながら、ここでちょっと注意が必要です。
岩宿駅から岩宿遺跡までは、歩くと15分〜20分ほどかかります。
つまり、少し距離があるので、
- 「ゆっくり歩いていくのが好きな方」
- 「体力を気にせず、楽に行きたい方」
といったように、人によって移動手段を使い分けるのが良いでしょう。
駅からはタクシーも出ていますので、無理のない方法で、ぜひ岩宿遺跡まで足を運んでみてくださいね。
両毛線とは?
両毛線は、
- 栃木県の小山駅
- 群馬県の新前橋駅
までの路線であり、みどり市はその中間に位置します。
両毛線について詳しくは、こちらの記事(当サイト)でも解説していますので、併せてご覧ください。
みどり市の由来
ちなみに、岩宿遺跡のあるみどり市という名前は、合併前のかつての3つの町・村が、
- 「緑が豊かな、自然にとても恵まれた市であってほしい」
という願いを込めて、「みどり市」と名付けられました。
2000年代以降に新しく合併した市では、ひらがな表記の市名が増加
みどり市のように、2000年代以降に新しく合併した市では、ひらがな表記の市名が増えていっています。
「ひらがな」の市町村が増えた理由
群馬県みどり市のように、2000年代になってから新しく生まれた市町村には、ひらがなで書かれた名前が、とても増えていっています。
つまり、市町村がそれぞれ合併するときに、
- 「新しい市の名前をどうしよう?」
と話し合う場で、「ひらがな」が選ばれるケースがとても多くなっているわけです。
「ひらがな」が選ばれる理由
そこには、以下のようないくつかの理由があります。
- 公平性を保つため:漢字で元の町の名前を入れると、どうしても、ある特定の町だけが目立ってしまいます。すると、公平性を欠いてしまう場合があるためです。
- 親しみやすさを重視するため:小さな子どもからお年寄りまで、誰もが読みやすく、そして、やさしく親しみやすいイメージになるためです。
- 観光のPRのため:ひらがなにすることで、全国の人に名前を覚えてもらいやすく、観光のPR効果が高まるためです。
合併による公平性の確保
このように、複数の町村が合併してできるときには、それぞれの町村の漢字表記をそのまま使用すると、
- 他の町村の住民にとってはなじみが薄くなってしまい、不公平感を抱かせてしまう
という可能性があります。
そこで、ひらがな表記にすることで、
- どの町村出身の住民にとっても親しみやすく、公平な印象を与えることができる
というわけです。
その他の「ひらがなの市名」
他にも、たとえば、
- 茨城県の「かすみがうら市」
- 栃木県の「さくら市」
などが、ひらがな表記の市町村名として挙げられます。もちろん、
- 埼玉県の県庁所在地である、さいたま市
も有名です。
このように、2000年代になってからの市町村の合併においては、ひらがなの名前が、その市や町のイメージ戦略にとって、とても重要な役割をもつようになっているのですね。
岩宿遺跡で「露出」していた関東ローム層とは?
岩宿遺跡において、赤い土が露出していた「関東ローム層」とは、関東平野の広い台地や丘などを覆いつくしているという、赤褐色の火山灰が積もってできた地層のことです。
すなわち、この「関東ローム層」は、日本を代表する大きな火山である
- 箱根山
- 富士山
などが活発に噴火したときに、ドバッと噴き出してきた、大量の火山灰によってできているのです!
関東ローム層は、火山灰が降り積もってできたもの
したがって、
- 噴火のときに噴き出してきた火山灰が、
- 今の関東平野にどんどん降り積もってゆき、
- 長年にわたって、雨や風などで削られて風化してゆき
- それが、長い時間をかけてできたもの
が、この関東ローム層なのです。
したがって、
- 私たちが住んでいる関東地方の地面の下に、そういった大昔の火山の活動の跡が残っている
ということを考えると、とてもロマンを感じますね。
考古学とは?
ちなみに、相沢忠洋さんがあまりにも熱中した考古学とは、一体どんな学問なのでしょうか。
これは、まるで
だと考えると、とても分かりやすいかもしれません。
すなわち、昔の人たちが残した、
- 土の中に埋もれている道具
- 古い建物の跡
- 壊れた焼き物のかけら
などといった、昔の人々が使っていた物モノ・根拠を、地面から丁寧に掘り起こしていくわけです。
そして、これらの発見されたモノ・根拠などから、
について調べる学問なのです。
こうした「昔の人々の生活がわかる」という発見は、まるでタイムマシンで昔に移動できたような感覚に陥ってしまうため、相沢忠洋さんはハマりまくっていたわけですね。
考古学は、歴史を証明するための、大切な学問
ちなみに私たちが学校や教科書で学ぶ歴史の多くは、昔の人が書いた「文字の記録」から分かっているわけです。
したがって、
- 文字が無かった、大昔の時代
- 文字があっても記録が残っていないような、本当の歴史
を詳しく知るためには、この考古学が、とても大切な役割をもっています。
例えば、土の中から、ひとつひとつの証拠を丁寧に掘り起こしていくといった、なんとも地道な作業は、まるで宝探しのようであり、ロマンのある学問なのです。
すなわち、相沢忠洋さんのような、好奇心・探求心のカタマリのような人は、この考古学の発掘作業にハマらない理由が無いわけです。
きっと彼は、穴を掘っては素晴らしい発見をするたびに、彼の頭の中は凄まじいドーパミンで満たされていたのでしょう。
旧石器時代の存在を証明
そして、相沢忠洋さんが岩宿遺跡で石器を発見する前は、それまでの日本では、縄文時代よりも以前の文化の存在は、否定されていました。
つまり、彼が出てくるまでは、
とまで考えられていたのです。
現在では考えられないことですよね。
日本の歴史は、縄文時代よりも前の昔から始まっていた!
しかし、相沢忠洋さんの存在によって岩宿遺跡で発見された石器のおかげで、なんと約3万年前から、日本に『旧石器時代』の人々が住んでいたことが、明らかになったのでした。
すなわち、これまでの常識だった
という従来の考え方を、相沢忠洋のさんの発見が、見事にひっくり返してくれたのでした。
したがって、岩宿遺跡の発見は、日本の考古学の研究に、まったく新しい見方をもたらしてくれたという、とても素晴らしい出来事だったのです。
相沢忠洋の歴史を、さらに詳しく
元々は民間の商売人だった、相沢忠洋
先述の通り、相沢忠洋さんは、プロの考古学者でも学者さんでもなく、元々は民間の商売人にすぎませんでした。
つまり相沢忠洋は、もともと納豆などを売って生計を立てていくという、アマチュアの考古学者にすぎませんでした。
彼は、大好きな穴掘りをしながらでも生計を立てるために、納豆などの行商をして、食いつないでいました。
これは普通の人では、到底できるものではありません。
何より周りから反対されちゃいますよね・・・。
しかしそんな周囲のアウェー感よりも、彼の考古学への情熱の方が、圧倒的に上回っていたのです。
考古学への情熱
このように、好奇心がとても旺盛だった彼は、考古学に対してとても強い関心・情熱を持っていたのでした。
そのため、発掘に集中するために会社員のような定職に就くことはしませんでした。
その代わり、先述の通り納豆を売りながら、その商売の合間に、遺跡の発掘調査を行っていたのでした。
「素人」というだけで全く相手にされなかった
しかし、相沢忠洋さんは、最初は学者たちから、全然相手にしてもらえませんでした。
今でもそうですが、 当時は学者以外のアマチュアの言うことは信じないという風潮が強かったからです。
つまり、YouTubeがある現代のように、
という時代では無かったわけです。
つまり、当時は極端な言い方をすると、
- たとえ才能があったとしても、学者ではない、素人というだけで認めてもらえない
という時代だったわけです。
相沢忠洋さんは、遺跡の発見をエラい人たちに説明するために、栃木県の桐生から東京までの長距離を、はるか自転車で行き来したといいます。
なんという行動力でしょうか。
このように、相沢忠洋の生涯は、学歴という既成概念の壁と戦いながらも、最終的にはその壁を、自らの手で打ち破ったという、不屈の精神の物語なのです。
相沢忠洋は、いかにして大発見をしたのか
独学で学ぶ
相沢忠洋さんは、まず小学校を卒業してからは、そこからは学校には行かずに、一人で独学で考古学を学んでいました。
しかし当時の日本では、大学まで進学・卒業をして勉強をした、「エラい学者さん」が主流だったのでした。
そのため、相沢さんのように、一人で勉強している人は信頼性がなく、バカにされたりして、ほとんど相手にされなかったのです。
「素人の勘違いだ!」と、誰にも信じてもらえなかった発見
したがって、彼が毎日毎日熱心に、岩宿で一生懸命に掘りあて、石器を見つけたときも、たくさんの学者さんからは、
- 「そんなはずはない」
- 「素人の間違いだ」
などと言われてしまい、残念ながら誰からも、全く信じてもらえませんでした。
なぜなら、彼に「学歴」というものがなかったからです。
つまり、当時は何よりも
- 学歴があること
- 専門家であること
が最重要であり、相沢忠洋さんのような納豆を売りながら個人で掘り続けた人の発見は、誰からもまともに相手にされなかったのでした。
孤独な熱心までの探求が、常識を覆した
誰にも理解されず、一人ぼっちで、孤独な日々を送っていた相沢さん。
しかし彼は誰よりも考古学が大好きで、とにかく熱心に、毎日毎日穴を掘り続けたのでした。
それでも彼は、ただひたすらに自分「信念」だけを信じて、同じ場所をずーっと、延々と何度も何度も掘り続けました。
これは、まず普通の人にはできることではありません。
よほどの熱意・熱量がないと、到底できることではないのです。
その熱意は、やがて、
という、動かぬ証拠へとつながっていきました。
1949年 ついに、岩宿での彼の発見が、学者の中で認められる
何度も何度も、学者さんたちから否定され、笑われても、決して諦めなかった相沢さん。
しかし1949年、あるときに彼に理解ある学者さんに才能を見いだされ、ようやく彼の発見は世間的に認められるようになったのでした。
彼の「諦めない心」こそが、日本の歴史の常識をひっくり返すほどの、偉大な発見につながったのですね!
大切なのは、「熱意」と「努力」
したがって、相沢さんの人生は、私たちに、
ということを、教えてくれているように思います。
おわりに・岩宿遺跡まとめ
相沢忠洋さんの、当時の学者からまったく信じてもらえなかった苦労と、それでも情熱を失わなかった姿勢に触れて、いかがだったでしょうか。
彼の生涯のストーリーは、
を教えてくれますね。
この歴史的背景を知ることで、岩宿遺跡そのものが、単なる石器が発見された場所ではなく、
- 一人の情熱的な人物が、歴史を動かした舞台
なのだと感じられるはずです。
この学びが、あなたの今後の探訪を、より豊かなものにしてくれることを願っています!

コメント