金沢城と金沢の名物・歴史について、わかりやすく解説してゆきます!
観光・歴史に詳しくない方にも、やさしく解説してゆきます!

金沢城・橋爪門(石川県金沢市)
はじめに

「ようこそ金沢へ」(金沢駅前)石川県金沢市
今回は、石川県の金沢について学んでいきましょう!
金沢は、江戸時代に加賀藩を治めていた前田氏が、文化や学問をとても大切にしたことで栄えた街です。
金沢の文化を語る上で欠かせないのが、能楽の流派(つまり、金沢版の能楽)である加賀宝生ですね。
また、
- なんと全国の98%以上を生産しているというピッカピカの金箔
- さらには江戸時代から伝わる美しい着物で有名な加賀友禅
なども、かつての加賀藩(つまり、金沢市の前身)リーダーであった前田氏が大切に育んできた伝統工芸なわけです。
これらの歴史や名物を知ることで、金沢での観光や旅行が、きっともっと面白くなりますよ!
金沢城(加賀藩)前田家を中心に栄えた、金沢
「ラブライブ!」と金沢の、意外な関係とは!?
かつて江戸時代は加賀藩といい、またその太古の昔は加賀国の中心地として栄えてきた、前田家を中心にえた、石川県金沢市。
この金沢が、実は、
という人気アニメの舞台になっているっていうことを、ご存知でしたか?
ラブライブ!シリーズ「蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」の舞台に
ここで、「ラブライブ!蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」とは、
- スクールアイドル活動を目的とした、架空の女子高生グループ
- また、彼女たちのキャラクターの声を演じる声優達による、実在する11人の女子からなる、女性声優ユニット
になります。
このアニメは、石川県金沢市に(しかも、かなりの山奥)あるという、架空の私立高校である、
- 蓮ノ空女学院
を舞台に活動する、スクールアイドルのグループである、
- 「蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」
の11人を主人公としています。
「聖地巡礼」で、金沢の街を探訪しよう
このように、「ラブライブ!」の舞台になった場所は、いわゆる「聖地」と呼ばれています。
その聖地には、ファンのみなさんが、実際にその場所を訪れるという、いわゆる
- 「聖地巡礼」
と呼ばれている行為が、とても盛んに行われています。
すなわち、この「ラブライブ!蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」にも、
- 金沢駅周辺
- 近江町市場
などといった金沢の名所・ランドマークの数々が登場しているため、ファンにとってはたまらない場所となっているわけです。
そもそも「ラブライブ!」シリーズとは?
ところで、この「ラブライブ!」シリーズは、いわゆる「スクールアイドル」という、架空の女子高生グループが主人公の物語です。
その「スクールアイドル」の目的は、おおよそ
- 学校の知名度を上げる
- それにより、少子化にともなう「廃校」のピンチから、学校を救う
といったものとなっています。
また、彼女たちのキャラクターの声を演じる声優さんたちが、現実でもアイドル活動をしているというのも、このシリーズの大きな特徴となっているわけです。
したがって、これまでのシリーズには、
- 2013年…「ラブライブ!(初代)」グループ名:μ’s(ミューズ)舞台は、東京の秋葉原
- 2015年…「ラブライブ!サンシャイン!!」グループ名:Aqours(アクア):舞台は、静岡県の沼津市
- 2020年…虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会(作品名・グループ名ともにほぼ同じ):舞台は、東京のお台場
- 2023年…「ラブライブ!スーパースター!!」グループ名:Liella!(リエラ):舞台は、東京の渋谷区
といった、様々な場所が、アニメの聖地・舞台として登場しているわけです。
また、「ラブライブ!蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」の動画である
- 「おいでよ!石川大観光」
という曲は、石川の観光・歴史を学ぶ上でも、とても勉強になり役立ちます。
金沢駅前の鼓門
金沢のシンボル!鼓門(つづみもん)とは?
金沢駅の前に、まるで太鼓のような形をした、とても立派な門があるのを、よくご存知ですよね。
これは「鼓門」といって、金沢の顔ともいえるランドマークなのです。
この鼓門は、なんと高さが13.7メートルもあります!
ランドマークとは?
ここで、ランドマークとは、その場所を代表する、シンボルのような建物や目印のことです。
例えば、東京なら東京タワーやスカイツリーのように、
と、みんながすぐに思い浮かべるような存在のことを、ランドマークと呼ぶわけです。
したがって、金沢駅の「鼓門」は、金沢の顔とも言える、大切なランドマークというわけです。
能楽と鼓門の関係
またこの鼓門は、
- 能楽
という日本ならではの伝統芸能で使われる、まさに「鼓」という楽器をイメージして作られています。
能楽とは?日本最古の舞台芸術
ちなみに「能楽」とは、約650年にもおよぶ長い歴史を持つ、とても古い日本ならではの伝統芸能です。
すなわち、
- お面をつけた登場人物が、
- 歌や踊り、そして楽器の演奏に合わせて、
- 物語を表現する
といった、世界でも珍しい『舞台芸術』になります。
「加賀宝生」は、金沢の特別な伝統芸能!
そしてここ石川県、特に金沢市では、昔からこの能楽が、とても盛んな地域でした。
理由は、加賀藩のリーダー・前田氏が、この能楽をゴリ推ししてサポートしてきたからです。
金沢では、中でも特に「加賀宝生」と呼ばれる、金沢独自の能楽が発展しました。
金沢で能楽が盛んな、意外な理由
では、なぜ金沢で能楽が、こんなにも盛んになったのでしょうか。
それは、
- 江戸時代に金沢を治めていた前田家が、能楽をとても大切にしていた
ことが、その理由なのです。
したがって、前田家は、能楽を武士たちの「たしなみ」として、熱心に広めていきました。
つまり、武士にとってためになるから、藩を挙げてこの能楽を推奨・奨励していたのです。
すなわち、能楽は、武士たちの精神を鍛えるための、大切な文化でもあったのですね。
プロだけでなく、武士や商人にも浸透していた金沢の能楽
前田氏がこの能楽をゴリ推し・推奨したおかげで、金沢では、プロの演者だけでなく、一般的な武士や商人たちも、この能楽を楽しむようになりました。
そして金沢は、日本全国の中でも、特に能楽が盛んでよく知られる地域へと発展していったのでした。
藩のリーダー・前田家によって手厚くサポート・ゴリ推しされた、加賀宝生
先述の通り、加賀藩をトップとした治めていた前田家とよばれるお殿様の一族は、まさにこの加賀宝生をとても大切にし、さらには色んな人々に奨励していました。
特に、後述する、特に前田氏の歴史の中でも評価の高い、4代藩主の前田綱紀さんは、この金沢ならではの「宝生流」の能楽を、加賀藩全体で広めるように勧めていったのでした。
「鼓門」は、地域の無形文化財をイメージ!
前置きが長くなりましたが、ラブライブ!「蓮ノ空」でも登場する、金沢駅前にあるこのでっかい「鼓門」は、先述の江戸時代の金沢で流行った能楽である「加賀宝生」で使われる楽器である鼓を、まさにそのデザインに取り入れているというわけです。
北陸地方でもっとも人が集まる場所である金沢駅のすぐ目の前に、こうした「能楽」の賜物を持ってくるわけですから、金沢にとって「能楽」の存在がいかに重要だったか、というのが非常によく理解できます。
すなわち、金沢駅の鼓門は、地域の特別な文化財を、「門」という形で表現しているわけですね。
したがって、この能楽の金沢バージョンである「加賀宝生(かがほうしょう)」は、今は金沢市が指定している「無形文化財」にもなっているというわけです。
能楽にはいわゆる「形がない」ため、無形文化財にカテゴライズされているというわけですね。
一方、もし陶磁器みたいに形があれば、有形文化財です。
また、文化財の指定は、国だけではなく、都道府県や市町村単位でも行っている、というわけでもあります。
「加賀百万石」の城下町、金沢
金沢の街は、江戸時代に、いわゆる
- 「加賀百万石」
とも呼ばれた加賀藩の城下町として、とても栄えていました。
つまり、この「加賀百万石」という呼び名は、石高すなわちお米の生産量が、なんと102万5千石もあったことから来ています。

金沢城(石川県金沢市)
ちなみに、
- 2位の薩摩藩(鹿児島県)は、約76万石
- 3位の仙台藩(宮城県)は、約62万石
- 全国の主要な藩は、だいたい20万石~30万石もあれば、かなり多い方
- むしろ大半の大名は、せいぜい数万石くらい(下手したら、むしろそれ以下)しか持てなかった
といったことを考えると、加賀藩の百万石というのが、いかに突出して多かったかがわかります。
加賀百万石について詳しくは、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。
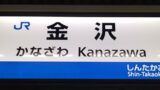
したがって、これは徳川幕府に次ぐ、全国の大名の中でも、一番大きな石高だったということなのです。
加賀藩主・前田家でも特に重要な「利家」「綱紀」

金沢城・石川門(石川県金沢市)
加賀藩の歴代藩主・前田氏の中で、特に重要な人物といえば、やはり
- 前田利家(初代)
- 前田綱紀(5代目。加賀藩主としては4代目)
の二人ですよね!
この二人は紛れもない、加賀藩の絶対的エースです(※この言い方、わかる方います?)。
つまり、それぞれ違う形で、加賀藩の歴史に大きな影響を与えたというわけです。
前田利家(初代藩主): 加賀藩の「創業者」
「百万石の大名」としてあまりにも名高い前田利家さんは、まさにこの加賀藩を、ゼロから立ち上げたという、とても偉大な人物です。
彼はまだ戦国時代だった頃に、豊臣秀吉の家臣(部下)として、秀吉の天下統一をしっかりサポートし、戦乱の世を力強く生き抜きました。
そして、秀吉からその功績が認められたことより、加賀国(つまり、いまの石川県)という大きな領地をもらうことになりました。
そして、そこからまさしく加賀藩の基盤を築きあげたわけです。
そして、秀吉が亡くなった後も、その息子・後継者を補佐する重要なポジションである五大老(※)の一人として徳川家康と渡り合い、また徳川家との関係もよい感じに保つことで、加賀藩を守り抜きました。
その結果、「百万石」という日本一の領地を維持したわけです。
※五大老とは、豊臣秀吉の死後、その後継者である幼い豊臣秀頼を補佐するために設けられた、最高意思決定機関の名称でした。
このメンバーは、
- 徳川家康
- 前田利家
- 毛利輝元
- 上杉景勝
- 宇喜多秀家
という5人の大大名(つまり、大名の中でも特にスゴい人たち)でした。
つまり、徳川家康と前田利家は、この当時はなんと同じ地位だったわけです!スゴいですね。
前田利家は、藩主(藩のリーダー)としての期間は短かったですが、その後の加賀藩の繁栄は、まさに彼が築いた土台があってこそのものだった、というわけです。
したがって、彼は「藩祖」として、石川県・金沢では特別な存在(むしろ英雄)とされています。
前田 綱紀(第5代藩主): 加賀藩の「黄金時代を築いた名君」
前田綱紀は、約78年という、ほぼ一世紀にも及ぶような驚くほど長い期間、藩主(藩のリーダー。知事や市長のようなもの)を務めました。
すなわち、加賀藩の政治を安定させ、平和な時代を築いたわけです。
彼の最大の功績は、武道よりもむしろ勉強・学問を優先する、「文治政治」を進めたことでしょう。
文治政治とは、武力ではなく、学問や文化を重視して、国を治めることです。
彼は、藩校「明倫堂」の前身となる学問所を整備し、全国から優秀な学者を招きました。
その結果、この時代に
- 加賀友禅
- 九谷焼
- 加賀蒔絵
といった、金沢ならではの工芸品が大きく開花したのでした。
また、茶道や能楽といった文化も大いに発展しました。
こうした文化的な繁栄が、いまでも語り継がれる「加賀百万石」のイメージをさらに決定づけたわけです。
すなわち、すごく優雅な時代だったんだろうな、ということが想像できます。
また、彼は治水事業や新しい田んぼの開発にも力を入れ、財政の基盤も固めました。
なぜ、この二人を特に知っておくべきなのか?
それは、二人が加賀藩の歴史を象徴しているからです。
- 前田利家: 戦国時代という「荒波」を乗り越え、加賀藩という「器」そのものを創り上げた人物です。
- 前田綱紀: その「器」を、文化や経済、学問でいっぱいに満たし、加賀藩の個性を確立させた人物です。
この二人の功績がなければ、いまに続く加賀百万石の繁栄はなかったでしょう。
したがって、加賀藩の歴史を学ぶなら、まずこの二人から始めるのが一番わかりやすいといえます。
もちろん、この2人以外の他の藩主も金沢のために一生懸命頑張りましたが、それでもやはりこの二人は、まさに加賀藩の「始まり」と「絶頂期」を代表する存在であるというわけです。
大都市「金沢」は、歴史的な街並みが残る街
当時の金沢は、人口の規模でいうと、
- 江戸(東京)
- 大坂(大阪)
- 京(京都)
という、日本のいわゆる三大都市「三都」に次いで、4番目の名古屋と並ぶほどの大都市でした。
また、金沢の街が、第二次世界大戦のときに、アメリカ軍からの空襲を受けなかったことは、とても幸運なことでした。
これにより、昔ながらの歴史的な建物がたくさん残っていて、
- 主計町茶屋街
- ひがし茶屋街
- 長町武家屋敷跡
などといった、歴史を感じさせる素晴らしい風景が、今でもたくさん残っているのです。
金沢市について詳しくは、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

金沢が空襲を受けなかった理由
なぜ、金沢は空襲の被害に遭わなかったのでしょうか。
米軍の資料によると、当時の金沢は、軍事的な戦略価値が低いと判断されたため、空襲の対象から外されたようですね。
金沢には、当時「第九師団」という日本陸軍の部隊が置かれていました。
しかし、この部隊は台湾に駐留しており、ほとんど兵力が不在だったのです。
したがって、軍事的な重要性が低いと判断されたのかもしれません。
第九師団とは何か?について詳しくは、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

世界的にも人気の観光都市、金沢
実は金沢は、アメリカ人をはじめとする外国の方々にも大人気の観光地でもあります。
特に、歴史的な街並みや文化、そして現代アートとの融合が、多くの外国人観光客を惹きつけています。
すなわち、以下のような場所が、人気の観光スポットとして知られているわけです。
- 兼六園
- ひがし茶屋街
- 金沢21世紀美術館
やはり、これだけ魅力的な街並みが残っているからこそ、金沢のファンは世界中に多いのかもしれませんね。
金沢城は、どんなお城なのか?
加賀藩の政治の拠点となった金沢城は、石川県の金沢市にあるお城です。
金沢城の始まりと前田家
金沢城は、もともと金沢御堂というお寺があった場所に、そのお城が築かれることになりました。
しかし戦国時代、このお寺が焼失してしまった後に、織田信長の家臣(部下)であった佐久間盛政が、このお寺が存在していた場所に、金沢城の原型となるお城を建て始めたわけです。
「賤ヶ岳の戦い」で、佐久間盛政(勝家側)の敗北、前田利家(秀吉側)の勝利
そして、その主君・ボスである織田信長が本能寺の変で敗れたのでした。
その後、その信長が持っていた土地を争って、賤ヶ岳の戦いでという争いが勃発したのでした。
この戦いは、
- 柴田勝家
- 豊臣秀吉
という、かつてどちらも信長の部下だった者同士が、天下をかけて、現在の琵琶湖の北あたりで戦いました。
この戦いにおいて、先述の金沢の佐久間盛政は、柴田勝家の家臣として大活躍しました。
しかし戦いの途中で、元々は柴田側だった前田利家が秀吉側に寝返り、戦場から離脱してしまったのでした。
佐久間盛政はそれでも秀吉を追い詰めるほど奮戦しましたが、秀吉軍に敗れて捕らえられてしまい、その後処刑されてしまいました。
佐久間盛政とは?
佐久間盛政は、戦国時代の武将です。
鬼玄蕃という恐ろしい異名を持つほど、その武勇にはとても優れていました。
前田家以前に、初期の金沢城を建て始めた一人でもありました。
先述の通り、織田信長・柴田勝家の家臣(部下)として活躍し、特に賤ヶ岳の戦いでは、大将の秀吉を追い詰めるなど、その強さを見せつけた人物です。
賤ヶ岳の戦いとは?
賤ヶ岳の戦いは、1583年に起こった、天下の行方を決める重要な戦いです。
織田信長が亡くなった後、その後継者の地位を巡って、家臣(部下)だった
- 柴田勝家
- 豊臣秀吉
の二者で激突しました。
この戦いで秀吉が勝利したことで、天下統一へ大きく近づいたわけです。
賤ヶ岳の戦いについては、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

柴田勝家とは
柴田勝家は、かつては織田信長に仕えていた武将でした。これは秀吉も同じでした。
鬼柴田(鬼の柴田)と呼ばれるほど、戦場では特に勇猛果敢でした。
信長の死後、その残された領地をめぐって、同じ部下だった豊臣秀吉と対立してしまい、天下を争いました。
しかし、賤ヶ岳の戦いで敗れ、悲しいことに妻と燃え上がる福井城の中で自害してしまいました。
柴田勝家の最期については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

金沢城の始まり
豊臣秀吉は、戦場で前田利家が味方になったことや、長年の友情(盟友関係)を評価しました。
したがって、前田利家は元々佐久間盛政が治めていた領地を、秀吉から受け取ることになります。
すなわち、この領地の中に、佐久間盛政が築き始めた金沢城(当時は尾山城と呼ばれていました)があったというわけです。
このように、賤ヶ岳の戦いでの利家の行動が、金沢城が前田家の拠点となる、大きなきっかけになったのですね。
百万石の礎
その後、前田利家が金沢城に入ると、本格的な城郭が築かれてゆきました。
前田家は、このお城を拠点に、加賀百万石の礎を築き上げたというわけです。
前田利家は、江戸時代が始まる少し前の1592年から、金沢城を作り直す工事を始めました。
そして、以下のような大規模な工事を行ったのです。
- お城のまわりにある曲輪や堀を広げ、城をよりバージョンアップしました(曲輪は、お城の中にあるエリアのことです)。
- 5階建てのビッグな天守を建てました。
- 櫓という、敵をよく見渡せる物見やぐらのような建物を、たくさん建てました。
兼六園が生まれた背景
兼六園は、加賀藩の4番目の殿様である前田綱紀が、お城のそばに作った「蓮池庭」という庭園が元になっています。
兼六園は、
- 茨城県水戸市の偕楽園
- 岡山県岡山市の後楽園
とともに、日本三大庭園の一つとされています。
兼六園について詳しくは、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

強大な力を持った加賀藩
金沢城を拠点にしていた加賀藩の殿様・リーダーである前田家は、「外様大名」という、もともと徳川家と関係がなかった家柄でした。
しかし、徳川家との結婚などを通して、とても強い関係になったのです。
そのため、
- 徳川家とも関わりが深い、松平という「名乗るだけで身分が高いことを示す」苗字
- 徳川家の印である、葵紋
もらうことができました。
(葵紋は、徳川家の家紋のことです。)
「葵紋」とは、水戸黄門の「アレ」
ちなみに、水戸黄門の有名なセリフである
という紋所とは、徳川家のシンボルの紋章である、葵紋のことです。
つまり、徳川家の
- 「三つ葉葵の紋」
ですね。
この紋所つまり葵紋を持ってると、それだけで徳川家に関係ある「偉い人」であることを示すことができ、周りの人々は一瞬でひれ伏(ふ)したわけです。
そんなスゴい「シンボル」を、加賀藩は持つことができたわけです。
徳川将軍の名前を一部もらうことができた加賀藩・前田家
前田家は、3番目の加賀藩の殿様である光高からは、将軍の名前の一部(この場合は、徳川家光の「光」)をもらうことができるようになったのでした。
昔は、偉大な先祖などから「一文字」名前をもらうことはとても名誉だったので、これは前田家にとってもとても名誉なことだったでしょう。
ここまで紹介した前田綱紀の「綱」も、江戸幕府4代将軍・徳川家綱からもらったものです。
こうして加賀藩は、全国の大名の中で一番大きい、100万石という広大な土地を治める藩として君臨し続けていたのでした。
金沢の名物
名産品・金箔の秘密
金沢では、金箔の製造がとても盛わけです。
その理由の一つは、金沢の地が一年を通して雨が多く、湿度が高い気候にあるからなというわけです。
湿気が多いと、静電気が起きにくくなるため、質の良い金箔を作るのには、ぴったりな気候なのです。
さらに、金箔が発展した背景には、
- 加賀友禅
- 輪島塗
といった、昔から伝わる(大量の金箔を必要とする)工芸品がたくさん作られていたことがあります。
これらの工芸品を作るためには、たくさんの金箔が必要だったため、金箔作りがどんどん発展していったのです。
このように金沢は、江戸時代から金箔作りで有名で、その金箔は、輪島塗をはじめ、様々な伝統工芸品に対して使われていったのでした。
そのため、金箔作りは前田氏からのサポートもあり、どんどん盛んになっていったのです。
金箔の意外な事実
金箔は、純粋な金だと思われがちです。
しかし、ほとんどの金箔は、純金というわけではありません。
金箔をより美しく、そして丈夫にするためには、金に、少しだけ銀や銅を加える必要があるわけです。
ただし、とても豪華な飾りにするために、わざと金の量を増やした金箔を作ることもあります。
金沢を代表する伝統工芸、加賀友禅
加賀友禅は、まさに金沢を中心に作られる、着物の色を染める方法(技法)、つまり金沢にしか出来ない誰にもマネ出来ないテクニックです。
このテクニック(技法)れは、いまやとても貴重であるため、国によって伝統工芸品にも指定されているというわけです。
これが石川県によって指定されているのならもちろん理解できますが、国によって指定されているのは、それは我が国にとってそれだけ貴重であることの、何よりの証明になります。
- 京友禅
- 江戸友禅
並んで、「日本三大友禅」の一つとされています。
加賀友禅が持つ独自の特徴
加賀友禅の特徴は、
- 絹の生地に対して、
- 草花や鳥、自然の景色などを、筆で色づけしていく
ことです。
また、この友禅染には、「加賀五彩」と呼ばれる、
- 藍色
- 黄土色
- 草色
- 古代紫色
- 臙脂色
の5つの色が、基本的な色として使われているのも特徴です。
さらに、本物の草花のように見えるように、特殊な技法も使われています。
- 「先ぼかし」:色の濃い部分から、だんだん薄くしていく方法です。
- 「虫食い」:葉っぱが虫に食べられたような表現で、リアリティを出しています。
- 「糸目糊」:筒から絞り出した糊で、絵を描く方法です。
加賀友禅が歩んできた道
加賀藩が応援・サポートしたことで、この加賀友禅はどんどん発展してゆき、江戸時代の中頃には、ついに
- 「加賀のお国染め技法」
として、しっかりとしたものになりました。
つまり、加賀国(昔の石川県・加賀藩の呼び方)といえば友禅染だ!みたいに全国にその名前が知られるほどの地位を確立したわけです。
そして、加賀友禅は、作る人が最初から最後まで、一人で作っていくわけです。
そのため、その人の個性や「手作り感」が作品にもモロに表れてくるのが特徴です。
これは、AIに代替されないスキルです。
すなわち、これはどれだけAI(人工知能)が発展したとても、決して真似できないオリジナリティ・創造性のカタマリというわけですね。
そりゃ、「国が伝統工芸品に指定するのもわかる」って話でしょう。
「弁当忘れても傘忘れるな」とは?
これは、金沢をはじめ雨の多い北陸地方でよく使われる言葉です。
すなわち、
という意味のことわざです。
すなわち、石川県や富山県など、日本海側でよく使われます。
北陸地方は天気が変わりやすく、
からです。
すなわち、突然の雨で困らないように、いつも傘を持ち歩くことの大切さを教えてくれています。
その他、このフレーズは日常生活においても、
という教訓も込められています。
備えあれば憂い無しですね!
金沢観光では、傘を忘れない。けど、お弁当も「心」も忘れたくない。
金沢観光では、傘が必須アイテムです!
先述の通り、金沢は
- 「弁当忘れても傘忘れるな」
という言葉があるくらい、天気が変わりやすい街です。
すなわち、突然の雨でも、傘があれば安心して観光できますからね。
しかし、お弁当も忘れないようにしたいものです。
もちろん、お弁当を忘れても、金沢には近江町市場やひがし茶屋街など、おいしい食べ物がたくさんあります。
なので、たとえお弁当を忘れても、
- 美味しいものを楽しむ心
- 旅を楽しむ心
- 歴史を学ぶ心
も忘れないようにしたいものですね!
おわりに・まとめ
金沢の観光・名物・歴史を学んでみて、いかがでしたか?
前田氏が築き上げた文化が、今も街のあちこちに息づいているのが分かっていただけたのではないでしょうか。
本文でも紹介した加賀宝生が盛んだったことや、金箔や加賀友禅といった伝統工芸が発達したのも、全て金沢の歴史と深く結びついています。
すなわち、これらの背景を知ることで、街を歩くだけでも、その奥深さが感じられるはずです。
ぜひ、ここで学んだことを活かして、金沢での探訪を楽しんでくださいね!

コメント