伊豆・大仁の鉄道旅と、長嶋茂雄という偉人のスゴさ・激動の生涯について、わかりやすく解説してゆきます!

長嶋茂雄さんがかつて現役世代に自主トレをしていた、伊豆・大仁の景色(静岡県伊豆の国市)
はじめに:長嶋茂雄のスゴさと、熱い生涯を学ぶ!
さて、今回は長嶋茂雄という偉人の波乱に満ちた生涯を、一緒にじっくりと学んでいきましょう!
すなわち、彼の情熱的な野球人生を知ることで、ミスターへの理解が深まります。
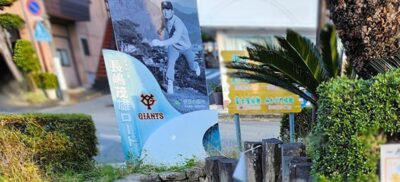
長嶋茂雄さんは現役時代、自主トレーニングで大仁に滞在された(静岡県伊豆の国市)
この学びは、長嶋さんゆかりの地である伊豆・大仁を観光したり、旅行や探訪をする際に、大きな喜びと面白さを加えてくれますよ!
聖地を訪れる感動を何倍にも高めるために、ぜひ知識を深めていきましょう。ワクワクしますね!
長嶋茂雄さんと伊豆・大仁の関係

長嶋茂雄さんがかつて現役世代に自主トレをしていた、伊豆・大仁の景色(静岡県伊豆の国市)
静岡県の伊豆・大仁は、長嶋茂雄さんにとってプロ野球人生の始まりと言える、非常にゆかりの深い場所です。
すなわち、巨人軍の大仁グラウンド(現在の大仁ホテル付近)で、新人時代から厳しい練習に打ち込みました。

伊豆・大仁駅からの景色(静岡県伊豆の国市)
また、何十年ぶりに長嶋さんが大仁を訪れたときは、大仁の人々は「お帰りなさい」と迎え入れたそうです。
心あたたまるエピソードですね!
したがって、この地は長嶋さんの熱い野球人生の原点なのです。
長嶋茂雄さんの死去と、語り継がれる栄光
長嶋茂雄さんは、2025年6月3日の午前6時39分に、ご逝去されました。
すなわち、89歳でその波乱に満ちた生涯を閉じられました。
長きにわたり、プロ野球界を牽引し、熱狂的な感動を与え続けた偉大な功績は、永遠に不滅です。
私たちファンにとって、ミスターの情熱的なプレーと明るい笑顔は、かけがえのない宝物ですね!
伊豆・大仁へのアクセス
伊豆・大仁(静岡県伊豆の国市)へのアクセスは、主に鉄道と車が便利です。
まず、鉄道の場合は、
- 東海道新幹線または東海道線で三島駅(静岡県三島市)で行き、
- そこから伊豆箱根鉄道・駿豆線に乗り換え、
- 南の修善寺方面へ約30分ほど進み、
- 大仁駅で下車
します。
したがって、東京方面からも比較的スムーズに移動できます。
伊豆・大仁の観光や歴史については、以下の前回の記事でも解説していますので、ご覧ください。

長嶋茂雄さんは、何がすごかったのか?
数多くの名ドラマ・名シーンを、国民の脳裏に焼き付けた
現代に生きる多くの人は、
- 長嶋茂雄ってよく聞くけど、ぶっちゃけ何がすごいの?
って思う人も多いかもしれません。
この数字だけを見れば、確かに正直あまりスゴいとは思えないでしょう。
もちろんこの数字も、普通の選手には打てないほどスゴいのですが、やはり通算500本以上打った人が他にもいることを考えると、確かにちょっと見劣りする数字ではありますよね。
しかしそれもそのはず、
というわけです。
なぜなら、長嶋さんの魅力は、
- 数字では図ることのできない、数多くの名ドラマ・劇的なシーンを、当時の現役世代を知る多くの国民の心に焼き付けた
ことにあるからです。
国民に「プロ野球」という娯楽を定着させた
長嶋茂雄さんが登場するまで、日本のプロ野球の人気は、決して高くはありませんでした。
それよりも、むしろ大学野球、特に東京六大学野球が熱狂的な人気を博していました。
長嶋さんが立教大学において、輝かしい活躍を見せた後、1958年に読売ジャイアンツに入団したことで、プロ野球の人気が爆発的に高まりました。
長嶋茂雄さんは、それまで評価の低かったプロ野球を、国民的スポーツとして定着させました。
長嶋茂雄さんの経歴を簡単に紹介
佐倉市での出身エピソード
長嶋茂雄さんはまだ日本は戦前にあたる1936年2月20日に、現在の千葉県佐倉市において生まれています。
すなわち、少年時代の野球の原点がこの地にあったと言えます。
どんな幼少期だった?
長嶋茂雄さんの幼少期は、スポーツに夢中な活発な少年でした。
佐倉市の自然の中で育ち、野球だけでなく、水泳や相撲など、様々な運動において、まるで天才的・神の申し子のような天性の才能を見せていたそうです。
すなわち、長嶋さんの持つ驚異的な運動能力は、この頃から培われていったのでしょう。
お父さんが野球好きだった影響もあり、自然と野球に打ち込むようになってゆきました。
負けず嫌いで明るい性格は、この幼少期に形成されていったと言われています。
ミスターのエネルギッシュな原点ですね!
プロの誘いを断り、学問との両立のため立教大学進学へ
地元の佐倉一高(現在の佐倉高校)時代には、すでに抜群の野球センスを発揮していました。
特に、高校卒業時にも既に巨人からのプロ入団の誘いがありましたが、
- 「大学でしっかり勉強したい」
- 「野球と学問を両立したい」
と断り、立教大学に進学したという真面目なエピソードも残っています。
ミスターの誠実さがうかがえますね。
大学を沸かせた後、デビュー
長嶋さんは大学卒業後、1958年(昭和33年)に読売ジャイアンツ(巨人)に入団すると新人ながら首位打者・打点王を獲得したのでした。
このように、規格外の活躍を見せました。
1958年・1959年の活躍について
長嶋茂雄さんは、1958年(昭和33年)に、たくさん活躍し伝説を残した立教大学から、巨人(栄光ある巨人軍)へ入団しました。
それは戦後13年、日本が敗戦と荒廃のショックから、まさに立ち上がろうとしていた時代でした。
この当時は「もはや戦後ではない」という言葉も飛び交ったような時代であり、新たな日本の高度経済成長期への幕開けへの時代とともに、長嶋茂雄さんの伝説・栄光あるプロ野球人生が、まさにスタートしたというわけです。
ルーキーイヤー(1958年)大活躍!しかし「一塁を踏み忘れる」大失態も
このデビューとなった1958年は、ホームランをいきなり29本を打つという大活躍をしました。
しかし、1本だけ一塁を踏み忘れるという大失態をおかしてしまい、この時のホームランは取り消されてしまったのでした。
つまり、この「一塁踏み忘れ」がなければ、デビュー(ルーキー)年に30本という偉業を達成できていたわけです。
なんとも惜しいというか、まさに天然ボケのミスターらしいエピソードですね。
1959年 伝説の天覧試合 天皇陛下の前で感動の劇的ホームラン!
天覧試合となった1959年の阪神戦では、なんと夜の9時を過ぎた最後の最後で、サヨナラホームランを放ちました。
天覧試合:天皇陛下が観戦される武道やスポーツの試合をいいます。
この日本国民全員を熱狂に包んだドラマチックなホームランにより、長嶋さんは国民的な人気を確立しました。
4ー4の同点で迎えた9回のウラ、もはや試合が夜の9時を過ぎており、天皇陛下も(事前に決められていた)21時15分のお帰りの時間が近づいてきたところでした。
しかし、陛下もいよいよ帰られようとされていた、そのわずか直前の21時12分。
長嶋茂雄選手が、最後の最後で奇跡的なホームランを打ったのでした。
客席はもちろん、大拍手・大喝采。まさに、
- 「そんなことある!?」
- 「そんなドラマあるの!?」
と思わず笑ってしまいそうな、あまりにも劇的・感動的なホームランだったのです。
しかもそれまでの2試合は無安打という不調でしたが、この日はなぜか大ホームラン。
というのが、まさにミスターだったのでした。
この日本国民全員を感動の渦に包み込んだ出来事は、プロ野球が国民的スポーツへと発展する、大きな転機となりました。
国民的スポーツへの発展
このように、長嶋さんの天覧試合の成功は、プロ野球への国民の注目度をとても大きく高めることになりました。
そのため、プロ野球を日本の「国民的娯楽」へと発展させる、大きなきっかけとなりました。
1958年・1959年は、ルーキーイヤーから2年連続で本塁打王・打点王を獲得するなどという、まさにスター選手の誕生でした。
1960年代の活躍
日本の高度経済成長期にあたる1960年代は、長嶋さんがまさに絶頂期として、またV9時代の中心選手として、大活躍した時期です。
「ON砲」として恐れられる
この時代、王貞治選手と組んだON砲は、球界最強のコンビとして恐れられました。
- 3番 ファースト・王
- 4番 サード・長嶋
つまり、「王が打てば、長嶋が打つ」みたいな感じで、最強の「ON砲」としてこの間、首位打者・本塁打王・打点王、MVPを何度も獲得しました。
そしてなんと、1965年~1973年にかけてなんと9連覇するという、V9の黄金時代を築き上げたのです。
すなわち、球界最高の打者としての地位を確固たるものにしました。
プロ野球を、国民的な「娯楽」に
高度経済成長期にあった1960年代、長嶋茂雄さんと王貞治さんが活躍した時代のプロ野球は、国民的スポーツとして、家族の団らんの中心にありました。
つまり、家族みんなで食卓を囲んで、当時は白黒からカラーへと移行しかけていたテレビで、長嶋さん・王さんの活躍を野球中継で観るのが、当時の国民の理想的な「楽しみ」「幸せのあり方」だったのでした。
まだYouTubeも存在していなかった当時は、今みたいな
みたいな「ソロ活」は、当時は考えられなかったでしょうね・・・。
毎日球場に行っても飽きない、長嶋さんのプレー
長嶋さんのプレーは、毎日見ても決して飽きないような、面白いエンタメ要素満載のプレーが多かったのでした。
特に、
- 「わざと難しく球を取る」など、見る者を絶対に飽きさせない、派手なプレースタイル
- 得点になるシーンなら、たとえクソボールでも打ちにいく、派手なバッティング
- とても明るい・面白い・天然ボケな、「どこか憎めない」キャラクター
- 常にファンのことを考える、全力のファンサービスの姿勢
- 三振するときも、ヘルメットが脱げるほどの大スイング
などの数々は、多くのファンを魅了しました。また、
という比喩表現すらあったほどなのでした。長嶋さんのように「毎日見ても飽きない選手」なんて、なかなかそう多くはいるものではないですよね。
つまり、長嶋さんは、
- 「ここで打てば、ファンは絶対大盛り上がり」
という場面で必ずファンの期待に応えて打っていたので、それもファンを飽きさせない要素の一つだったのでした。
1970年代前半 選手晩年~引退へ
年齢からくる、体力の衰え
しかし、1970年代前半に入ると、年齢からくる体力の衰えに苦しめられるようになってきました。
そして1974年をもって、長嶋茂雄さんは現役を引退することになりました。
体力の衰え 屈辱的なシーンが増えた
長嶋さんは1973年ころから明確な衰えが見え始め、この当時既に37歳と高齢の域となっていました。
また、それまで長嶋さんが務めてきた4番打者の座はすでに王貞治さんに譲っており、長嶋さんは5番を打っていました。
そして極めつけは、
- 相手ピッチャーが、4番・王貞治さんとの勝負を避けて敬遠(意図的なフォアボールを与える)し、
- 不調の5番・長嶋での勝負を突き付けられ、
- 相手の作戦通りに、ダブルプレーを取られる
という、なんとも屈辱的なシーンが目立つようになったのでした。
この時の状況を、長嶋さんは
と語っています。すなわち、打った球が素直に内野ゴロになってしまう、ということを示唆しているわけです。
つまり、もはやこの時点で、長嶋さんにとって思い通りのバッティングは出来なくなっていたことがわかります。
「V9」の夢が破れ去る
1973年までの巨人軍は、1965年の黄金期から9年連続で優勝するという「V9」をなんとか守り続けていました。
しかし、長嶋さん本人はじめ、他の黄金期のメンバーもかなり年齢的に衰えていた1974年には、とうとう優勝を中日ドラゴンズに譲ってしまうこととなってしまいました。
結果的にこの年の巨人は、2位の阪神に次ぐ3位ということとなりました。
すなわち、力ここに及ばず、栄光の10連覇の夢は破れ去ってしまったのでした。
1974年に現役引退へ
長嶋選手の現役最終年となった1974年には、年齢は既に38歳となっていました。
打率は.244、本塁打は22本と、全盛期に比べるとやはり低下しており、その衰えと限界は隠せないものとなっていました。
このように、例えどんなスターであっても、年齢には抗えないのです。それは例えイチローさんであっても、そしておそらく未来の大谷翔平さんであっても。
そう考えると、時の流れは残酷で、寂しいものですよね。
引退試合「我が巨人軍は、永久に不滅です!」
そして、1974年10月14日・後楽園球場において行われた引退試合での
という言葉は、今でも語り継がれる名言となりました。
したがって、引退後も巨人軍の監督として、その情熱は受け継がれていくこととなります。
後楽園球場:1937年から1987年まで、今の東京ドームの近くにあった野球場です。
電光スコアボードや人工芝の導入など、日本の野球の歴史において、常に先進的な役割を担っていました。
しかし1987年、老朽化のため閉鎖され、その役割は東京ドームに引き継がれました。
長嶋さんの凄さは、ホームラン数だけでは語り尽くせない
このように、長嶋茂雄さんは、以下のような大活躍で、とにかくファンを喜ばせ、期待に応えていました。
- ここで打てば得点になる!(もし打たなければ失望・野次覚悟)というシーンで、必ず打っていた
- どんなに不調なときでも、大舞台になると何故か「魔物に取り憑かれたように」打ちまくった
- たとえどんなクソボールでも、打てると思った球なら、天性のカン(=「動物的カン」とも)で打っていた
このように、長嶋さんは例えどんなに不調であったとしても、チャンス・大舞台になると何故か打ちまくるという、謎の天性の強いバッターとして、多くのファンを大熱気に包んでいました。
「野球の神様」「ミスタープロ野球」の称号
そして長嶋茂雄さんには、これまでの栄光が称えられ、
- 野球の神様
- ミスタープロ野球
といった、名誉ある称号が与えられたのでした。
背番号3番は「永久欠番」へ
そして長嶋茂雄さんの背番号「3」は、読売ジャイアンツの永久欠番であり、長嶋さんが不滅の存在であることの象徴となりました。
永久欠番:その選手が使用していた背番号を、その球団では他の選手が永久に使用できないように定めたものです。
これは、選手への敬意と栄光を末永く称えることを目的とした制度です。
1975年以降の長嶋監督
現役引退後の1975年から、長嶋茂雄さんはすぐさま巨人軍の監督に就任しました。
この年からはそれまでの「3」に代わり背番号90を背負っての、新たな船出でした。
しかし、この第1次監督時代は、V9時代の終焉と重なり、なかなか優勝には手が届きませんでした。
いきなり「最下位」「批判」という苦境
監督に就任して初年度、最初はなかなか勝てなかったため、
- 熱過ぎる指導
- 「型破り」「常識破り」で、(味方にすら)予測不能だった采配
は、賛否両論を呼びました。
それでも、長嶋監督は
というとても強い信念のもと、常にファンを魅了する野球を目指しました。
采配:監督が指示や作戦を出し、選手の起用や試合の判断などを行うことを指します。
チームの方向性を決めたりするため、勝敗に直結する責任重大な行為です。
この采配がうまくいかないと、選手の士気にも影響を与えるくらい重要です。
天性の「長嶋采配」のメリット・デメリット
長嶋監督の采配は、非常に型破りで直感的であったため、「天性の采配」と呼ばれました。
もちろんこれは、普通の監督ならばやらない「常識はずれ」なやり方となります。
そのため、当然ながらメリット・デメリットと、賛否両論がありました。
長嶋采配の「メリット」
メリットとしては、常識にとらわれない大胆な決断が試合の流れを一気に変え、ファンを熱狂させることが挙げられます。
すなわち、誰も予想できない一打を呼び込む力がありました。
相手チームからすれば、
- 「いつ何を仕掛けてくるかわからない」
- 「長嶋さんは何を考えてるのかわからない」
みたいな感じで、文字通り予測不可能な采配だったため、中には長嶋采配を苦手としていたチームや監督は多かったでしょう。
長嶋采配の「デメリット」
一方、長嶋采配のデメリットとしては、データや理論などに基づいた「客観的野球」ではないため、失敗したときには批判の的になりやすかったことです。
もちろんこうしたやり方だと、理論派の選手とはうまく合わず、長嶋さんの「直感」による采配や指示などに納得いかなかったという選手は多かったことでしょう。
一方、長嶋さんの永遠のライバルだった野村克也監督は、長嶋さんとは全く真逆でガチガチ理論派の「データ野球」だったため、本当に正反対です。
長嶋さんは現役時代から「天性のカン(動物的カンとも)に頼る野球で成功してきた」という成功体験があった部分もあったのでした。
そのため、どうしても野村克也さんとは真逆の「天性野球」になってしまうのは、ある意味仕方なかったことでしょう。
つまり、こうした直感こそが、ミスターの魅力であり、逆に脆さでもあったと言えるでしょう。
1970年代後半 ON砲の衰退、チームの低迷
長嶋さんが1975年から第一次監督に就任した頃は、まさにチームの世代交代の時期でした。
つまり、1960年代の「黄金時代」を支えてきたメンバーは、自身の引退も含めて高齢化により、否が応でも若手選手へのバトンタッチ・世代交代を迫られていた時期だったのでした。
特に、ON砲の一角である王貞治選手も既に35歳を過ぎていてベテランの域に入ってきており、チーム全体としてベテラン選手の高齢化とともに、絶対的な得点力が衰え始めました。
すなわち、この時期は慣れない長嶋監督の采配ミスやベテラン選手の衰退などにより、チーム全体が低迷期へと突入しました。
長嶋監督も厳しい批判に立たされるなど、厳しい時代を迎えました。
しかし、それでも長嶋監督は若手育成に力を注ぎました。
すなわち、この苦しい時期があったからこそ、後の巨人の土台ができたとも言えますね。
地獄の伊東キャンプ「立ち上がれない程の過酷さ」
こうしたチームの低迷を打破するため、長嶋監督は1979年の秋に、伊豆半島の東側にあたる街である静岡県伊東市において、伊東キャンプを敢行しました。
このキャンプ(合宿)は、長嶋監督による特に非常に厳しい練習で知られ、選手は立ち上がるのも困難なほどボロボロに鍛えられたため、地獄のキャンプと呼ばれました。
選手たちが立ち上がれないほどの、ハードな練習
この伊東キャンプでは、
- 坂道ダッシュ
- 地獄のノック
- わずかな休みですら、選手は外出したくなかった
など、そのハードな練習は壮絶極まるものでした。
しかし、逃げた選手は誰もいなかったというのですから、これもまたスゴいものです。
このキャンプで鍛えられた若手選手が、後の1980年代に活躍
こうして長嶋監督は猛練習によって、若い選手たちを鍛え直そうとしていたのでした。
長嶋さんの情熱的な指導は、時に過酷でしたが、選手たちの意識改革に繋がりました。
そして、この時に鍛えられた若い選手たちは、
- 中畑清さん
- 江川卓さん
をはじめ、1980年代以降の巨人軍において、大きな活躍をしていくことになるのでした。
この「地獄の伊東キャンプ」における熱いエピソードは、今でも伝説として語り継がれています。
1980年 監督(第一次)退任 王貞治選手も引退
1975年から続いた第一次長嶋監督時代は、先述のように思うように結果が出せなかったのでした(1976年・1977年は優勝したものの、それ以後の低迷ぶりに世間は容赦無かった)。
それに伴い、世間からの長嶋体制に対する批判も頂点に達していたのでした。
このことから、長嶋監督は、1980年限りで巨人の監督を退任することとなったのでした。
また、同時にON砲の盟友である王貞治選手も、1978年あたりから本塁打数が減り始めてゆき、とうとう年齢からくる衰えから、1980年に現役を引退しました。
王貞治さんは1980年に、30本「しか」打てなくなって辞めたのでした。「しか」というのは、毎年50本がデフォルトだった王貞治さんにしては、少ない・物足りない数字だったからです。
でも普通ならば30本は、全然恥ずかしくない数字ですよね。
「王貞治のバッティングが出来なくなった」と言い残し、引退されたのでした。
すなわち、ここに巨人のV9時代を築いた2人の黄金コンビが、ついに同時にユニフォームを脱いだ瞬間となったのでした。
それは今までの野球の常識が通用しなくななったということでもあり、それは1980年代という新たな野球の時代のはじまりを、この2人の解任・引退は示していたのでした。
そして、この長嶋さんの退任は電撃的で、ファンに大きな衝撃を与えました。
この出来事は先述の通り、一つの時代の終わりを象徴していました。
1981年~1992年までの長嶋茂雄さん
様々な球団から監督就任要請があったが、全て断った
長嶋さんはこの時期、巨人軍以外の球団からもたくさん監督就任の要請を受けていたのでした。
特に、1980年代半ばあたりにおける大洋ホエールズ(現在の横浜DeNAベイスターズ)からのオファーは、長嶋さんの持つ圧倒的なカリスマ性を求めて、とても熱烈なものだったのでした。
しかし、長嶋さんはこれらの要請を全て断りました。それは、
という、長嶋さんならではのこだわり・ポリシーがあったからでした。
すなわち、これは「巨人軍の長嶋」としての信念を貫いた形です。
やはり、ミスターにとって巨人は特別な存在だったわけですね。
この決断からも、長嶋さんの巨人への深い愛情が伝わってきます。
1990年代前後 バラエティー番組で「面白いおっちゃん」扱いされる
1980年代後半から1990年代にかけて、長嶋茂雄さんは野球解説者としてだけでなく、バラエティー番組にも出演するようになりました。
すなわち、親しみやすいキャラクターが注目されました。
長嶋さんの天然かつユニークな言動が、
として、野球ファン以外からも広くたくさんの人々に愛されました。
長嶋さんの持ち前の陽キャラ性・天然ボケ・面白いキャラと、長嶋節と呼ばれる独特な言い回しは、テレビの前のお茶の間を和ませました。
すなわち、ミスターの明るい人柄とサービス精神が、タレントとしても魅力的だったということでしょう。
1993年~2001年 第二次長嶋監督時代
松井秀喜さんをドラフトで引き当てる
そんな中、しばらく野球界の現場からは遠ざかっていた長嶋茂雄さんは、1993年に実に13年ぶりのブランクを経て、巨人軍の監督に復帰しました。
しかも、当時甲子園(高校野球)で大活躍しまくっていた松井秀喜さんをドラフト会議で引き当てたこともあって、大変な話題となり、人気を総ナメにしていたのでした。
松井秀喜さん:石川県の星稜高校で大活躍をしており、特に1992年夏の甲子園では、あまりにもの活躍でプロ・怪物過ぎて「五打席連続敬遠」をされるほど、相手チームからは恐れられていました。
それと同時に、松井秀喜さんの入団先・進路は、とても世間から注目されるようになっていました。
松井秀喜さん本人は阪神タイガースの大ファンで阪神を志望していましたが、長嶋茂雄さんがその年の秋におけるドラフト会議で自信のクジを引き当てた(交渉権を獲得した)ため、ズッコけたそうです。
しかしその後すぐに長嶋監督から「松井君待ってるよ!」と電話があり、松井さんは巨人入団に前向きな気持ちになれたそうです。
これがいわゆる、第二次長嶋政権の始まりです。
1994年 伝説の「10.8決戦」を制して、見事に優勝
松井秀喜さんを見事にドラフト会議で率いれた長嶋監督は、復帰した翌年の1994年に、中日ドラゴンズとのいわゆる「10.8決戦」を制して、見事にリーグ優勝を果たしました!
10.8決戦:1994年10月8日に行われた試合であり、どちらも同率首位で、勝った方が優勝という、あまりにも注目が集まった試合でした。
また、この決戦で敗北した中日ドラゴンズは、必然的にリーグ2位ということになりました。
すなわち、劇的な勝利で、ミスターは再び名将・名監督として認められることになりました。
この第二次長嶋政権下では、松井秀喜選手をはじめとする若手を育て上げてゆきました。
松井秀喜さんとの「素振り」エピソード
長嶋監督と松井秀喜選手の師弟関係を象徴するのが、いわゆる「素振り」のエピソードです。
特に、長嶋監督が松井選手に深夜まで付きっきりで、何百本もの素振りをさせたという話が知られています。
すなわち、ミスターは松井選手の才能を信じ、徹底的に基礎を叩き込んだのでした。
この魂の指導が、のちの大打者・松井秀喜を育てたのですね。
松井選手は、2012年の現役引退のとき、
と述べられていたのでした。
まさしく、感動的な師弟愛ですね!
1990年代後半の、苦しい監督時代
しかし、長嶋監督は1990年代後半は、
- 星野仙一監督率いる、中日ドラゴンズ
- 野村克也監督率いる、ヤクルトスワローズ
などの強力なライバル球団が出現し、長嶋監督率いる巨人軍にとっては、かなり苦しい時期が続きました。
特に「データ」「理論」などを徹底的に駆使した頭脳野球である野村監督の「神采配」にはかなり苦戦し、なかなか勝てない苦しい時期が続きました。
しかも色々なチームから4番バッターを次々に獲得してきて、まるで巨人だけで「4番ばかりのオールスター状態」になっていたのにも関わらずに勝てなかったのは、巨人に対する批判をさらに加速させる要因となってしまいました。
しかし、長嶋さんはそれでも
こうした長い期間の苦難を乗り越えた先に、なんと2000年の優勝という栄光が待っていたのですね。
2000年の「ON対決」と、監督退任
そんな苦難な時期を乗り越えた2000年の日本シリーズでは、
- 長嶋監督率いる、読売ジャイアンツ(巨人)
- 王貞治監督率いる、福岡ダイエーホークス(当時)
の最強両チームがそれぞれ激突した「ON対決」として、歴史的な注目を集めました。
その結果、長嶋監督が率いる巨人が勝利し、見事に日本一に輝きました。
すなわち、ミスターが盟友・王貞治さんとの世紀の対決を制したのでした。
この歓喜のシーズンの翌年に、長嶋監督は後任の原辰徳さんへとバトンタッチし、監督を勇退しました。
そして引退(勇退)の際には、
監督勇退後(2002年~)
2002年、佐倉市名誉市民顕彰
2002年に、長嶋茂雄さんは千葉県佐倉市の名誉市民に選ばれました。
これは、彼が佐倉市出身であり、また長年プロ野球界で偉大な功績を残したことに対する顕彰です。
すなわち、長嶋さんは地元からもその活躍が高く評価されたということです。
長嶋さんの出身地である佐倉市には、長嶋茂雄記念岩名球場があるなど、今でもゆかりの地として知られています。
地元からも愛されるミスターは、本当に誇り高き存在ですね!
2013年 国民栄誉賞受賞
長嶋茂雄さんは、2013年に国民栄誉賞を受賞しました。
すなわち、これまでの様々な偉大な功績が、国によって正式に認められたのです。
また、このときは松井秀喜さんと同時受賞となり、先述の通りの師弟関係での受賞は、とても大きな話題となりました。
授賞式においては、2004年に発症した脳梗塞の後遺症があり、不自由な体ながらも、感動的なスピーチを披露し、多くのファンの心を打ちました。
国民栄誉賞:1977年に福田赳夫内閣によって創設され、王貞治さんのホームラン新記録達成を称えるために設けられました。
表彰の基準は、国民に敬愛されていること、社会に明るい希望を与えていること、「前人未到」の偉業を達成したことが挙げられます。
2010年代後半の長嶋さん
2010年代後半、既に年齢が70代の中盤に達していた長嶋茂雄さんは、病気と闘いながらも、野球界の発展をずっと見守り続けました。
すなわち、巨人軍の終身名誉監督としてその存在感を示し続け、グラウンドに立つ機会こそ減りましたが、その存在感はなお絶大でした。
2021年に行われた東京2020オリンピックの開会式では王貞治さん、松井秀喜さんと聖火ランナーを務められました。
また、プロ野球の試合をテレビで観戦するなど、野球への情熱は衰えることはありませんでした。
ミスターの静かな闘いが続いていた時期です。
晩年・逝去
長嶋茂雄さんの晩年は、体調の回復とリハビリに努める日々でした。
メディアへの露出こそ減ったものの、野球界のレジェンドとして、常に注目を集めていました。
すなわち、令和の時代となり、彼の現役時代をほとんど知る人がいない世の中になっても、国民的ヒーローとしての地位は揺るぎませんでした。
2025年6月3日、長嶋茂雄さんは89歳でご逝去されました。
しかし、彼が日本中に夢と感動を与え続けた功績は、永久に不滅です。
松井秀喜さんが弔辞で述べられたように、
今度は私が、監督(長嶋茂雄さん)を逃しません。
だから私は、あえてサヨナラとは言いません。
今後も、引き続きよろしくお願いします。
と仰られたことは、まだミスターとの別れは存在せず、今後の明るいプロ野球界の未来の展望を力強く述べられたような、とても感動的なものでした。
私たちはミスターを、これからも永遠に愛し続けることでしょう。
おわりに・長嶋さんの熱い生涯を学んでみて
長嶋茂雄さんの熱い生涯を振り返ってみて、いかがだったでしょうか。
すなわち、プロ野球という枠を超えた、国民的ヒーローのドラマを感じられたことでしょう!
佐倉での幼少期から立教大学での活躍、そして巨人での栄光と苦闘は、私たちの心を打ちますね。
この知識を持つことで、伊豆・大仁の観光地などを訪れる際の感動は、何倍にも膨らみますよ!
ミスターの原点を探訪する旅は、きっと忘れられない思い出になるでしょう。ぜひ訪れてみてください!

コメント