鉄道唱歌 東海道編の歌詞(横須賀の観光・歴史など)について、鉄道に詳しくない方にもわかりやすく解説してゆきます!
まずは原文から!
はや横須賀に着きにけり
見よやドツクに集まりし
わが軍艦の壯大を
さらに読みやすく!
はや横須賀に 着きにけり
見よやドックに 集まりし
わが軍艦の 壮大を
さあ、歌ってみよう!
♪はやよこすかにー つきにけりー
♪みーよやドックに あつまりしー
♪わがぐんかんのー そうだいをー
新橋駅→高輪ゲートウェイ駅→品川駅→大森駅→川崎駅→鶴見駅→東神奈川駅→横浜駅→大船駅→藤沢駅→大磯駅→国府津駅(→小田原駅・熱海駅)
(横須賀線)
大船駅→鎌倉駅→逗子駅→横須賀駅→久里浜駅
※鉄道唱歌に関係ある主要駅のみ抜粋(便宜上、ターミナル駅等も表記)
※鉄道唱歌の当時の「神奈川駅」と、現在の「東神奈川駅」は別の駅
※小田原駅・熱海駅は鉄道唱歌の当時のルートには含まれない
逗子駅を過ぎて、横須賀方面へ
鎌倉観光を終えると、今度は
- 逗子駅(神奈川県逗子市)
を過ぎて、横須賀方面へ向かいます。

逗子駅(神奈川県逗子市)
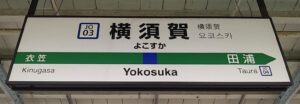
横須賀駅(神奈川県横須賀市)
横須賀線の歴史 かつて軍事輸送のための路線だった
大船駅(神奈川県鎌倉市)から分かれる横須賀線は、元々は
- 造船
- 海軍工廠
- 鎮守府
などといった、明治時代の日本に欠かせない機能を備えた軍港都市・横須賀への軍事輸送のために造られた路線でした。
広島県の「呉線」も、横須賀線の歴史と似ている
これは広島県にある呉線などにも同じことがいえます。
呉線は、
- 海田市駅(広島県安芸郡海田町)
から山陽本線と分岐して、
- 呉駅(広島県呉市)
に至る路線です。
かつて呉市には(横須賀と同じく)当時の日本海軍の戦艦を造る海軍工廠や、海の守りの要である鎮守府が置かれていたのでした。
そのため、呉線は軍事的に重要な路線でした。
横須賀の、「軍港」として栄えてきた歴史
神奈川県横須賀市は、古くから軍事的に重要な港として栄えた街です。
明治時代には、
- 京都府舞鶴市
- 長崎県佐世保市
- 先ほど述べた、広島県呉市
などの軍港と同じように、当時の日本の海の防衛の要という意味で「鎮守府」がおかれていた場所です。
「鎮守府」とは、簡単にいえば国の防衛の重要な拠点のことです。
舞鶴鎮守府については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

呉鎮守府については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

佐世保鎮守府については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

「鎮守府」とは?その由来は、かつての東北地方にあり
「鎮守府」というフレーズは、元々は鉄道唱歌 奥州・磐城編でも解説したように、
- 岩手県奥州市にあった「胆沢城」
- 宮城県多賀城市にあった「多賀城」
などといった、東北地方の防衛の拠点に対しても用いられたフレーズでした。
本サイトで以前解説した東北地方の復習にはなりますが、かつて平安時代の東北地方には朝廷に従わない「蝦夷」とよばれる勢力がありました。
これらの人々を征伐するために、朝廷から東北地方に派遣された、
- 源頼義
- 源義家
などの武士がいました。
これらの武士の「東北地方の軍事的な拠点」として、また「防衛の要」として構えていたお城(多賀城や胆沢城など)のことを「鎮守府」と呼んでいたわけです。
奥州の鎮守府や、源頼義・源義家などの関連事項に関しては、以下の各記事でもわかりやすく解説していますので、ご覧ください。


横須賀は「天然の良港」として発展してきた
横須賀と同じように、明治時代に佐世保、舞鶴市、呉などの港町が鎮守府の場所として選ばれたのは、
- 元々非常に入り組んだ複雑な海岸にあったため。
- それらが自然のバリアーとしての役割を果たしてくれるため。
- こうした地形から、敵から守るために防衛上都合が良かったから。
などの理由が挙げられるでしょう。
このような自然が作り出した優れた港のことを、「天然の良港」といいます。
横須賀でかつて明治時代に活躍した、レオンス・ヴェルニー
横須賀市は、明治時代に軍港として発展させていくため、レオンス・ヴェルニーというお雇い外国人を招いて軍事施設を発展させていきました。
「お雇い外国人」とは、日本に海外の技術を教えたり、また定着させるために海外から招かれた外国人のことをいいます。
当時の日本は「富国強兵」といって、欧米列強に追いつけ追い越せという勢いでした。
そのため、国の文明や軍事力を発展させていくために、とても必死だったのです。
JR横須賀駅の駅近くには、ヴェルニーの名前に因んだ「ヴェルニー公園」があります。
横須賀が海軍基地として適していたのは、巨大な軍艦が停泊できるだけの充分な深さのある海があったからでもありました。
船を造るための施設「ドックどつく」
「ドック」とは、巨大な船を造るために必要な、人工的に造った巨大なくぼみのことです。
このくぼみの中に船の型を入れ、高い場所から人が船を造ったり、整備や修理をしたりすることができるというわけです。
また、都市部などで水が流れるように人工的に造ったくぼみのことを「暗渠」というのをご存知かもしれません。
これと同じで、ドックせんきょのことを「船渠」と呼んだりします。
ドックはかつて「どつく」「ドツク」とも表記しました。
小さい文字のことを「捨て仮名」というわけですが、この「捨て仮名」が正式に日本語に採用されるようになったのは、1946年のことです。
なので明治時代には、「ドツク」「ステーシヨン」みたいな表記が多いわけです。
横須賀出身の小泉純一郎・前首相と、hideさん
横須賀市は、小泉純一郎前首相や、X JAPANのギタリストだったhideさんの出身地でもあります。
かつての内閣総理大臣・小泉純一郎さん
小泉純一郎さんは、2001年~2006年における日本の内閣総理大臣でした。
2001年に内閣総理大臣として就任すると、戦後1位の87パーセントという驚異的な支持率を記録しました。
また、横須賀市出身であり2023年現在現職の衆議院議員である小泉進次郎さんは、小泉純一郎前首相の次男にあたります。
また、小泉純一郎前首相はX JAPANのファンであることを公言されており、自民党のCMでX JAPANの代表曲「Forever Love」を使用されたことでも話題になりました。
伝説のX JAPANのギタリスト・hideさん
hide(ヒデ、本名・松本秀人)さんは、横須賀市出身のギタリストでした。
1964年12月生まれであり、小学校の頃は肥満体型に悩まされ、とても内気な少年だったと言われています。
しかし中学生になってギターを始めてからは一転して明るい性格となり、また減量にも成功してロックギタリストに相応しいスリムな体型を手に入れました。
その後X JAPAN(当時は「X」)のギタリストとして1989年にデビューされるとX JAPANは日本人なら誰もが知るほどのロックバンドとなりました。
1998年5月に残念ながら他界されましたが、現在でも私を初めとする根強いファンから愛され続けています。

猿島(神奈川県横須賀市)
X JAPANの歴史については、以下の記事でもわかりやすく解説していますので、ご覧ください。

横須賀の海から、かつて房総半島へと渡った、日本武尊
また、横須賀には、かつて日本神話においてヤマトタケルノミコト(日本武尊)にゆかりのある地名である、「走水」という地名があります。
横須賀の走水は、かつて日本武尊が「関東地方を征伐せよ」と父上の景行天皇に命じられて房総半島まで向かう途中、この地域から東京湾を渡って房総半島へ向かわなければなりませんでした。
妻が犠牲になり、嵐を静める
しかし、あまりにも荒れ狂う海のため、ここで戸惑ってしまいます。
そこで、日本武尊の妻の弟橘媛が、自ら犠牲になって海へ走って飛び込み、見事に嵐で荒れる海を静めました(これが「走水」の由来)。
房総半島へと渡った、日本武尊
日本武尊は、嵐が止んだ東京湾を渡り、房総半島の君津に渡りました。
君津という地名は、日本武尊(君)が上陸した湊(津)という故事にちなみ、千葉県君津市の地名の由来になっています。
そして、嵐を止ませるために、自ら海(水)に走って飛び込み犠牲になった妻のことを想い、日本武尊はいつまでもその海(津)から去りませんでした。
木更津という地名は、「日本武尊(君)が去らずの津」という故事にちなみ、千葉県木更津市の地名の由来となっています。
君津、木更津における日本武尊の伝説・エピソードについては、以下の記事でもわかりやすく解説していますので、ご覧ください。

横須賀以外にも、日本武尊に由来する地名は、全国に存在する
このように、日本武尊(ヤマトタケルノミコト)の故事に由来する地名は、全国に存在するのです。
例えば、千葉県船橋市の「船橋」という地名も、日本武尊が木で出来た船を橋の代わりににして渡った場所、という意味からきています。
大阪府羽曳野市の「羽曳野」という地名も、日本武尊が亡くなってから鶴となって飛んでいき、羽を引いて飛んだ野原という意味からきています。
静岡県焼津市の「焼津」という地名も、関東地方に向かう途中(東国遠征)で、敵を倒すために天叢雲剣で野原を焼き払った湊(津)という故事からきています。
このように、地名からその地の歴史をたどるというのも、とても面白いものです。
横須賀に存在する、防衛大学校
また、横須賀の走水には、自衛隊の幹部を育成する学校である防衛大学校があります。
横須賀の街を観光していると、制服を着た防衛大学校の学生さんたちとすれ違うことがあります。
「防衛大学校」とは?
防衛大学校は、神奈川県横須賀市走水にある、幹部自衛官を育成する学校です。
幹部自衛官とは、三尉以上の階級の自衛官のことをいいます。
自衛隊の階級は、
- 幕僚長
- 将
- 佐
- 尉
- 曹
- 士
などに分けられます。上にいくほど偉くなります。
(上記は正確ではなく、便宜上簡略化して表記しています)。
このうち、「尉」以上の階級の人を、幹部自衛官といいます。
「佐」までいくと、かなり偉い人の部類に入ります。「将」以上は、そうそうなれるものではありません。
自衛隊で最も偉い人は統合幕僚長であり、陸海空の自衛隊を全て統率します。
統合幕僚長は、東京都の市ヶ谷の防衛省におられます。
防衛大学校卒業後はエリートコース しかし学生生活は厳しい
卒業したら、若くしていきなり「幹部」
防衛大学校卒業後は、いわゆる「士」と「曹」の階級を省略して、現場でいきなり幹部自衛官として指揮命令する立場になります。
そのため、会社でいうといきなり課長職以上のポジションとなります。
その後も次々に出世していくため、エリートコースであるといえます。
給料ももらえ、衣食住もタダ
また、防衛大学校は一般大学とは違い、学費がかからないばかりか、給与まで支給されます。
全寮制の厳しい生活、パワハラどころじゃない厳しい指導
しかし、その代わり全寮制で集団生活の厳しい生活を義務付けられ、先輩や教官の命令は絶対で逆らえません。
防衛大学校に限らず、自衛隊教育隊や警察学校・消防学校・海上保安大学校などもそうですが、人の命を守る公務員の卵として育成される以上、パワハラ上等の鬼のような教官によって厳しい指導を受けることは仕方ありません。
辞める人多し、集団生活が苦手な人には向かない学校
こうした厳しい環境のため、適性の無い者は容赦なく退職に追い込まれ、ふるい落とされます。
公務員としていざ現場に出れば、どんな危険が待ち受けているかわからないわけですから、パワハラだなんて言っていられません(ただし、近年は改善傾向)。
つまり、それに耐える訓練ということなんですね。
少なくとも、集団生活が苦手な人には向かない職種といえるでしょう。
卒業式の「帽子投げ」は圧巻
防衛大学校は、やはり卒業式がとても有名です。
- 内閣総理大臣による「訓示」
- 卒業生が一気に帽子を上に投げて走り出す、帽子投げ
卒業生によるこういった迫力あるシーンは、テレビ等でも見たことがある人が多いのではないでしょうか。
ペリー提督が黒船で到着した、浦賀(久里浜)
横須賀の存在する三浦半島には、1853年にマシュー・ペリー提督が黒船を率いて訪れた場所であると知られています。
歴史の教科書では「浦賀に来港した」と習うと思いますが、実際にペリー提督が上陸した場所は久里浜になります。
久里浜駅(神奈川県横須賀市久里浜)は、横須賀線の終着駅でもありますよね。
久里浜には、ペリー提督来港を記念する「ペリー公園」があります。
横須賀近くにある、別荘地が並ぶ「葉山町」
横須賀の近く・三浦半島の西側には、葉山町という、別荘に適した、とても景色のよい地域があります。
葉山町には、天皇陛下や皇族の方々のご静養に用いられる、葉山御用邸があります。
御用邸とは?
御用邸とは、天皇陛下や皇族の方々の別荘のことをいいます。
御用邸の場所は一般的に、景色が綺麗であり、夏は涼しく、冬は暖かい、気候のよい場所が選ばれます。
栃木県にある「那須御用邸」は、夏にとにかく涼しい那須高原にあります。
次は、横須賀から大船駅へ戻り、大磯方面へ
横須賀の観光が終わったら、再び大船駅に戻り、国府津方面へ向かってゆきます!

コメント