鉄道唱歌 奥州・磐城編の歌詞を、わかりやすく解説してゆきます!
両毛線の地理・歴史などを、やさしく解説してゆきます!
↓まずは原文から!
經て高崎に至るべし
足利桐生伊勢崎は
音に聞こえし養蠶地
さらに読みやすく!
経て高崎に 至るべし
足利桐生 伊勢崎は
音に聞こえし 養蚕地
上野駅→王子駅→赤羽駅→(荒川)→浦和駅→大宮駅→蓮田駅→久喜駅→栗橋駅→(利根川)→古河駅→間々田駅→小山駅→小金井駅→石橋駅→雀宮駅→宇都宮駅
(両毛線)
小山駅→足利駅→桐生駅→伊勢﨑駅→前橋駅→新前橋駅(→高崎駅)
※鉄道唱歌に関連する主要駅のみ表記
※新前橋駅~高崎駅は上越線の区間
小山駅を左(西)へ行くと、両毛線で前橋・高崎へ
前回説明したように、小山駅(栃木県小山市)は左右(東西)に別々の線路が分かれています。
すなわち、
- 右側(東側)を水戸線
- 左側(西側)を両毛線
といいます。

小山駅・両毛線ホームより(栃木県小山市)
そのうち、今回は両毛線の旅ということになります。
そもそも「両毛線」とは?
両毛線は、栃木県小山市の小山駅と、群馬県前橋市の新前橋駅を結ぶ、いわば
- 「栃木県と群馬県を、東西にそれぞれ結ぶ路線」
になります。
両毛線は「りょうげせん」ではありません。
「りょうもうせん」です。
私もはじめは「りょうげせん」と読んでしまったため、慣れるまでは大変ですね。
養蚕の名産地として栄えてきた、両毛線の沿線
また、歌詞にもあるように、両毛線の沿線は製糸や織物、養蚕などの名産地として栄えてきた歴史があります。
そのため、歴史的にこれらの生産物を運ぶための路線として作られました。
新前橋駅からは、さらに上越線と接続して、
- 高崎駅(群馬県高崎市)
に至ります。
「両毛線」の名前の由来とは?
両毛線の名前の由来について、少し勉強しましょう。
群馬県は元々、上野国という国名でした。
「うえの」ではなく、「こうづけ」と読みます。
また、栃木県は元々、下野国という国名でした。
「しもの」ではなく、「しもつけ」と読みます。
- 群馬県→上野国、上毛野国
- 栃木県→下野国、下毛野国
そして、間に「毛」という文字が入る場合があります。
読み方は同じです。
つまり、上毛野国と下毛野国の両方の「毛」がつく国を結ぶ、つまり
- 「群馬県と栃木県の両方の県を結ぶ」
という意味で、「両毛線」というわけです。
なお、「上毛新聞」「上毛電鉄」などのように、群馬県のことを「上毛」という表現は一般的に存在しています。
しかし、栃木県に対して「下毛」という表現をするのはあまり一般的ではないようです。
「上越新幹線」の「上越」と、新潟県上越市の「上越」は、意味が異なる
さらに補足すると、「上越新幹線」というのは
- 「上野国(群馬県)」
- 「越後国(新潟県)」
を結ぶ新幹線という意味になります。
つまり、群馬県と新潟県を結ぶ新幹線という意味となります。
川端康成の有名な小説「雪国」の冒頭に出てくる、いわゆる
の国境とは、いわゆる
- 上越国境(群馬県と新潟県の県境)
のことではないかと言われています(諸説あり)。
つまり、ここでいう「上越」とは、新潟県上越市の「上越」とは意味が異なります。
新潟県は広い!大きく分けて三つのエリアに分かれる
新潟県はとても広いため、京都に近い順に、
- 「上越」
- 「中越」
- 「下越」
に分かれています。
さらに、京都に近い順に
- 福井県→越前
- 石川県→加賀
- 富山県→越中
- 新潟県→越後
のように分かれています。
混乱しないよう、併せて覚えておきましょう。
なぜ上越妙高駅は、上越新幹線じゃないの!?という疑問
このことを知らないと、
という疑問が起こってしまうわけです。
私も小学生のときは、なんで上越新幹線が新潟県上越市に向かっていないのだろう、と思っていました。
両毛線沿線の旅
話がだいぶずれてすみません。
両毛線の沿線の話題に戻ります。
「足利学校」や足利氏の出身地としても知られる、栃木県足利市

足利駅(栃木県足利市)
両毛線の沿線にある栃木県足利市は、その名の通り、あの室町幕府を作り上げた足利氏の発祥の地として知られています。
また、
- 隣の小山市も、小山氏と縁がある
- 結城市も、結城氏とゆかりがある
ということは、前回も説明しました。
この辺りは、その地名とゆかりある一族と関連が高いケースが、比較的多いという印象です。
日本最古と呼ばれた学校「足利学校」
そして、足利市にはかつて日本最古と呼ばれた学校である「足利学校」があります。
創立はなんと平安時代で、日本の歴史上トップクラスに古い学校であり、日本最古の学校とも呼ばれています。
両毛線の旅:「桐生織」で有名な、群馬県桐生市
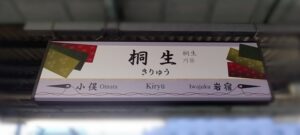
桐生駅(群馬県桐生市)
群馬県桐生市は、同じく両毛線沿線の重要拠点であり、いわゆる桐生織で有名な、織物の産地です。
織物といえば京都の西陣織が有名ですが、それと比肩するほどの名声があります。
織物の産地で他に鉄道唱歌に関係するところでは、
- 岩手県盛岡市や福井県福井市の羽二重織
- 福岡県福岡市博多区の博多織
が有名だと歌われていますね(それぞれ、以下になります)。
併せて覚えておきましょう。
両毛線の旅:同じく絹織物で有名な、群馬県伊勢崎市
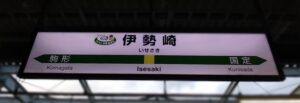
伊勢崎駅(群馬県伊勢崎市)
群馬県伊勢崎市も、桐生市と同じく両毛線の重要都市であり、また絹織物が盛んです。
絹と生糸はどう違うの?という疑問がわくと思いますが、簡単に説明すると以下のようになります。
- 生糸→加工しておらず、原料である繭に近い糸
- 絹→生糸を加工して、おりやすくしたもの
両毛線の旅:群馬県の県庁所在地・前橋市
群馬県前橋市は、群馬県の県庁所在地です。
人口では高崎市の合併により抜かれてしまったものの(高崎市:37万人、前橋市:33万人)、赤城山の麓に雄大に市街地が広がる、県庁所在地に相応しいとても大きな都市であることには変わりありません。
なお前橋市は、鉄道唱歌 北陸編 第12番では、「上野一の大都会」と歌われています。
群馬県最大の人口を持つ都市・高崎市
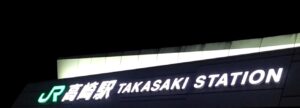
高崎駅(群馬県高崎市)
群馬県高崎市は、前橋市と並ぶ群馬県の2大都市の一つです。
高崎駅は上越新幹線・北陸新幹線が停車する駅であり、駅前はとても都会的に栄えている群馬県最大の人口を擁する街です。
かつては、江戸時代に京都へ徒歩または馬で向かう旅人たちの道路であった中山道の宿場町・高崎宿として栄えました。
両毛線沿線の解説
明治時代の「殖産興業」で栄えた、群馬県の養蚕・生糸産業
このように、群馬県や隣の栃木県では、明治時代に
ということで、
- 当時の主力産業であった、生糸や織物などを、
- いかに大量に効率よく生産し、
- それを輸出することで、大きな利益を上げる
かが重要でした。
そのため、群馬県には桑畑・養蚕・製糸・織物に関連する地域がたくさんあります。
以下が、それぞれの工程です。
- 桑畑→カイコが食べる桑を育てる
- 養蚕→桑を食べさせてカイコを育てる
- 製糸→カイコが生んだ繭から糸を作る
- 織物→糸をおりあわせて着物を作る
群馬県、栃木県のいわゆる両毛地域では、これらの名産地というわけです。
製糸で特に有名なのは、現在では世界遺産にも登録されている、
- 「富岡製糸場(群馬県富岡市)」
が有名ですね。
富岡製糸場については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

魅力度ランキングでは常に下位・・・群馬県には魅力がない? けど実はこんなにある群馬県の魅力
観光地としての群馬県ですが、2021年の
- 「都道府県魅力度ランキング」
において、群馬県は44位という不本意な結果に終わってしまい、山本知事が「法的措置も検討」という発言をして話題になったことがありました。
しかし、群馬県には以下のようなたくさんの観光的魅力があります。
- 避暑地で有名な伊香保温泉、榛名山
- 日本一のモグラ駅「土合駅(群馬県利根郡みなかみ町)」
- 死者数世界一でギネスブック登録で有名な、谷川岳
- みなかみ町の温泉街、利根川の流れの景観
- ドリフターズの曲「いい湯だな」でも歌われている「草津温泉(群馬県吾妻郡草津町)」
- ユニークな形をした山で有名な「妙義山」と、碓氷川の景観
- 温泉マークの発祥地「磯部温泉(群馬県安中市)」
- 信越本線横川駅(群馬県安中市)の「峠の釜めし」「アプトの道」
などなど。
他にも挙げればたくさんあると思います。
なお、現在ではドリフターズの曲で有名な「いい湯だな」も、元々はデューク・エイシスというアーティストによる群馬県の温泉をメインに歌った曲です(草津温泉、伊香保温泉、万座温泉、水上温泉)。
これらの群馬県の観光的魅力については、鉄道唱歌北陸編でかなり歌詞を割いて歌われていますので、そちらで詳しく解説しています。
【伊香保温泉について】

【磯部温泉について】

【アプトの道について】

群馬県の観光と名所探訪はいかがだったでしょうか。
次回は、再び小山駅から宇都宮方面へ
次は、再び小山駅に戻り、宇都宮方面へ戻ります!

コメント