鉄道唱歌 奥州・磐城編の歌詞を、わかりやすく解説してゆきます!
栃木県北部・塩原の地理・歴史などを、やさしく解説してゆきます!
↓まずは原文から!
急げば早も西那須野
こゝよりゆけば鹽原の
温泉わづか五里あまり
さらに読みやすく!
急げば早も 西那須野
ここよりゆけば 塩原の
温泉わずか 五里あまり
さあ、歌ってみよう!
♪いそげばはやもー にしなすのー
♪ここよりゆーけば しおばらのー
♪おんせんわずかー ごりあまりー
宇都宮駅→西那須野駅→那須塩原駅→黒磯駅→黒田原駅→新白河駅→白河駅→泉崎駅→矢吹駅→須賀川駅→郡山駅→日和田駅→本宮駅→二本松駅→安達駅→松川駅→福島駅
※鉄道唱歌に関係ある主要駅のみ抜粋
日光の観光を終え、再び宇都宮駅へ 那須塩原・黒磯方面へ向かう
日光の観光を終えると、また宇都宮に戻って、東北本線に乗り換えて、
- 那須塩原
- 黒磯
方面へと向かいます。

宇都宮駅(栃木県宇都宮市)
宇都宮は、ギョーザの名所
なお、宇都宮の観光などについてあまり触れていなかったため、少し触れておきます。
宇都宮はギョーザ(餃子)の名物として有名です。
それは、戦時中に満州にいた兵士たちが日本に戻ってきたとき、
ということで、持ち帰られたものだそうです。
ギョーザ定食 浜松 VS 宇都宮!?
これは同じく、ギョーザが名物である静岡県浜松市にも同じことがいえます。
なお、ギョーザの名をめぐって宇都宮市と浜松市はライバル関係にあり、競合関係にあります。
宇都宮駅周辺には、まるで探すのに困らないほど、ギョーザのお店がたくさんあります。
私(筆者)も、ギョーザ定食をいただいたことがあります(^^)。
是非、静岡県浜松市のギョーザ定食と比較して、食べてみましょう。
さらに余談 浜松 VS 多治見!?
余談ですが、浜松市は「日本一暑い街」の座をめぐって、岐阜県多治見市とも競合関係・ライバル関係にあります。
浜松市は多方面に観光関連において、ライバル多しですね。
静岡県浜松市の観光的魅力については鉄道唱歌 東海道編 第27番で歌われています。
以下の記事でわかりやすく解説していますので、ご覧ください。

以下の記事でわかりやすく解説していますので、ご覧ください。

必要品を整え、再度旅へ出発
また、ギョーザを食べなくとも、宇都宮駅周辺は飲食店も充実しています。
また、駅向かい側の大きな商業施設である「トナリエ宇都宮」には、100均もあります。
そのため、これからの長い旅に備えて必要品(※)を買っておきましょう。
※必需品とは人にもよりますが、例えばマスク、ティッシュ、簡単なお菓子類、電池、携帯トイレなど。
昔の栃木県・下野国の安寧を守り続けてきた、二荒山神社
宇都宮の真ん中に立つ立派な神社が、
- 「二荒山神社」
です。
この二荒山神社は、栃木県が「下野国」と呼ばれていた時代から、下野国の平和や安全を守り続けてきた(これを「鎮護」「鎮守」などのようにいいます)、重要な神社です。
東北本線に乗り込もう 岡本駅・鬼怒川を過ぎ行く
さて、宇都宮で観光や食事、買い物などを済ませると、いよいよ東北本線に乗り、
- 那須塩原・黒磯方面
へと向かいます。
宇都宮駅から乗る場合は、大抵の場合は
- 「東北本線・黒磯行き」
に乗ることになると思います。
岡本駅を過ぎ、鬼怒川を渡る
宇都宮駅を出発し、一つ隣の
- 岡本駅(栃木県宇都宮市下岡本町)
を過ぎると、
- 鬼怒川
という大きな川を渡ります。
烏山線との分岐駅・宝積寺駅
鬼怒川を渡ると、烏山線との分岐駅である
- 宝積寺駅(栃木県塩谷郡高根沢町宝積寺)
に着きます。
烏山線は、宝積寺駅と烏山駅(栃木県那須烏山市)を東西に結ぶ路線です。
東北本線から東へ分岐していく路線になりますが、烏山駅でストップしており、そこから先の路線が続いておりません。
こうした「先が続いてない路線」のことを、いわゆる「盲腸線」といいます。
「盲腸線」は、なぜできるのか?
盲腸線ができる理由は、
- 本来はもっと先まで延長して大都市まで至る路線とする計画が、
- 沿線の人口減少やモータリゼーション(※)などの影響で、利用者が見込めなくなった場合に、
- 先の路線が建設されずに、
- 途中までの路線が残ってしまう
というのが一般的です。
※高度経済成長期以降に自動車が一般家庭に普及し、それに伴い鉄道の利用者が減るなどの現象が起こる
烏山線の場合も、元々は水郡線の
- 常陸大子駅(茨城県久慈郡大子町大子)
まで続く計画があったとする説や、水戸方面まで伸ばす計画があったそうです。
しかし、それらの計画が頓挫してしまい、現在の
- 宝積寺駅~烏山駅間
のみが残り、盲腸線となったようです。
氏家駅・矢板駅・野崎駅を過ぎて、やがて西那須野駅へ
宝積寺駅を過ぎると、
- 氏家駅(栃木県さくら市氏家)
- 矢板駅(栃木県矢板市)
- 野崎駅(栃木県大田原市)
などの駅を過ぎて、歌詞にあるように
- 西那須野駅(栃木県那須塩原市)
に至ります。
栃木県さくら市
ちなみに、栃木県さくら市は、
- 主要駅である氏家駅のある氏家町
- 周辺の町である喜連川町
のそれぞれが2005年に合併して、できた街です。
氏家町は、かつて奥州街道の宿場町である「氏家宿」があった町でもあります。
周辺に鬼怒川など桜の名所が多かったことから、「さくら市」と名付けられたそうです。
北関東圏における、同じ桜の名所
また、北関東圏で同じ桜の名所といえば、奈良の吉野と比肩する桜の名所である
- 茨城県桜川市
があります。
最寄駅は、水戸線岩瀬駅です。
さらに、さくら市と読み方が全く同じ
- 千葉県佐倉市
とは、全く別の自治体となります。
栃木県さくら市のように、2000年代以降に新しくできた市は、ひらがなでおしゃれな市名が多い印象ですね!
西那須野から西へ約20km、塩原温泉郷
・・・話がずれてしまいすみません。
塩原温泉郷は、西那須野駅から約20kmほど西にいったところにある温泉街です。
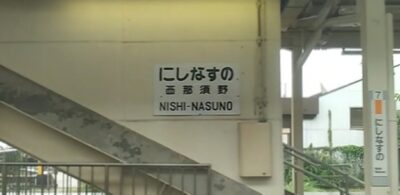
西那須野駅(栃木県那須塩原市)

西那須野駅(栃木県那須塩原市)
歌詞では
温泉わずか五里あまり」
とあります。
すなわち、一里は約4kmですから、4km × 5里= 20kmで、大体計算が合うかと思われます。
窓の左側には、徐々に那須の山々が登場
西那須野駅を過ぎたあたりから、窓の左側にはいよいよ、標高約1,500m~2,000mにも及ぶ、那須の山々が姿を現すようになります。
すなわち、標高が高いため、真冬の時期にこの地域を旅行すると、早速山々が白い雪をかぶった状態になってきます。
那須塩原駅(栃木県那須塩原市)に到着
そして、新幹線も停車する重要駅であり、那須への観光の入り口ともいうべき
- 那須塩原駅(栃木県那須塩原市)
に到着します。
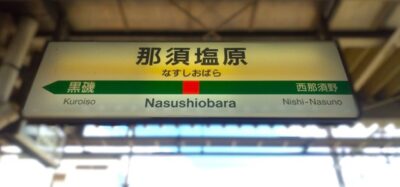
那須塩原駅(栃木県那須塩原市)
「塩原」の名前の由来 昔は「塩」がよく採れた場所だった?
塩原の由来には、諸説あります。
- 昔はこの地域まで海岸線が来ており、
- そこから豊富な塩がとれたこと
から「塩原」とする説があります。
すなわち、現在の海岸線と大昔の海岸線が違うというのは、よくある話なのです。
例えば、
- 昔は東京湾の水面が高かったことから、さいたま市の見沼あたりまで海岸線がきていたため(奥東京湾)、「浦和」という地名の由来になった。
- 江戸城のある辺りまで入り江(日比谷入江)がきていたことから、入り江の戸口という意味で、「江戸」という地名の由来になった。
など、諸説あるものの過去の海岸線に由来する地名は、少なからずあると考えられるというわけです。
全国各地にある、「塩」に由来する地名
なお、昔は「塩」は非常に重要なものと考えられていました(現在でも重要ですが)。
すなわち、「塩」に由来する地名はとても多いというわけです。
例えば、長野県塩尻市の「塩尻」という地名は、
- 越後(新潟県)の方から来た人が、
- 塩が採れない内陸部まで行って、塩を売っていたときに、
- 塩尻市のあたりで、塩の在庫が切れてしまい、
- 「塩が途切れる場所」という意味で、「塩尻」という地名になった
とする説があります。
また、
- 塩尻の東にある甲斐国(現在の山梨県)は、内陸部であるため、
- 東海地方から塩を輸入するしかなく、
- 武田信玄の時代に深刻な塩不足に陥り、
- 甲斐国の人々の生活に影響を及ぼしたこたから、
- 越後国(新潟県)の上杉謙信が、敵国であるはずの甲斐国の人々を救うために、塩を送った
というエピソードがあります。
これが「敵に塩を送る」という言葉の語源になったとされています。
次回は、那須高原・殺生石の話題へ
次は、那須高原・殺生石の話題となります!

コメント