山陰鉄道唱歌の歌詞を、わかりやすく解説してゆきます!
淀江・日野川の地理・歴史などを、やさしく解説してゆきます!
↓まずは原文から!
淀江の町を過ぎゆけば
濁れる水の日野川に
鐵の採取ぞしのばるゝ
さらに読みやすく!
淀江の町を 過ぎゆけば
濁れる水の 日野川に
鉄の採取ぞ しのばるる
さあ、歌ってみよう!
♪よどえのまちをー すぎゆけばー
♪にごれるみーずの ひのがわにー
♪てつのさいしゅぞ しのばるるー
鳥取駅→湖山駅→宝木駅→浜村駅→青谷駅→泊駅→松崎駅→倉吉駅→由良駅→八橋駅→赤碕駅→御来屋駅→名和駅→大山駅→淀江駅→伯耆大山駅→米子駅
※鉄道唱歌に関連する主要駅のみ表記
淀江→日野川(→米子)
日本海をはるか北にして、大山の麓を米子に向かって進む

海を窓の遠くに、米子方面へ進む(山陰本線)(鳥取県)
そして大山のふもとを過ぎゆくと、やがて
- 淀江駅(鳥取県米子市淀江町)
- 伯耆大山駅(鳥取県米子市)
を過ぎます。そして、日野川という大きな川を渡ります。
大山をバックにする、淀江駅(淀江町)
淀江駅は、大山(標高1,729m)がバックによく眺められます。

淀江駅(鳥取県米子市淀江町)
伯備線との合流点・伯耆大山駅
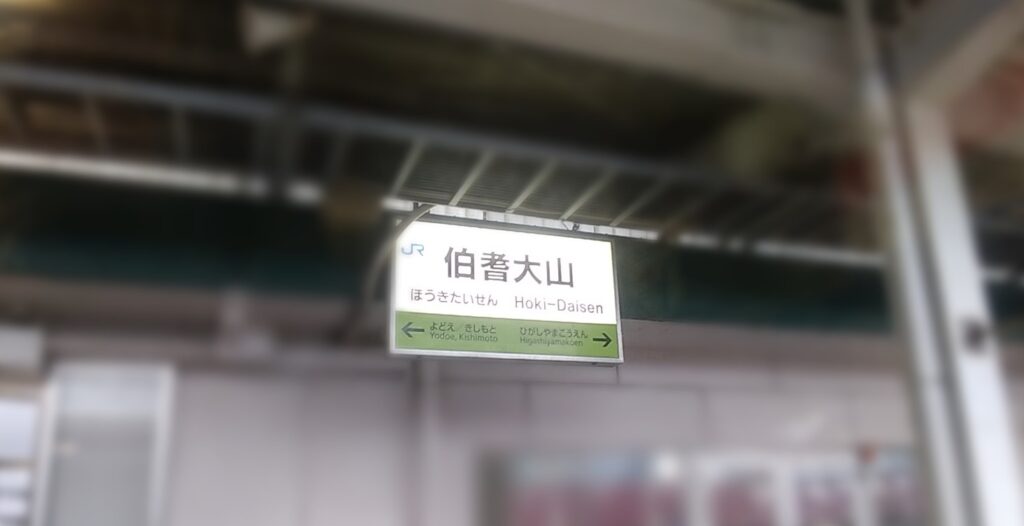
伯耆大山駅(鳥取県米子市)
伯耆大山駅は、伯備線との分岐駅・合流駅でもあります。
日野川は、伯備線とともに並行して流れてきた川です。
伯備線とは?
伯備線は、岡山県の倉敷市からはじまり北上していくと、
- 総社(岡山県総社市)
- 備中高梁(岡山県高梁市)
- 新見(岡山県新見市)
- 備中神代(岡山県新見市)
- 根雨(鳥取県日野郡日野町)
を通り、やがて日本海側の伯耆大山駅に至ります。
伯耆大山で山陰本線と合流し、米子に至ります。

伯耆大山駅より少し手前の、伯備線と山陰本線との合流点。(鳥取県)
特急「やくも」も、伯備線を経由します。
やくもは、山陽地方と山陰地方を速く結ぶ、重要な列車となります。
日野町の「金持神社」
なお、上記に少し出てきた根雨駅は、鳥取県の中国山地山深くの日野町の駅です。
日野町には「金持神社」という、なんとも縁起のよい名前の神社があります。
古くから貴重な「鉄」を取り出していた、日野川

日野川(南側)(山陰本線の車窓より)(鳥取県)
日野川では、歌詞にあるように、砂から鉄を取り出す「砂鉄の採取」が行われてきました。
砂鉄の採取は、天然の(鉄の混じった)砂から、鉄を取り出す技術です。
「鉄」は、そのままの状態で自然に存在しているわけではありません。
必ず、自然の砂や石などに(不純物が)混じり合った状態で存在しています。
そのため、自然の砂から鉄を取り出すために、日野川では「砂鉄の採取」が行われていました。
「鉄」は言うまでもなく、「鉄道」などに使われてきた重要な資源です。
日野川の場合は、この濁った水の中に、鉄を含んだ砂がたくさんあったわけですね。
「しのぶ」とは、「思い起こされる」などの意味を持つ言葉です。

日野川(北側)(山陰本線の車窓より)(鳥取県)
次回は、瓊子内親王・安養寺について
次は、後醍醐天皇の娘さん(皇女)であった、瓊子内親王の話題となります!

コメント