鉄道唱歌 山陽・九州編の歌詞(岡山・後楽園)について、鉄道に詳しくない方にも、わかりやすく解説してゆきます!
↓まずは原文から!
天下に三つの公園地
後樂園も見てゆかん
國へ話のみやげには
さらに読みやすく!
天下に三つの 公園地
後楽園も 見てゆかん
国へ話の みやげには
さあ、歌ってみよう!
♪てんかにみつのー こうえんちー
♪こうらくえーんも みてゆかんー
♪くーにへはなしの みやげにはー
神戸駅→兵庫駅→鷹取駅→須磨駅→舞子駅→明石駅→加古川駅→姫路駅→相生駅(旧・那波駅)→岡山駅→倉敷駅→福山駅→尾道駅→糸崎駅→三原駅→海田市駅→広島駅→西広島駅(旧・己斐駅)→五日市駅→宮島口駅→岩国駅→柳井駅→徳山駅→防府駅(旧・三田尻駅)
※鉄道唱歌に関係ある主要駅のみ表記
※鉄道唱歌のできた当時(1900年)は、防府駅(旧・三田尻駅)から先は開通していなかったため、徳山港から船で門司(九州)へ
岡山市を代表する庭園・後楽園
後楽園は、岡山市を代表する大きな庭園です。
後楽園と岡山城は隣接しているため、セットで観光するのがよいと思われます。
岡山の後楽園は、
- 石川県金沢市の兼六園
- 茨城県水戸市の偕楽園
とともに、日本三大庭園と呼ばれます。
回遊式庭園
このタイプの公園は、基本的に
- 公園の真ん中に、大きな池がある
- その池の周りには、柳や松などの、風流ある美しい木が、たくさん植えられている
- 池の周りを歩いて回りながら、鑑賞して楽しむ
ということが一般的です。
こうした公園のことを回遊式庭園といいます。
池田氏が観賞用に作った公園
岡山はもともと、池田氏という一族のお膝元でありました。
その池田さんが、街中に美しい観賞用の公園がほしいということで、岡山城のそばに造られたのが後楽園ということになります。
岡山の由来「小高い丘にある城」
なお、「岡山」の由来は、「岡山」という小高い丘に、岡山城が建てられていたことに由来します。

岡山城(岡山県岡山市)
他の二つの公園について
ここで、水戸の「偕楽園」と、金沢の「兼六園」についても少し解説しておきます。
水戸の偕楽園
水戸の偕楽園は、かつて水戸藩の9代藩主・徳川斉昭という方が「みんなで楽しもう」ということで作った、それが「偕楽園」です。
偕楽園とは、みんなで楽しむという意味です。
また、偕楽園は目の前の千波湖及び弘道館と並んで、梅の花の名所とも言われています。
偕楽園については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

金沢の兼六園
金沢の兼六園は、藩主の前田氏が金沢の街中に観賞用の公園を作るという意味で作られた公園です。
兼六園は、公園に必要な美しい要素を6つ兼ね揃えているので、兼六園と言われるわけです。
なお兼六園には、明治時代に金沢から西南戦争に向けて行った人をとむらうための、日本武尊(ヤマトタケルノミコト)の像があります。
兼六園については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

岡山藩の歴史
ここからは、江戸時代の岡山藩の歴史について語ってゆきます。
岡山藩は、関ヶ原の戦いで徳川家康の敵にあたる西軍についてしまったため、江戸時代に幕府から信用されずに冷遇を受ける、いわゆる外様藩だったのでした。
小早川秀秋の裏切りが評価され、岡山藩を与えられる
しかも、岡山藩の藩主には、関ヶ原の戦いで東軍の家康側に寝返ったことで有名な小早川秀秋も藩主についています。
しかし、2年ほどで亡くなっています。
なぜ小早川秀秋が岡山藩を安堵(分け与えられること)されたのか。
それは、関ヶ原の戦いの途中で自分たちの仲間に加わり、有益な情報を提供したことが評価されたからです。
※ただし、現代でこれをやると、不正競争防止法違反に!
ただし、この時の小早川秀秋はよかったですが、現代の実社会でこういうことをやると、
と、会社側からも疑心暗鬼されてしまうのが普通です。
そのため、この時の小早川秀秋は徳川家康からよく信頼されたなあ、と個人的には思ってしまいます。
※もちろん、みだりに会社にとって健全な企業活動を行うのに必要な情報を正当な理由なく公然と知らしめる行為は、法律違反になります。
注意しましょう。
(不正競争防止法)
話がややズレましたが、その後の岡山藩は、池田氏の一族による支配が、江戸時代全般にわたって続きました。
新田開発で、各藩で米の生産量を競うようになる
岡山藩は、後楽園の造営のみならず、いわゆる「新田開発」などを積極的に行い、これまでにない良質な田んぼを、どんどん作っていきました。
なぜかというと、簡単に言えば税収アップのためです。
税収といっても、当時はいわゆる米による「年貢」であり、また「石高」などで表されます。
当時の全国の藩は、大名同士でこの石高の量を競い合い、特に向上心ある意欲的な大名は、どんどん新田開発や農業の効率化に取り組みました。
加賀百万石・前田氏
もっとも石高の高かったのは、加賀百万石と言われた、金沢の前田氏の約103万石です。
そして、
- 薩摩の島津氏による、約75万石
- 仙台の伊達氏による、約62万石
と続きます。
加賀百万石については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。
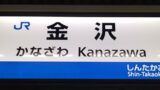
米沢を建て直した、上杉氏
また、現在の山形県米沢市にあたる米沢藩も、上杉鷹山公のもと、それまでの常識をくつがえすように、農民ならず武士にも農業のノウハウを教えるなどして、農業を発展させ藩の税収を上げる努力をしてきたのでした。
航路を使って運ばれた、全国の米
また、仙台藩も伊達氏の主導のもと、仙台で採れた大量のお米は、江戸時代にできた「東廻り航路」を使って、太平洋側の海を通って江戸の街で大量に消費され、仙台藩は大きな利益を上げていました。
この当時は「東廻り航路」「西廻り航路」など海を使った貨物輸送が発展したため、自分の領地だけでなく他の地域により多く販売する(販路を拡大する)ことが(それまでと比べて)容易になっていたのです。
とはいえ、当時は「舟で運んでいる途中に米が海水にさらされて、ダメになった」などの問題も依然と多かったようです。
江戸時代の新田開発
さらに江戸時代には、新しい農業の技術が次々に開発され、より効率的に農業ができるようになりました。
岡山では、「備中鍬」が有名ですね。
江戸時代には戦争のない平和な世の中だったため、非常に人口が増えました。人口が増えると、多くの米や食料も必要になります。
そのため、江戸時代には饑饉や自然災害もあったでしょうが、こうした苦難を乗り越えて、現代の我々が安全に、安く、大量にお米を食べられることに繋がっているのです。
現代と今後の農業の課題
もっとも、現代では少子高齢化による農業の後継者不足から、AIやドローンなどを使った農業の自動化・可視化や、ITを使った農業の効率化などのノウハウも考え出されています。
あなたの「かしこさUP」に
だいぶ話がズレてしまい、鉄道旅行や鉄道唱歌の話題とは関係ないこともたくさん話ましたが、少しでも皆さんの「かしこさUP」「教養力アップ」に繋げていただけたならば幸いです。
次は、香川県や瀬戸内海、そして金刀比羅宮についての話題をしていきます!

コメント