鉄道唱歌 関西・参宮・南海編の歌詞を、わかりやすく解説してゆきます!
造幣局の歴史などを、初心者にもやさしく解説してゆきます!
↓まずは原文から!
櫻の宮の夕すゞみ
なごりを跡に見かへれば
城の天守も霞みゆく
さらに読みやすく!
桜の宮の 夕すずみ
なごりを跡に 見かえれば
城の天守も 霞みゆく
さあ、歌ってみよう!
♪さくらのみやのー ゆうすずみー
♪なごりをあーとに みかえればー
♪しろのてんしゅも かすみゆくー
大阪城北詰駅(網島町)→京橋駅
(片町線(学研都市線))
京橋駅→放出駅→徳庵駅→住道駅→四條畷駅→星田駅→津田駅→祝園駅→木津駅
※鉄道唱歌に関係ある主要駅のみ表記
※網島駅、旧桜ノ宮駅は1913年に廃止
※現在の駅で最も近いものに置き換えてあります
網島を主発し、造幣局や大阪城の近くへ
前回説明した網島からは、大川の向こう岸に、造幣局が存在します。
「造幣局」とは?
造幣局とは、簡単にいえば「お金を作る場所」です。
お金といっても、いわゆる「100円玉」「500円玉」などの硬貨を造る場所になります。
ちなみに「お札」を造っている場所は、造幣局ではなく、
- 「日本銀行」
- 「国立印刷局」
になりますので、注意しましょう。
お札のことを「日本銀行券」といったりしますよね。
なぜ造幣局が、大阪に存在することになったのか?
なぜ造幣局が大阪にあるのかについては、様々なことが考えられます。
例えば、「かつての天下の台所だったこと」などが理由として考えられます。
しかしそれだと、今度は「なぜお札を作る日本銀行が、東京にあるの?」という話にもなってきます。
災害時のバックアップ(BCP)のため?
もしかしたら、大規模災害時のバックアップ機能(BCP)としての役割を持っていたのかもしれません(※)。
もし「造幣局」も東京に存在し、しかも東京で大災害が起きてしまったとき、「硬貨」「お札」の両方を造る機関が、どちらも破綻してしまいす。
すると、全くお金を作れなくなってしまい、ニセ札・ニセ硬貨などが横行しまう、といったリスクがあることも考えられます。
そのため、東京と大阪でリスクを分散した・・・などの理由を考えたのですが、違っていますかね(^^;)
※BCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)とは、もし災害が起きたとしても、なんとか事業を継続的させ、また災害の復旧を行っていくための計画をいいます。
あと他にも、1871年の発足時に「東京での治安が、まだ落ち着いてなかったから」などの理由も色々考えられるそうです。
当時はまだ幕末の動乱の余波が消えてなかったんでしょうかね。
網島の向こう側に存在する、造幣局
造幣局は、前回説明した網島の(川を挟んで向こう岸にあります。
造幣局からは、歌詞にあるように大阪城の天守の綺麗な景色が見えることになります。

網島(大阪府大阪市都島区)
「網島」とは?
網島は、寝屋川と、大川という川に囲まれている島になります。
もちろん、島というような島ではありませんが、昔は川と川に挟まれた土地のことを「島」と呼んでいたのでした。
例えば
- 長野県の「川中島」
- 広島県の「広島」
も、それぞれ名前の由来は似ています。
「京橋」の由来
網島と大阪城は寝屋川を挟んで、「京橋」という橋によって結ばれています。
これが、京橋駅(大阪府大阪市都島区・城東区)をはじめとする「京橋」の地名の由来です。
NTT西日本の本社も存在
京橋のやや西には、NTT西日本(西日本電信電話株式会社)の本社もあります。
NTT(日本電信電話株式会社)も、
- JR(日本旅客鉄道株式会社)
- JT(日本たばこ産業)
と同じで、「三公社五現業」の1つです。
なお、先ほど述べた「造幣局」を含む、
- 造幣局
- 国立印刷局
- 郵便
- 国有林
- アルコール専売
などは、「五現業」の中に含まれます。
NTTも、元々は国鉄(日本国有鉄道)と同じように、「電電公社(正式名称は日本電信電話公社)」と呼ばれていました。
しかし1985年に民間に分割され、NTTとなっています。
東京にも存在する「京橋」
「京橋」は、東京にも存在する地名です。
もっといえば、「日本橋」も東京・大阪の両方にあります(読み方は異なる。
このように、「橋」が由来の地名は、東京や大阪(特に大阪)には多く存在します。
江戸時代は「水の都」として栄えた、大坂や江戸
それは、江戸も大坂も、江戸時代には町中に舟が通るための運河や堀が張り巡らされていた「水の都」だったことが理由です。
そのため、多くの橋がかけられていました。
「舟」がメインだった江戸時代 町中に多くの「運河」「お堀」がめぐらされた
江戸時代には、
- 物を大量に運べるトラック
- 人を大量に運べる路線バス
などが無かったため、舟で大量にモノや人を運んだ方が、効率がよかったのでした。
しかし、明治・大正・昭和になるにつれて、列車や自動車の普及により、水路は用済みとなって衰退したのでした。
そのため、その多くはほとんど埋め立てられており、存在しません。
現在でも残る「運河」は
その跡地は道路などになって活用されています。
北海道小樽市の小樽運河のように、現代でも残っているケースも存在します。
詳しくは、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

東京・大阪における「~橋」の地名の例
東京では
- 「日本橋」
- 「京橋」
- 「新橋」
とあり、このうち「京橋」「新橋」は、川が埋め立てられてしまっています。
そのため、現在は跡(遺構)が残るのみであり、橋そのものは存在しません。
東京の「日本橋」
「日本橋」は、東海道と、中山道の起点です。
南は東海道、北は中山道となり、はるか西の滋賀県草津市・草津宿で合流します。
大阪の「日本橋」
なお、
- 東京では「にほんばし」
- 大阪では「にっぽんばし」
といいます。
なので、略して「ポンバシ」などと親しみを込めていうと、これは大阪の日本橋のことになります。
ポンバシの「オタロード」
ポンバシには「オタロード」と呼ばれるアニメ・ゲーム・メイドカフェなどを中心とする通りがあります。
東京でいう秋葉原みたいな位置づけのイメージです。
東京の「新橋」
「新橋」は、言うまでも無く1872年に日本で初めて鉄道開業した街です。
詳しくは、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。
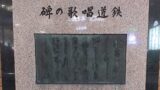
東海道五十七次のゴール地点となった、高麗橋
京橋のさらに西には、高麗橋という橋があります。
高麗橋は、東海道五十七次のゴールになります。
「東海道五十三次」と「東海道五十七次」の違い
東海道五十三次は、江戸~京都を結ぶ途中で53の宿場町があった江戸時代の道路です。
これを大坂まで延伸し、さらに4つの宿場町を付け加えたものが、東海道五十七次になります。
そのゴールが高麗橋というわけです。
江戸時代の人々には鉄道や航空機などはありませんでした。
そのため、こうした街道を20日以上もかけて、宿場町に泊まりながら歩いてきたのです。
山科の「髭茶屋追分」から、東海道と分岐
東海道五十七次は、京都の山科の髭茶屋追分という分かれ道から、東海道と南西へ分岐して、大阪の高麗橋に至ります。
東海道五十三次は、髭茶屋追分からそのまま西へ進み、三条大橋でゴールとなります。
東海道五十七次(京街道)は、京阪本線のルートにも準拠
また、東海道五十七次(京街道)は、
- 「守口」
- 「枚方」
などを通るため、現在の京阪本線に並行して進む街道になります。
次は、放出駅へ
京橋駅を過ぎると、次は放出駅に止まります!

コメント