中央線鉄道唱歌の歌詞を、わかりやすく解説してゆきます!
小金井の地理・歴史などを、やさしく解説してゆきます!
↓まずは原文から!
都少女がたもとほり
花狩りくらす小金井は
關東一の名所かな
さらに読みやすく!
都少女が たもとおり
花狩りくらす 小金井は
関東一の 名所かな
さあ、歌ってみよう!
♪みやこおとめがー たもとおりー
♪はなかりくーらす こがねいはー
♪かんとういちのー めいしょかな
飯田橋駅→市ヶ谷駅→四ツ谷駅→信濃町駅→新宿駅→大久保駅→中野駅→荻窪駅→吉祥寺駅→武蔵境駅→武蔵小金井駅→国分寺駅→立川駅→日野駅→豊田駅→八王子駅→高尾駅
※鉄道唱歌に関連する主要駅のみ表記
※現代の中央線の起点は東京駅
※飯田橋駅は、当時は飯田町駅と牛込駅に別れていた
花の名所・小金井市へ 栃木県にも同じ「小金井」がある!?
武蔵境駅(東京都武蔵野市)を過ぎると、
- 東小金井駅(東京都小金井市)
- 武蔵小金井駅(東京都小金井市)
の順に進んでゆきます。
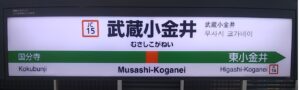
武蔵小金井駅(東京都小金井市)
かつて「桜の名所」と呼ばれた、小金井
小金井は、かつてより「花の名所」と呼ばれてきました。
他にも、
- 茨城県桜川市の岩瀬
- 奈良県の吉野山
など、こうしたところが桜の名所です(もちろん全国他にもたくさんあります)。
東京都小金井市には、後述するように桜の名所の小金井公園があります。
小金井の由来は、
などの意味から来ています。
水不足が多かった昔は、水が湧き出る場所(井戸)はとてもありがたかった
昔は、現代と違って、いつも水不足で困っていました。
そのため、
- まるで、水が「金のよう」に出る井戸
の存在は、とてもありがたく嬉しかったというわけですね。
一方、現代では、たとえ日照りで水不足に陥っても、ダムや溜池などから、水を補填することができます。
ちなみに、栃木県にも
- 小金井駅(栃木県下野市)
という駅があります。
こちらは、東京都の武蔵小金駅の方が後にできたため、重複を回避する必要がありました。
そこで、旧国名である「武蔵国」の名前を冠して、武蔵小金井ということで、重複を避けたのだと思います。
かつて「桜を見に行くための駅」として開設された、武蔵小金井駅
現在の武蔵小金井駅は、
- 明治時代に、小金井の桜が有名になって観光名所となったため、
- そのときに、お花見の季節限定で開設された、仮のプラットホームが原型
となります。
つまり、
- お花見のために、後述の小金井公園まで歩いていくために、
- 列車を乗り降りするためのスペースを確保したこと
が、現在の武蔵小金井駅の原型になっています。
小金井駅より北へ1kmほどいくと、歌詞にもある桜の名所である、「小金井公園」に着きます。
歌詞によれば、鉄道唱歌の当時(明治時代)には小金井公園は
- 「関東一の名所」
と呼ばれていたようですね。
小金井が「花の名所」になった理由 玉川上水と、桜の関係
では、なぜ小金井が関東一の名所になったのか。
それは、現在の小金井公園のすぐ南を流れる、玉川上水に植えられた大量の桜にありました。
玉川上水とは?
玉川上水とは、江戸時代にできた、江戸の町に人々の生活に必要な飲み水を供給するための、人工的な川のことです。
上水とは、人々の生活に必要な水のことであり、対義語は下水になります。
その水の源は、東京都西部の多摩川です。
- 東京都羽村市の羽村取水堰から水を取り出し、
- 玉川上水として、東京都新宿区の四ッ谷まで流れて、
- そこから江戸・東京都民にとって不可欠な用水となって、供給されている
というわけです。
玉川上水の源・羽村取水堰については、以下の記事でわかりやすく解説していますので、ご覧ください。

かつて玉川上水の脇に、たくさん植えられた桜
その玉川上水の脇に、たくさんの桜が植えられたわけです。
その理由は、昔は、
と人々に信じられていたからです。
また、桜をたくさん植えることで、観光名所になります。
さらに、またお花見にきた人々が、
- 玉川上水の土手や堤の地面を踏むことで、地面を固めてくれる
という効果を期待したものでもありました。
吉野(奈良県)や桜川(茨城県)から、大量に呼び寄せられた小金井の桜
こうして玉川上水にたくさん植えられた桜ですが、中でも小金井のものが特に有名になったのでした。
小金井の桜は、
- 奈良県の吉野
- 茨城県桜川市
から取り寄せたものでした。
当時としてはとても珍しい桜だったため、多くの人々が小金井の桜を見ようとしたのでした。
明治時代~大正時代にかけて、小金井の桜は鉄道唱歌の歌詞にあるように、関東一の名所になったのでした。
小金井にある、高橋是清の邸宅
小金井公園には、高橋是清の邸宅があります。
高橋是清は戦前の1930年代の総理大臣であり、「二・二六事件」で殺されてしまった人物でもあります。
そもそも、二・二六事件とは?
二・二六事件とは、現代でいうと
「自衛隊が国を裏切って、政府を攻撃した」というようなとんでもない事件です。
つまり、「クーデター」の一種です。
もっと正確に言うと、
- 大日本帝国憲法の通りに、天皇による政治を推し進めたいというグループである「皇動派」
- 天皇ではなく、軍部で政治を推し進めたいというグループである「統制派」
の対立から起きた事件です。
1930年代の日本 大日本帝国憲法の時代とは、大きく変わっていた
1930年代の日本は、
- 「天皇と政府、偉いのはどっちだ」
と世論が二分していました。
例えば、1931年の「満州事変」は、天皇の意思決定ではなく、あくまで軍部が勝手に暴走して行われたことだからですね。
また、満州事変をきっかけに、1932年に「満州国」という日本の操り人形のような国を作ったのも、天皇の意思決定ではなく、軍部の暴走によるものです。
さらに1930年の「ロンドン海軍軍縮条約」では日本の軍艦の保有数は欧米列強の7割と決められてしまい、しかもそれも天皇の決定ではなく、政府の決定でした。
大日本帝国憲法の「天皇主権」は、 1930年代には、もはや時代にそぐわなくなっていた
大日本帝国憲法下では、「天皇は神聖不可侵」であり、天皇が全ての意思決定をできるほど、天皇が一番偉いという位置付けのはずでした。
しかし当時の昭和天皇は、「天皇機関説」といって、
- 「天皇は君臨こそするが、統治はしない」
というスタンスを取っていました。
つまりこれは、現代の日本や、欧米諸国などと同じというわけです。
そのため、この時の昭和天皇は、直接政治をしない・口を出さないというスタンスを貫きました。
天皇主権を貫きたいグループ「皇道派」と、より穏和的に新しい時代に変えたい「統制派」というグループで対立
しかしこれに納得できないのが、大日本帝国憲法を忠実に守り、「天皇主権」を重んじよう、としている人々です。
彼らのことを「皇道派」といいます。
ここで、
- 皇道派は、どちらかというと武力をもって解決したいという、過激なグループ
- 統制派は、あくまで穏やかな方法で、物事を解決したいというグループ
でした。
皇道派がついに「政府を攻撃する」という クーデター「2二・二六事件」が勃発
そして、
- そんな「皇道派」の人達(特に「青年将校」という、若いエリート達)が、
- 天皇を差し置いて、政治をやろうとする政府を攻撃すべく、
- 1936年2月26日に起こしたクーデターが、二・二六事件である
というわけです。
二・二六事件により、首相は殺害され、国会がある永田町は占拠された
これにより、当時の総理大臣だった高橋是清は殺されてしまい、しかも国会議事堂などがある永田町や、霞ヶ関などの政府の主要機関などは、占拠されてしまいました。
現代でいうと、これは自衛隊が政府機関を攻撃して、占拠するようなものです。
考えただけで恐ろしいですよね。
昭和天皇がストップを呼びかけたことにより、反対派は降伏・事件は終了
しかし昭和天皇は、
と、この事件に対して激怒します。
元々は天皇主権を復活させるために、皇道派たちははクーデターを起こしたのでした。
しかし、逆に天皇から怒られるという始末でした。
昭和天皇にとってこの事件は、いわゆる「ありがた迷惑」だったわけですね。
結局クーデター側は投降し、二・二六事件は失敗に終わります。
なんか全然関係ない話題になったかもしれませんが、少しでも皆様の何かの参考になれば幸いです。
太宰治が生涯の最後を過ごした、東京都三鷹市
あと前回触れられなかった、東京都三鷹市について触れておきます。
東京都三鷹市は、私が好きな小説家である太宰治が最後に暮らした町であり、またその生涯を終えた街でもあります。
太宰治がその生涯を終えた、三鷹市の玉川上水
生まれつき精神的に弱かった太宰治は、それまで5回ほど自殺未遂を繰り返していました。
しかも愛人の女性と一緒に自殺するはずが、愛人だけ死んで自分は生き残るということもありました。
その度重なる自殺未遂が、ようやく「完遂」となったのが、三鷹駅のすぐ隣にある「玉川上水」という場所です。
「玉川上水」とは、先述したように、東京の街に飲み水を提供するために作られた、人工的な川です。
玉川上水は、先述の小金井市だけでなく三鷹市をも経由しており、現在の三鷹駅のそばを流れているというわけです。
太宰治は1948年6月13日に玉川上水へまたまた愛人の女性と飛び込み、38歳の若さで亡くなりました。
小説「グッド・バイ」を書き残したまま、玉川上水でこの世を去った
ちなみにこの時、遺作となった「グッド・バイ」という小説を書いている途中でした。
「グッド・バイ」は、太宰治が「人間失格」の後に書いていた小説です。
しかし書いている途中で太宰治は自殺したため、未完の(途中までの)作品となってしまいました。
しかし、そんな時期に書かれたとは思えないほど、ジョーク混じりのとても明るい作品となっています。
もしよければ、読んでみてください。
次回は、国分寺駅へ
以上、今回はとにかく話がズレてすみませんでしたが、次は国分寺に止まります!

コメント