中央線鉄道唱歌の歌詞を、わかりやすく解説してゆきます!
塩山(甲州市)・恵林寺の歴史などを、やさしく解説してゆきます!
↓まずは原文から!
温泉に遊ぶ夕間ぐれ
晩鐘ひゞく惠林寺は
夢窗國師の大伽藍
さらに読みやすく!
温泉に遊ぶ 夕間ぐれ
晩鐘ひびく 惠林寺は
夢窓国師の 大伽藍
さあ、歌ってみよう!
♪いでゆにあそぶー ゆうまぐれー
♪ばんしょうひびく えりんじはー
♪むーそうこくしの だいがらんー
高尾駅→相模湖駅→上野原駅→四方津駅→鳥沢駅→猿橋駅→大月駅→初狩駅→笹子駅→(笹子トンネル)→甲斐大和駅→塩山駅→山梨市駅→石和温泉駅→酒折駅→甲府駅
※鉄道唱歌に関連する主要駅のみ表記
広大な甲府盆地へ
甲斐大和駅を出て、笹子トンネルに続くもう1つの長大トンネルを出ると、窓の左側には広大な「甲府盆地」が姿を現します。
そして、窓に広がる「広大なブドウ畑」も姿を現します。
日本一のフルーツ大国・やまなし
山梨県は、ブドウの生産量が日本一です。
また、桃の生産量も日本一です。
そのため、山梨県は「フルーツ王国」とも呼ばれます。
ブドウの生産量が日本一のため、「甲州ワイン」も人気です。
勝沼ぶどう郷駅に到着
やがて、ブドウの産地の最寄駅である
- 勝沼ぶどう郷駅(山梨県甲州市勝沼町)
に着きます。
「くだもの名」と「地名」が入った駅名
勝沼ぶどう郷駅は、開業当初は「勝沼駅」でした。しかし1993年に現在の「くだもの名と地名が入った駅名」に変更されました。
ちなみに、さくらんぼ生産量日本一の山形県にも
- さくらんぼ東根駅(山形県東根市)
という、「くだもの名と地名を掛け合わせた駅」があります。
勝沼ぶどう郷駅にかつて存在したスイッチバック
また、勝沼ぶどう郷駅は現在のように(塩山駅に向かって)「急な下り坂の上」にあるため、昔は駅に列車が停車する際に下に滑り落ちないように、「スイッチバック」の形式でした。
スイッチバックとは、「人」の形をした線路のことです。スイッチバック駅では、以下の手順で列車は動きます。
- 一旦先頭から、線路分岐したホームに突っ込む
- 平らな駅のホームで、乗客を乗り降りさせる
- 終わったら、バックして坂のきつい本線に戻る
- 再び前へ発車して、坂を登っていく
という方式です。
なぜスイッチバックが設けられていたのか
スイッチバックが設けられていたのは、
- 坂が急なところにある駅においては、列車が滑り落ちないよう、別途で「平らな場所」に、ホームを設けるため。
- 線路が1本しかない単線だった時期に、列車がすれ違うための「退避スペース」としての役割を設けるため。
などでした。
時代とともに、スイッチバックは廃止
時代とともに車両の性能が向上し、また2本の線路からなる複線になると、退避スペースが不要となってきます。
そのため、1968年に勝沼駅のスイッチバックは不要になって廃止となり、現在ではきつい坂道にホームがあります(それで問題なくなっています)。
また、勝沼駅のスイッチバック時代の旧ホームは、現在では公園として整備されていて、自由に散策することができます。
塩山駅に到着
勝沼ぶどう郷駅を過ぎると、やがて
- 塩山駅(山梨県甲州市)
に着きます。
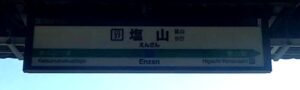
塩山駅(山梨県甲州市)
かつては「塩山市」の駅 現在は甲州市
塩山駅は、元々はその名の通り塩山市の駅でした。
塩山市は、2005年に親設合併して甲州市となり、塩山駅は現在は甲州市の中心駅になります。
山梨県は、「甲」のつく地名が多い
山梨県は、かつて「甲斐国」と呼ばれていたので、「甲」がつく自治体が多くなります。
- 右側:甲州市(塩山駅のあるところ)
- 中央:甲府市(県庁所在地)
- 左側:甲斐市(竜王駅のあるところ)
ちょっと強引な暗記方法
土地勘がないと(地元民でもないかぎり)なかなか覚えるのは難しいですが、
- 甲州市は「こう”し”ゅう」であり、
- ”し”の文字が、右側を向いている
ため、地図上で右側にあるのが「甲州市」だと覚えましょう。
これは簿記における貸借対照表において、右側は貸方(か”し”かた)なので、
- 「”し”は右側を向いてるため、右側」
という覚え方と同じものを、応用させてもらいました。
ちょっと無理のある暗記方法ですかね(^^;)
歌詞「海の幸ある塩山」とは?
歌詞では、
- 「海の幸の塩」というフレーズと、
- 「塩山」という地名
を掛けてるのだと思います。
いわゆる、掛詞と呼ばれるものです。
夢窓疎石(夢窓国師)が建立した、恵林寺
恵林寺は甲州市にあるお寺で、夢窓疎石の建てたお寺になります。
恵林寺は、塩山駅から北へ徒歩約1時間の距離に存在しています。やや遠いため、天気のよい日に散歩がてら向かわれる方もいるようです。
鎌倉終わり~南北朝に活た、夢窓国師
夢窓疎石は、歌詞のように夢窓国師とも呼ばれます。
夢窓疎石は、鎌倉幕府の滅亡から南北朝の対立といった、世の中がカオスな状況の中で生まれました。
そうしたことから、「どこか人里離れた山の中で、戦乱なんか関係なく、ひっそりと暮らしたいなぁ」という願望を持ちつつ、あちこちの地方を布教しながら回ったのでした。
その弟子の数は、なんと一万人もできていたといいます。
そして夢窓疎石は、後醍醐天皇らをはじめとする実に7人もの天皇から厚い信頼を受けたのでした。
そして、臨済宗において非常に尊い称号である「国師号」を授かりました。
なので「夢窓国師」と呼ばれるわけですね。
武田信玄と、快川和尚
戦国時代に入ると、甲斐国の「戦国最強の武将」と言われた武田信玄は、恵林寺の快川和尚と、まるでよき友人のように信頼関係を深めてゆき、恵林寺は発展していったのでした。
やがて武田信玄は、恵林寺を自らの霊廟とし、武田氏の菩提寺と定めました。
霊廟とは、高貴な武将のお墓のことです。
菩提寺とは、ある一族が祀られているお寺のことです。
武田家の滅亡とともに、恵林寺は包囲される
武田信玄が1573年に亡くなり、また息子の武田勝頼が1582年に天目山で織田信長によって滅ぼされると、恵林寺は織田軍に包囲されてしまいます。
織田軍は、恵林寺を包囲し、火でめった打ち・焼き討ちにし、100人余りが容赦なく殺されたといいます。
「心頭滅却すれば、火もまた涼し」
快川和尚も炎の中で、
という言葉を残して亡くなりました。
これは心を完全に「無」にすれば火なんて全然熱くない、というある種の「悟り」に近いものです。
これが転じて、
- 「どんな苦しい状況におかれても、精神を落ち着かせれば、怖くない」
という意味になります。
虎渓山永保寺を建立した、夢窓疎石
夢窓疎石は、岐阜県多治見市の虎渓山永保寺を建てた人でもあります。
多治見市における虎渓山永保寺については、以下の記事もご覧ください。

次は、山梨市へ
塩山駅を出ると、次は山梨市に止まります!

コメント