中央線鉄道唱歌の歌詞を、わかりやすく解説してゆきます!
酒折宮・日本武尊・甲斐善光寺の歴史などを、やさしく解説してゆきます!
↓まずは原文から!
夜には九の夜日には又
十日重ねし旅衣
酒折の宮はかしこしや
さらに読みやすく!
夜には九の夜日には又
十日重ねし旅衣
酒折の宮はかしこしや
さあ、歌ってみよう!
♪よーにはここのよ ひにはまたー
♪とーおかかさねし たびごろもー
♪さこりのみやはー かしこしやー
高尾駅→相模湖駅→上野原駅→四方津駅→鳥沢駅→猿橋駅→大月駅→初狩駅→笹子駅→(笹子トンネル)→甲斐大和駅→塩山駅→山梨市駅→石和温泉駅→酒折駅→甲府駅
※鉄道唱歌に関連する主要駅のみ表記
酒折駅(甲府市酒折)に到着
石和温泉駅を出て、酒折駅へ
石和温泉駅(山梨県笛吹市)を出ると、甲府駅がだんだんと近づいてきます。
そして甲府駅の少し手前、
- 酒折駅(山梨県甲府市酒折)
に到達します。

酒折駅(山梨県甲府市酒折)

酒折駅(山梨県甲府市酒折)
日本武尊ゆかりの地・酒折宮へ
今回の歌詞はちょっと難しいですが、
- 酒折駅の少し西に存在する酒折宮
- 神話の時代に、酒折宮を訪れたヤマトタケルノミコト(日本武尊)
の話題となります。
「東夷」とは?
歌詞にある東夷とは、いわゆる
- 奈良(大和朝廷)からみて、東の国(主に関東地方)にいた、朝廷に従わない人達
のことをいいます。
日本武尊(ヤマトタケルノミコト)とは?なぜ東国へ遠征したのか?
日本武尊は、父の第12代天皇・景行天皇に命じられ、関東地方(東国、板東とも)の征伐に向かいます。
景行天皇とは?
ここで景行天皇とは、第12代天皇です。
飛鳥時代の推古天皇が第32代なので、相当昔の天皇であることは間違いないです。
ちなみに参考までに、
- 令和の天皇陛下(今上天皇)は、第126代である
- 日本の初代天皇は神武天皇である
になります。
神武天皇は紀元前660年2月11日に奈良県橿原市において即位したので、2月11日は「建国記念日」とされています。
東国遠征を終えた日本武尊
日本武尊の東国遠征については、以下の各記事でもわかりやすく解説しているため、ご覧ください。


大和国(奈良県)に帰る途中で、山梨県のこの地に立ち寄った
関東地方の征伐を無事に終えた日本武尊は、茨城県を出発して、奈良県の大和朝廷に帰る途中だったのでした。
そのときに立ち寄った場所が、まさしく山梨県甲府市の酒折宮だった、ということになります。
坂折宮において詠んだ歌「連歌」のはじまり
日本武尊がここ酒折宮に辿り着いたとき、尊は
と、まるで独り言のように歌を詠みました。
すると、たまたま隣にいた翁が、
というアンサーソングを、絶妙なタイミングで歌で返しました。
※実際にはこのような今風の言葉ではなく、昔の古語による五・七・七の歌になります。
これはいわゆる「連歌」のはじまりであり、酒折宮は「連歌発祥の地」と呼ばれます。
- 「五・七・七」の歌に対して、
- 別の人が「五・七・七」の歌で返し、
- それを交互に返しながら歌う
という遊びです。
前回も説明したように、平安時代は「朝廷」といって、貴族の皆さんは
- 朝早くに出勤し、
- 昼までには公務を終え、
- 午後は歌を詠んで遊ぶ
などの優雅な生活を送っていました(その代わり、土日休みは無し)。
そのため、天皇や貴族をはじめ、武将らにとっても「歌遊び」というものは、とても重要だったのです。
ちなみに、歌の原文は
「新治筑波を過ぎて 幾夜か寝つる」
「かがなべて 夜には九夜 日には十日を」
になります。
それぞれ五・七・七の歌であり、五・七・五・七・七ではないことに注意する必要があります。
「かがなべて」とは、「日を重ねて」という意味です。
「新治(にいはり)」とは?
ちなみに「新治」とは、恐らくですが、現在の
- 茨城県筑西市
- 茨城県桜川市
あたりの地域ではないかと思われます。
JR水戸線に、
- 新治駅(茨城県筑西市)
- 大和駅(茨城県桜川市)
という名前の駅があります。
そのため、恐らくこの辺りの地域が、ヤマトタケルノミコト(日本武尊)のゆかりの地(出発の地、訪れた地)ではないかと思われます。
なお、茨城県かすみがうら市にも「新治」という地名があります。
ただし、こちらは恐らく無関係だと思われます。
したがって、新治は、関東(または板東、東国)を征伐した尊が地元の大和(奈良県)へ戻ろうと出発した(過ぎていった)、茨城県の場所ということになります。
水戸線とは?
先述の水戸線とは、
- 小山駅(栃木県小山市)
- 友部駅(茨城県笠間市)
とをそれぞれ結ぶ路線です。
水戸線については、以下の記事でもわかりやすく解説していますので、ご覧ください。
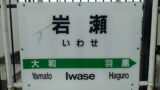
身延線と合流、甲府駅へ
酒折駅を出ると、身延線の線路が左側から徐々に迫ってきて、やがて合流します。
身延線とは?
ちなみに身延線とは、甲府駅を南へ進み、はるか南の静岡県富士市へと至る路線です。
身延線は、富士川沿いに進み、日蓮宗の総本山である身延山・久遠寺の沿線も通ります。
身延線が出来るまでは、富士川の上を舟でこぎ、人々や荷物を載せて運んでいたのでした。
身延線については、以下の各記事でも解説していますので、ご覧ください。
↓↓前編

↓↓後編

甲斐善光寺
そして、甲斐善光寺の近くを通ります。
そもそも「善光寺」とは?
善光寺は、本来は長野県長野市にあるものが本場です。
長野の善光寺の本尊は、「日本で最も古い仏像」といわれています。
また、誰も見ることができない「絶対秘仏」とされています。
ちなみに奈良の「法隆寺」は、「日本で最も古い木造建築のお寺」となります。
そのため、間違わないようにしましょう。
秘仏とは?
ちなみに秘仏とは、いわば見てはいけない仏様、ということになります。
秘仏は壁と扉によって仕切られており、厳重に管理されています。
まるで「三種の神器」を、天皇陛下すら見ることができないのと似ていますね。それだけ神聖である、ということです。
善光寺を中心に栄えてきた、長野県長野市
長野県の県庁所在地・長野市は、善光寺を中心に栄えてきた町なので、現在の善光寺は長野市にとっては欠かせない観光地でもあります。
長野の善光寺については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

戦国時代、様々な大名の手に渡った、善光寺の仏像
この長野の善光寺の仏像(善光寺如来)が、戦国の世の中において何度も場所を移されたのでした。
その際に、武田信玄によって信州(長野)から甲斐国(山梨県)に持って来られたのが、この甲斐善光寺です。
長野から地元・山梨まで、仏像を移してきた武田信玄
武田信玄は、善光寺平(長野市がある平野のことです)が戦場となってしまったときに、
- 上杉謙信の手から(仏像を)守る
という名目で、自分の地元である甲斐国(現在の山梨県)のこの地に、善光寺如来の仏像を移してきたのでした。
長野(信濃)の善光寺も、「川中島の戦い」によって荒れ果ててしまいました。
武田信玄は、甲斐国にこの仏像を持ってきたことで、まるで
という雰囲気もあったことでしょう。
上杉謙信も、地元・新潟へ仏像を移した?
しかし、上杉謙信も地元の新潟県上越市の浜善光寺に、この仏像を移したという説もあります。
織田信長も地元・岐阜へ、徳川家康も地元・静岡に移した?
また、1582年に武田勝頼が織田信長に滅ぼされた後、仏像は織田氏によって地元の美濃国(現在の岐阜県)に移されました。
また、その後再び徳川家康によって、地元の遠江国(※)に移されたりしました。
※遠江国:現在の静岡県浜松市あたりであり、家康が若いころの本拠地です。
あちこちへ移された「仏像」の祟り?
しかし、織田氏が美濃国に仏像を移した後に「本能寺の変」が起こってしまいました。これは
という噂が広がってしまったのでした。
また、
という噂まで立つようになりました。
これに恐怖した家康は、焦って甲斐善光寺へと、仏像を戻したといいます。
ついには秀吉までもが、仏像を地元・関西へ移動させる
そしてその後、1597年に豊臣秀吉によって、甲斐善光寺から京都の方広寺に移されました。
これは、方広寺が(前年の1596年に起きた)地震の被害に遭い、「京の大仏」が破損してしまったのでした。
その代わりに
- 「威厳ある仏様をお招きしたい」
という秀吉の意向によって、善光寺如来を移動させたのだとされています。
しかし「元々は大仏の置いてあった大きな台」に対し、サイズ的には小さい善光寺如来の仏像を置いたことには、どうも違和感があり、かなり馬鹿にされたとも言われています。
呪いに焦った秀吉 長野へ戻すも・・・
しかし翌年の1598年に、豊臣秀吉は病に倒れてしまいました。
これは
と噂されるようになりました。
挙げ句の果てには、秀吉は仏像が
と言い出す夢まで見てしまうという始末でした。
これに恐怖し焦った秀吉は、仏像を長野市の信濃善光寺に戻すことに決めました。
これにより、仏像は約30年ぶりに、長野市の信濃善光寺まで戻って来ることになりました。
しかし焦って仏像を返却したにも関わらず、秀吉はそのまま1598年に病死してしまいました。
結局30年間、あちこちへ「引っ越し」させられてしまった仏像
この実に30年もの間、善光寺如来の仏像は様々な武将たちによって、各地を転々と「引っ越し」していたことになります。
善光寺の仏像はなにせ「秘仏」であり、天皇家における「三種の神器」と同じくらい神聖なアイテムとなります。
つまり、これを持っている者や国は絶対的神聖権力者である、と主張したくなる気持ちもわかります。
戦国の世の中は「負け=死」ですから、みんななりふり構っていられなかったわけですね。
次回は甲府駅に到着
話が長くなりましたが、次でいよいよ甲府に着きます!

コメント