中央線鉄道唱歌の歌詞(洗馬・贄川・奈良井、木曽路など)について、鉄道に詳しくない方にもわかりやすく解説してゆきます!
↓まずは原文から!
洗馬や贄川奈良井宿
驛路の鈴の音絶えて
汽笛は響く木曾の谷
さらに読みやすく!
洗馬や贄川 奈良井宿
駅路の鈴の 音絶えて
汽笛は響く 木曽の谷
さあ、歌ってみよう!
♪せーばやにえかわ ならいじゅく
♪えきろのすーずの おとたえてー
♪きてきはひびくー きそのたにー
塩尻駅→洗馬駅→贄川駅→奈良井駅→藪原駅→宮ノ越駅→木曽福島駅→上松駅→須原駅→野尻駅→南木曽駅→坂下駅→中津川駅
※鉄道唱歌に関連する主要駅のみ表記
塩尻駅を南西へ進み、木曽路・中央西線へ
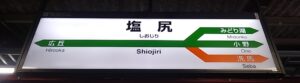
塩尻駅(長野県塩尻市)
塩尻駅(長野県塩尻市)を出ると、ここからは南西へと向かう、中央西線となります。
すなわち、木曽路を通って、名古屋方面へ向かってゆくことになります。
険しい木曽路へ 買い物は事前に済ませる
これからは、険しい木曽路に入ってゆくことになります。
中央西線は、普通列車も2~3時間に1本しか存在していません。
また、途中の木曽福島駅までは、あまり買い物が期待できるようなスポットがありません。
そのため、塩尻駅改札口にあるニューデイズ(New Days)で是非とも買い物を済ませておきたいところです。
昼食・水・マスク・ティッシュ・電池など、必要に応じて塩尻駅のニューデイズで買っておけば無難でしょう。
木曽の谷の鉄道旅へ
洗馬・贄川・奈良井と進む
塩尻駅を出ると、
- 洗馬駅
- 贄川駅
- 奈良井駅
という風に進んでゆきます。いずれも長野県塩尻市の駅です。
ここからはJR東海の管轄下となり、また長野県塩尻市の平野を南西へと過ぎて行ゆき、徐々に平野部は終わりを迎えます。
やがて、木曽の谷へと入って行きます。
「将軍」とは、旭将軍・義仲のこと 義仲にゆかりある洗馬駅へ
歌詞にある「将軍」とは、ここでは朝日将軍義仲こと、源義仲のことをいいます。
義仲は、木曽の宮ノ越という場所で育ったため、木曽義仲とも呼ばれます。
義仲がここで馬を洗ったことから、洗馬というわけです。

洗馬駅(長野県塩尻市)
宮ノ越については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

義仲ゆかりの地へ入ってゆく
先述の通り義仲は木曽で育ったので、ここから先は木曽の谷に入ってゆき、また義仲のゆかりの地にも徐々に近づいてゆきます。
ここから先は、中山道の
- 洗馬宿
- 贄川宿
- 奈良井宿
という風に続いてゆきます。

贄川駅(長野県塩尻市)
深い木曽の谷をゆく中山道 昔の旅人たちを苦しめてきた険しい道のり
中山道とは、江戸~京都間を約20日かけて徒歩または馬で移動していた、江戸時代の道路です。
当時は飛行機も新幹線も高速道路もなく、何日もかけて移動すしていたのでした。
そのため、旅人たちが途中で泊まるための町が必要になります。
これを宿場町といいます。
木曽の谷における中山道の宿場町に関しては、後述する奈良井宿をはじめとして、当時の江戸時代の建物、木造建築の建物などがそのまま残っている場所があります。
これは全国的にみても非常に珍しいことになります。

中山道の宿場町の一つ・奈良井宿(長野県塩尻市)
そのため、国内外からの観光客がとても多い地域であるといえます。
木曽川が削って作った、木曽谷

だんだんと険しい木曽の谷に入ってゆく(中央西線)(長野県)
木曽の谷は、主に木曽川が作る峡谷です。
「峡谷」または「谷」とは、川の水が削っていくことによってできる、山と山の間にできる凹んだ部分です。
この「谷」の底に川が流れ、川の周りには平地ができやすいため、ここに道が出来たり、民家が建ちならんだりしていくわけです。
ヒノキをはじめとした、木曽の木材
木曽の谷も、古くは中山道のような道ができたり、それに伴って宿場町が出来たりしていったのでした。
また、木曽は寒くて厳しい環境のため、ヒノキなどの木が丈夫に育ちます。
そのため、木曽のヒノキをはじめとする木材は江戸の家屋や伊勢神宮などに使われる木材として有名でした。
木曽の木材については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

木曽の中心地・木曽福島
木曽は、江戸時代には幕府が直接管理・運営する直轄地となっていました。
そのため、こうした木材を集めたり、売ったりするための拠点が置かれたのが、木曽の谷のちょうど真ん中にある、木曽福島という町です。

木曽福島の町並み(長野県木曽郡木曽町)

木曽福島の町並み(長野県木曽郡木曽町)
木曽福島については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

歌詞「駅路の鈴の音絶えて」
こうして栄えてきた木曽の谷を、今は列車は進んでゆきます。
歌詞によれば、
(列車が駅を離れていくたびに)絶えて、
木曽の谷に、汽笛が鳴り響く
というわけです。
昔の木曽路は、
ほどでしたが、今の時代は「特急しなの」で、木曽の谷を豪快に進んでゆきます。
贄川駅の「信州リハビリテーション専門学校」
贄川駅では、少なくとも私が乗ったときは、いつも大勢の若い人達が降りていきます。
若い女性の皆さんも男性の皆さんもみなスーツ姿であるため、恐らく高校生ではなく、大学生でしょう。
恐らくですが、贄川駅の近くには「信州リハビリテーション専門学校」という学校があるため、こちらの学生さんではないかと思われます。
中山道の宿場町・奈良井宿へ
やがて、中山道・奈良井宿で有名な、
- 奈良井駅(長野県塩尻市)
に到着します。
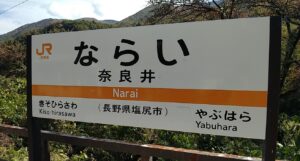
木曽の駅の一つ・奈良井駅(長野県塩尻市

木曽の駅の一つ・奈良井駅(長野県塩尻市)
江戸時代からの風情が、今も残る町並み

木曽の宿場町の一つ、中山道・奈良井宿(長野県塩尻市)

木曽の宿場町の一つ・中山道・奈良井宿(長野県塩尻市)
奈良井宿は、東西に約1kmというとてつもない長さの宿場町です。全国トップクラスの長さといっていいでしょう。
江戸時代の建物が今もリアルに残っており、しかもその街並みが延々と続くという凄まじい光景となります。

中央西線・奈良井駅(奈良井宿)あたりの線路の景色(長野県塩尻市)
奈良井宿については、以下の記事でさらに詳しく解説しておりますので、ご覧ください。

次回は、鳥居峠の話題へ
そして奈良井宿を出ると、鳥井峠という険しい山道に向かって進んでゆきます。
次は、「鳥居峠の戦い」の話題になります!

コメント