中央線鉄道唱歌の歌詞(旭将軍・義仲、宮ノ越)について、鉄道に詳しくない方にもわかりやすく解説してゆきます!
↓まずは原文から!
育ちし里は宮の越
傲る平家を討たばやと
旗揚げしたる南宮社
さらに読みやすく!
育ちし里は 宮の越
傲る平家を 討たばやと
旗揚げしたる 南宮社
さあ、歌ってみよう!
♪そだちしさとはー みやのこしー
♪おーごるへいけを うたばやとー
♪はたあげしたるー なんぐうしゃ
塩尻駅→洗馬駅→贄川駅→奈良井駅→藪原駅→宮ノ越駅→木曽福島駅→上松駅→須原駅→野尻駅→南木曽駅→坂下駅→中津川駅
※鉄道唱歌に関連する主要駅のみ表記
藪原駅を出て、宮ノ越駅に到着
藪原駅(長野県木曽郡木祖村)を出て、木曽路・中央西線を南下してゆきます。
やがて、
- 宮ノ越駅(長野県木曽郡木曽町日義)
に到着します。

宮ノ越駅(長野県木曽郡木曽町日義)
旭将軍・源義仲が育った、宮ノ越

宮ノ越からの木曽川(長野県木曽郡木曽町日義)
宮ノ越は、源義仲が育った場所でございます。
源義仲は、あの源頼朝のいとこであり、
- 朝日将軍または旭将軍・義仲
- また、木曽義仲
とも呼ばれます。

義仲さんは、私も尊敬している人だよ!
宮ノ越は、あくまで源義仲が「育った場所」
生まれは埼玉県・秩父あたり
宮ノ越は、あくまで義仲が「育った場所」であり、「生まれた場所」ではありません。
生まれた場所は、埼玉県の秩父あたりの地域であり、幼少期に一家で木曽に移住してきたのです。
また、宮ノ越では巴御前という、幼馴染の女性も生まれています。
愛人・巴御前にゆかりある「巴淵」
宮ノ越には、義仲の愛人の女性である巴御前に由来する、「巴淵」という峡谷があります。
この峡谷は、木曽川が深く入り組んだところにあります。
また、中央西線の車窓から、窓の右側に、わずかながら見ることができます。
平安時代・源平合戦とともに始まる、義仲の人生
貴族と武士の力関係が、逆転し始めていた時代
平安時代末期。
この頃は、朝廷や貴族が自分たちの荘園(自力で耕した巨大な農地のこと)を略奪などから守るため、武士を深く重用していた頃でした。
それに伴い、武士の力はどんどん強くなっていった時期でした。
強くなりすぎて、貴族と主従関係や力関係が徐々に逆転し始めている頃でもありました。
また平安時代後期は、あの藤原道長によって始められた摂関政治も、なんと100年にも及んで続いていた時期でした。
摂関政治の終わり 院政のスタート
しかし、その摂関政治も、平安時代の終わりには途絶えることになりました。
なぜなら、藤原道長の血筋の後継ぎの子どもが生まれなかったからです。
これによって、摂関政治に不満を持っていた他の貴族にとってはチャンスとなります。
やがて「院政」といって、
- 天皇自身はその座を退き、
- 後継(後任の天皇)は息子などに任せて、
- 自分は「院」という場所で仕切って、事実上の支配者となる
という政治の形式が、平安時代後期に始まりました。
「院政」のメリットは?
「院政」のメリットは、
天皇などのトップに責任を押し付けておきながら、自分が影のトップ・権力者になれること
です。
こうすれば、何か問題があっても自分が批判の矢面に立たされることはありません。
現代でも、自分が組織のトップを退いて息子に後を継がせておきながら、実際は裏で息子(トップ)に指図するという影の支配者である、といった事が行われる場合があります。
これを俗に「院政(を敷く)」と揶揄される場合があります。
源氏と平氏が、徐々に頭角を現してくる 「保元の乱」
話が少しズレましたが、平安後期にこの院政を行っていた者同士が権力争いするようになったのです。
そのため、どちらも「源氏」「平氏」の武士を味方に付け、争いが勃発します。
これを1156年の「保元の乱」といいます。
このとき、まだ源氏・平氏は対立していません。
ちなみに源氏も平氏も、元々は朝廷から信頼されていた武士たちでした。
というのも、
- 平氏は、桓武天皇の子孫(桓武平氏)
- 源氏は、清和天皇の子孫(清和源氏)
であり、どちらも先祖が天皇に辿り着くという、高貴な血筋の家系だったからです。
1160年「平治の乱」源氏の敗北、平氏の時代へ
そして1159年・1160年の「平治の乱」。ついに源頼朝の父である源義朝が平氏に敗れ、息子の頼朝も伊豆に流罪となってしまいました。
この頼朝が流れ着いた場所は蛭ヶ小島といい、伊豆箱根鉄道・駿豆線の、
- 韮山駅(静岡県伊豆の国市)
から向かうことができます。
伊豆・蛭ヶ小島については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

頼朝はここで後に妻になる北条政子と出会っています。
1180年「以仁王の挙兵」で立ち上がる、源義仲 旗揚げをした南宮神社
頼朝が20年間を伊豆の国で過ごした後、1180年の以仁王の挙兵において、全国の源氏に平氏打倒の命令が下ります。
これに伴い頼朝も挙兵しましたが、神奈川県の南西・真鶴あたりで起きた「石橋山の戦い」で敗れてしまいます。
石橋山の戦いについては、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。
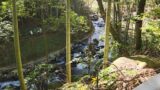

「傲り高ぶる平家を討て」と旗揚げ
また、義仲も1180年の以仁王の呼びかけに応じて、今回のメインである木曽・宮ノ越にて挙兵します。
宮ノ越には、南宮神社という神社が存在します。
義仲はここで、
と旗揚げはたあげしたのでした。
「よーし、平氏を倒すぞー!オーッ!」みたいなイメージですね。
北陸・倶利伽羅峠より、快進撃を続ける
義仲は、北陸・福井県の燧城にて一旦敗北しました。
しかし、富山県と石川県の県境にある倶利伽羅山の戦いで、なんと
したのでした。
これを「火牛の計」といい、倶利伽羅峠のある津幡町の名物になっています。
倶利伽羅山の戦いについては、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

その後、平氏軍を追って石川県の名前の由来にもなった手取川を渡ってゆきます。
手取川については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

手取川を渡った後は、北陸地方をどんどん南下してゆき、近江国(滋賀県)に入ります。
そして比叡山延暦寺を、武力ではなく交渉で突破しました。
ついに、念願の京都入り
やがて義仲は、ここに念願の京都入りを果たします。
義仲は東の方向からまるで朝日のように登場したため、「朝日将軍」「旭将軍」の異名がつきました。
めでたく京都に入った、義仲の運命は
さて、見事に京都入りした義仲の運命はどうなるのか。
続きは、次回お話しします!!

コメント