中央線鉄道唱歌の歌詞を、わかりやすく解説してゆきます!
須原・野尻の地理・歴史などについて、やさしく解説してゆきます!
↓まずは原文から!
しぶきに虹ぞ立ちわたる
名所めぐりも束の間に
須原の宿や野尻驛
さらに読みやすく!
しぶきに虹ぞ 立ちわたる
名所めぐりも 束の間に
須原の宿や 野尻駅
さあ、歌ってみよう!
♪しぶきににじぞー たちわたるー
♪めいしょめぐりも つかのまにー
♪すはらのしゅくや のじりえきー
塩尻駅→洗馬駅→贄川駅→奈良井駅→藪原駅→宮ノ越駅→木曽福島駅→上松駅→須原駅→野尻駅→南木曽駅→坂下駅→中津川駅
※鉄道唱歌に関連する主要駅のみ表記
今回は、上松→須原・野尻の行程へ
上松駅を出て、木曽川に沿って大桑村へ
上松駅(長野県木曽郡上松町)を過ぎ、
- 寝覚の床
も過ぎると、木曽路・中央西線を南下し、木曽川に沿って険しい山道をどんどん下っていきます。

木曽川に沿って、木曽の谷を進む(長野県)
木曽八景の1つ「小野の滝」
木曽谷に沿って進むと、途中、
- 上松駅
- 倉本駅
のちょうど中間に、また歌詞の冒頭にあり、また「木曽八景」の1つである、
- 「小野の滝」
という景勝地があります。
しかし、列車では本当に一瞬で過ぎ去ると思うので、私(筆者)は「小野の滝」を確認できていません。
すみませぬ(^^;)

「小野の滝」がある付近。鉄道では、これが目一杯!(中央西線)(長野県)
「木曽八景」とは?
ここで木曽八景には、以下の8つの景色が含まれています。
- 徳音寺
- 御嶽山
- 木曽の桟
- 寝覚の床
- 風越山
- 木曽駒ヶ岳
- 小野の滝
- 秋の与川の月
中央線鉄道唱歌では、これら8つの風景がすべて歌われています。
小野の滝に、七色のしぶきが輝く
歌詞では、
様子が歌われています。

「小野の滝」がある付近。鉄道では、これが目一杯!(中央西線)(長野県)
須原駅・野尻駅(大桑村)へ
倉本駅を過ぎると、やがて
- 須原駅
- 野尻駅
という風に到着します。
いずれも、長野県木曽郡大桑村の駅です。
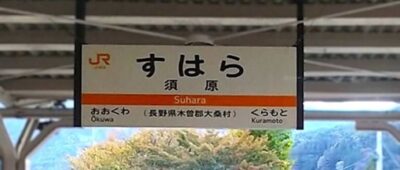
須原駅(長野県木曽郡大桑村)
中山道 須原宿・野尻宿
- 須原宿
- 野尻宿
阿寺ブルー
大桑村は、やはり
- 阿寺ブルー
という、水の青さが凄く綺麗な景色美が印象的です。
真っ白で綺麗な岩に、エメラルドグリーンに近い青さの木曽川の水がとても印象的です。
阿寺峡谷は、木曽川にかかる非常に深い峡谷です。
木曽駒ヶ岳
須原駅を過ぎると、バックに美しい木曽駒ヶ岳がそびえ立ちます。
また、車窓右後ろに来る、須原宿の整った町並みもまた印象的です。

須原宿の町並み(中央西線)(長野県木曽郡大桑村)
野尻宿の「七曲がり」
野尻宿には、敵の侵入を防ぐため「七曲がり」というカーブの連続がありました。
これには、宿場町にあえてカーブを多くすることで、死角を作り敵の侵入を防ぐ、という目的がありました。
それは、江戸幕府に反抗・謀反する藩や大名たちが、中山道を通って江戸へ向かうことを防ぐ、という目的が一つに挙げられます。
また、木曽の貴重なヒノキ(江戸の武家屋敷や、伊勢神宮など高貴な用途に使われる)を、勝手に盗んで持ち出されるのを防ぐ、という目的もあったでしょう。
かつて野尻駅から出ていた「野尻森林鉄道」
また野尻駅からは、明治時代には
- 「野尻森林鉄道」
という、貨物鉄道路線が出ていました。
また、この野尻森林鉄道の路線のことを、「柿其線」といいます。
森林鉄道とは
「森林鉄道」とは、まだ車やトラック・車道が一般的でなかった時代に(だいたい明治~昭和初期あたりに)、山で採れた木材を、貨車に載せて運ぶための鉄道です。
木曽地域は、ヒノキ(檜)をはじめとする木材が大量に採れる場所です。
また、それを各地に販売することで、生計を立てていましたから、採れた木材をどう運ぶかが重要でした。
「貨車」とは?
貨車は、荷物を載せる車両ですが、いわゆる「動力」が付いていません。
つまり、貨車のみで走ることはできないわけです。
貨車は、先頭の機関車に引っ張られて(または、後ろから押されて)、はじめて動くことになります。
また、明治時代の機関車は「電気」ではなく、「蒸気」で動くのが一般的でした。
そのため、機関車は必然的に、「蒸気機関車」でした。
機関車については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

明治時代には、その蒸気機関車が、大量の木材を貨車に載せて、一生懸命引っ張って運んでいたわけですね。
1960年代以降、自動車の一般化で森林鉄道は衰退
しかし、1960年代にもなると自動車やトラックが普及し、道路が整備されてゆしました。
そうなると、木材運搬の役割は必然的にそちらへ移っていくことになります。
やがて多くの森林鉄道は、役割を終えて廃止されてゆきました。
野尻森林鉄道は、現代でもわずかながら廃線跡があります。
というか、エメラルドグリーン色の木曽川にかかった鉄橋が、まさに明治時代のレンガ造りそのものです。
須原・野尻の次は、南木曽駅へ
次は、南木曽駅に止まります!

コメント