姫路城について、観光・歴史などをわかりやすく解説してゆきます!
初心者の方にもやさしく解説してゆきます!
世界遺産・姫路城

姫路駅からの、姫路城の眺め(兵庫県姫路市)
今回は、世界遺産にも登録されている姫路城について、一緒に見ていきましょう。
白鷺が羽を広げたような、その美しい姿は、まさに圧巻ですよね!
しかし、姫路城の魅力は、その美しさだけではありません。
その裏には、戦国時代から現代に至るまでの、壮大でドラマチックな歴史が隠されているのです。
歴史のロマンを感じながら、一緒に姫路城の世界を巡っていきましょう。
きっと、今よりもっと姫路城が好きになるはずです。

筆者、姫路の街より(兵庫県姫路市)
姫路城の由来

姫路城(兵庫県姫路市)
姫路城は、まるで白鷺が羽ばたくような美しい姿をしていますよね。
実は、姫路城は「不戦の城(※)」とも呼ばれています。
なぜなら、城が築かれてから、大きな戦乱に巻き込まれることがほとんどなかったからです。
※戦時中も、姫路城は不発弾やカモフラージュなどの様々な要因により、奇跡的に焼失を免れました。
これも姫路城が「不戦の城」と呼ばれる所以です。
そのため、その美しい姿を今に残すことができたのかもしれませんね!
姫路城は、なぜ「日本の城郭建築における最高峰」と呼ばれるのか?

「白鷺城」の異名を持つ姫路城(兵庫県姫路市)
姫路城は、その美しい姿から「白鷺城」という別名でも親しまれています。
しかし、美しいだけではなく、日本の城の最高峰と言われる理由は、次の3つが挙げられます。
白鷺:全身の羽が白い、サギとよばる鳥類の総称です。
例えば、岐阜県の下呂温泉には、温泉の由来となった白鷺伝説があります。
他にも、特急列車における「しらさぎ」は、主に名古屋と敦賀を結ぶ特急列車です。
とても美しい、完成度の高さ
これは言うまでもありません。
姫路城は 白鷺城と呼ばれるぐらい、まるで白鷺のように美しいお城の形になります。
保存状態の良さ
現在、かつて多く存在した日本のお城は、
- 老朽化
- 焼失、自然災害
- 江戸時代はじめの一国一城令(つまり、主要な一つのみを残して、ほかの城は廃止)
- 明治時代はじめの廃城令(軍事的に使えそうな城のみを残して、ほかの城は廃止)
などの理由で、今はほとんど残っていません(今各地に多く存在している城は、戦後に復元されたものも多い)。
すなわち、姫路城は、今に至るまでボロボロにならず、奇跡的に保存されてきたのです。
日本独自の城郭構造

姫路城(兵庫県姫路市)
姫路城は、日本独自の城郭構造を最もよく示しているお城です。
城郭構造:敵からお城を守るための、様々な仕組みや工夫のことです。
したがって、このお城を見れば、昔の人々がどのようにして敵と戦い、お城を守ろうとしたのかがわかります。
西国(西日本)監視・防衛の拠点だった姫路城

西国(西日本)の守りの拠点だった、姫路城(兵庫県姫路市)
姫路城は、もちろんシンプルに美しいというだけではありません。
実は「西国監視・防衛の拠点」という、とても重要な役割も担っていたのでした。
なぜ、姫路城は「西国の防衛拠点」だったのか?
江戸時代、姫路城は、その頑丈な構造と、戦略的にとても良い立地のおかげで、主に次のような重要な役割を担っていたのでした。
- 西日本にいる(幕府に反発しているかもしれない)大名の監視
- その反対勢力などから幕府を防衛し、その権力を守る
すなわち、姫路城は、江戸幕府にとって、重要な軍事拠点だったのです。
姫路城は、なぜ「戦略的な立地」だったのか?
姫路城は、瀬戸内海に近く、西国へのアクセスが良い場所に位置していました。
そもそも「西国」とは?
そもそも、西国とは、昔から京都や奈良といった都(畿内)から西にある国々(地域)を指した言葉です。
畿内:大昔の日本において、以下の5つの国のことをいいます。
- 大和国:現在の奈良県
- 山城国:現在の京都府南部
- 河内国:現在の大阪府東部
- 和泉国:現在の大阪府南部
- 摂津国:現在の大阪府北部と兵庫県南東部
まあ、畿内=ほぼ関西地方、と覚えておけばよいでしょう。
また、時代や文脈によって「西国」の範囲は異なりますが、かつては特に九州地方を指すことが多かったようです。
しかしその後、中国地方や四国地方も「西国」の中に含まれるようになりました。
したがって、西国からの反乱や侵略を防ぐための、重要な防衛拠点としての役割を担っていわけですね!
姫路城は「幕府の権威の象徴」でもあった!
では、なぜ江戸幕府に反発しているかもしれない大名たちが、西日本にいたのか?
それはかつて、西日本には、かつて関ヶ原の戦いで敗れたために、江戸幕府に恨みを持つ大名もたくさんいたのでした。
すなわち、そんな西国の大名たちにとって、姫路城の存在は、常に幕府の力を意識させるものとして機能していたのでした。
このように、姫路城は幕府に反逆して江戸に攻め込ませないための、重要な抑止力だったというわけです。
この「幕府に反発するかもしれない、西日本の大名たち」の存在については、江戸幕府もよく理解していたのでした。
そのため、幕府にとって攻め込まれる前に姫路城で食い止めるという、防衛拠点としての役割は、本当に重要だったわけです。
姫路城の存在する、播磨の中心都市・姫路
姫路の由来

姫路駅(兵庫県姫路市)
姫路のという地名は、お城が建っている「姫山」という場所の昔の名前「日女路の丘」に由来すると言われています。
「ひめじ」という響きが、なんだか可愛らしいですよね!
実は、この名前には、とても古い歴史があるのです。
姫路の名前の由来は、神話からきている?
姫路という地名は、古くは『播磨国風土記』に登場する「日女道丘」という丘の名前から来ていると言われています。
この「日女道丘」は、神話の中でも
- 「神様の船が流れ着いた場所」とされています。
そして、その時に流れ着いた「蚕子」が転じて、「ひめじ」と呼ばれるようになった、と伝えられています。
そもそも、昔はカイコのことを「ひめこ」と呼んでいたそうです。
したがって、この地域は、昔、養蚕業がとても盛んだったのかもしれませんね!
『播磨国風土記』とは、どんな書物?
ここで『播磨国風土記』とは、奈良時代にまとめられた、今の兵庫県にあたる播磨地方の地理や歴史、伝説などを記録した書物です。
なにせ大昔の書物であるため、現代人の我々にはわけのわからないフォント(万葉がななど)で書かれており、よほどの専門家でない限り、読むことは難しいでしょう。
現在残っているのは「写本」
ちなみに、現在残っている風土記は、原本ではなく、何度も書き写されてきた「写本」だけです。
つまり、コピー機がない時代に、手書きで写された「コピー」ということです。
そのため、時の権力者によって、都合の悪い記事が削除されたり、内容が書き換えられたりした可能性も指摘されています。
現在残っている写本は、平安時代に書かれたもので、国宝にも指定されています。
古代の播磨国の人々の生活や文化を知る上で、とても貴重な資料となっているのですね!
播磨国の国府・姫路
姫路は、奈良時代に播磨国の国府が置かれた場所でもありました。
姫路城が建てられるずっと前から、この場所はとても重要な場所だったのですね!
そもそも「国府」や「播磨国」とは?
播磨国とは、今の兵庫県南西部にあたる地域のことです。
「播州」という別名でも知られています。
そして、国府とは、奈良時代から平安時代にかけて、今の都道府県にあたる場所に置かれた「地方政治の中心地」のことです。
つまり、今の県庁所在地に似ていますね。
すなわち、国府には、都から派遣された国司という役人が、政治を行うための建物や、倉庫・住居などを建てていました。
つまり、ある種の「地方の都市」を形成していたのです。
播磨国は、昔のルールでは「大国」だった!
播磨国は、奈良時代の法律である律令制では、「山陽道」というエリアに属していました。
昔は「道」というと、単なるルートのことではなく、大きなエリアを指すことばでもありました。
現在でも「北海道」に、その名残がありますよね。
また、当時の法律である延喜式というルールでは、なんと「大国」に格付けされていました。
大国とは、今の都道府県で言うと、人口が多く、重要な役割を担う場所のことです。
当時の播磨国は、とても重要な地域だったことがわかりますね!
姫路城は、もともと播磨国・国府のあった「姫路」にあった!
播磨国では、国府と国分寺が、現在の姫路市に置かれていました。
国分寺とは、奈良時代に建てられた、国ごとに一つずつ置かれたお寺のことです。
つまり、姫路という場所は、昔から政治や文化の中心地だったのです。
その場所に、後に姫路城が築かれたというのは、なんだか運命的なものを感じますね!
国分寺とは何か?については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

姫路城および播磨国の歴史
平安時代から鎌倉時代にかけての姫路
平安時代から鎌倉時代にかけて、姫路では荘園という大きな田んぼが広がっていきました。
荘園とは、昔のエライ人たちが耕しまくって出来た、巨大な田んぼ・農園のことです。
ドロボーや不当な税金からの取り立てから防御・防衛するために、さまざまな工夫がこらされていました。
荘園について詳しくは、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。
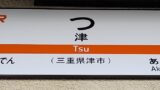
その後、鎌倉時代の終わり頃、14世紀の初めには鎌倉幕府に対して不満を抱いた、「悪党」と呼ばれる勢力が現れるようになってきます。
鎌倉時代終盤および「悪党」について詳しくは、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

そして以下で解説する通り、赤松則村が兵を挙げ、鎌倉幕府を倒すための戦いに参加しました。
赤松氏の存在をメジャーにした、赤松則村
赤松則村は、鎌倉時代末期から南北朝時代にかけて活躍した武将です。
後醍醐天皇とともに、鎌倉幕府を倒す
後醍醐天皇の鎌倉幕府討幕運動(元弘の変)に加わり、足利尊氏らとともに、鎌倉幕府を滅ぼすための戦いで活躍しました。
元弘の変について詳しくは、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

足利尊氏を助け、新田義貞を撃退
また、その後の後醍醐天皇による建武の新政に不満を抱いた足利尊氏が、後醍醐天皇と新田義貞に対して挙兵することとなりました。
そのとき、新田義貞の軍に追われて九州へ敗走するときに、播磨の上郡にあった白旗城に立て込もって、新田軍の追っ手を迎え撃ち、足利軍の九州落ち・再起を助けました。
上郡:現在の相生駅(兵庫県相生市)のやや北西にある、山陽本線・上郡駅のある場所です。
また、鳥取方面へと続く智頭急行との分岐点であります。
その後、足利尊氏は九州から復活して、楠木正成らを倒し、室町幕府を成立させたのでした。その後、赤松則村はその功績によって播磨国守護に任じられ、赤松氏を室町幕府を支える有力な守護大名に押し上げました。
江戸時代の姫路
そして、時代は移り、関ヶ原の戦いの後、池田輝政が姫路城を改築し、この地を支配しました。
その後、この地域には、
- 姫路藩
- 明石藩
- 赤穂藩
などが置かれました。
それぞれ、今の姫路市・明石市・赤穂市を中心とした地域ですね!
明治時代の姫路
明治時代になると、1871年の廃藩置県によって、兵庫県と姫路県に分かれました。
廃藩置県:昔の藩を廃止して、県を置くという、明治政府が行った行政改革のことです。
しかし、その後、姫路県は飾磨県と名前を変え、さらに1876年には兵庫県に編入されました。
ちなみに、現在の姫路市街地にある本町遺跡は、昔の国衙の跡だと考えられています。
国衙:国府と似ている言葉ですが、国府は国衙のある都市全体であるのに対して、国衙は行政機関そのものを指します。
赤松氏の歴史
嘉吉の乱で、室町将軍を倒してしまう
赤松一族の歴史は、それは波乱万丈なものでした。
前代未聞 赤松満祐は、なぜ将軍を殺したのか?
赤松満祐は、嘉吉の乱という事件で、室町幕府の第6代将軍、足利義教を暗殺しました。
なぜなら、義教が多くの人々を恐怖で支配していたからです。
足利義教:室町幕府の第6代将軍(在職:1429年~1441年)です。父は第3代将軍の足利義満で、第4代将軍の足利義持の弟にあたります。
兄である第4代将軍・足利義持が跡継ぎを決めないまま亡くなったため、くじ引きによって後継者が選ばれることになりました。
この「くじ引き」で選らばれたという経緯から、「くじ引き将軍」とも呼ばれています。
しかも、将軍になった経緯が、なんとくじ引きだったそうです。
義教のやりたい放題な政治は、もはや貴族や寺、そして各地の大名たちを恐怖に陥れたのでした。
そして、赤松満祐も足利義教の恐怖政治の標的(ターゲット)となり、自分の立場が危うくなったため、暗殺を決意したのです。
そしてついに、1441年(嘉吉元年)、赤松満祐は京都にある自分の屋敷の宴に足利義教を招き、殺害しました。
その後、赤松満祐は自分の領地である播磨国に戻りますが、室町幕府は赤松氏を「幕府に反乱した敵」として討つため、討伐軍を播磨へと派遣しました。
そのため、最終的に、赤松氏一族は幕府軍に敗れて滅び、赤松満祐も自害しました。
しかし、足利将軍が殺害されるという、このなんとも前代未聞の事件は、室町幕府の権威を大きく傷つけました。
また、幕府が混乱したことで、有力な大名たちが領土を奪い合う動きが加速してゆき、後の応仁の乱へとつながっていきました。
一旦滅亡した赤松氏は、どのようにして復活したのか?
嘉吉の乱で、一度は滅びた赤松氏ですが、今度は赤松政則が中心となって再興(復活)されました。
彼は、応仁の乱をきっかけに、播磨の戦国大名として、再び力をつけていきました。
なんとも、すごい執念ですね!
「守護」と「国司」は、どう違う?
鎌倉時代には、守護と国司という、2つの重要な役職がありました。
それぞれの役割は、以下の通りです。
- 守護
- 鎌倉幕府が選び、その国の武士を統率し、治安を守る役割を担っていました。
- 現代でいう県知事+警察本部長のような非常に強い権限を持ったトップというイメージです。
- 国司
- 朝廷が選び、法律に基づいた仕事を行っていました。
- 今でいうと、県知事のような役割ですね。
どちらも県知事レベルの権限は持っているため、当初はこの二者で二重行政のような状態でした。
しかし、次第に守護の方が力を持つようにってゆき、国司の権限はどんどん形骸化してゆきました。
したがって、
というわけです。
黒田官兵衛と姫路城には、深い関係があった?
黒田官兵衛、秀吉に姫路城を譲る
織田信長が中国地方へと勢力を広げていく中で、当時は家臣(部下)だった羽柴秀吉が、播磨国にやってきました。
その時、秀吉の勢力に恐れを抱いてしまった黒田孝高、つまり黒田官兵衛は、自分の城である姫路城を秀吉に譲ることにしました。
つまり、「長いものには巻かれよ」という感じで、無理に抗って滅ぼされるよりは、素直に秀吉に協力しておいたほうが、後々いいことがあると判断したわけですね。
これにより、姫路城は織田家(+秀吉)がこれから中国地方の毛利氏を攻めていくための、重要な拠点となったというわけです。
秀吉、播磨国を手に入れる!
1576年、中国攻めを進める信長の命令で、秀吉が播磨国に来ました。
すると、播磨の武士たちは、
- 織田氏に味方する派
- 毛利氏に味方する派
に分かれて、激しく対立しました。
まさに、戦国の世ですね。
三木合戦
しかし、1580年には、秀吉が三木合戦で三木城を攻め落とすことになります。
三木合戦は、1578年から1580年にかけて、現在の兵庫県三木市で行われた合戦です。
相手側の別所長治は、難攻不落とされた三木城に籠城しましたが、秀吉は城への兵糧の搬入路を断ち、約2年にわたる兵糧攻めを行いました。
これにより城内では多数の餓死者が出たとされ、この戦いは「三木の干殺し」とも呼ばれています。
最終的に別所長治は、お城の兵士たちの助命を条件に、一族と共に切腹し、三木城は開城しました。つまり、彼は自らの命と引き換えに、城の人々の命を救ったわけです。
これにより、織田側の羽柴秀吉軍が勝利しました。
秀吉・英賀城の攻略
三木城を落とした秀吉は、続いて英賀城などを攻め落としてゆき、見事に播磨国を手中に収めました。
英賀城は、かつて兵庫県姫路市のやや西側にあったお城です。
中世には「播磨最大の都市」とも呼ばれ、栄えましたが、 織田信長の播磨攻略により、羽柴秀吉の攻撃を受け、1580年に落城しました。
秀吉、天下を統一!
1582年6月、秀吉は、主君の信長を裏切って殺害した明智光秀を倒し、天下統一への道を歩み始めました。
その後、1583年には、天下統一の拠点として築いた大坂城へと拠点を移しました。
姫路城には、弟の豊臣秀長が入りました。
この後、秀吉が日本を統一したことは、あなたもご存知の通りです。
江戸時代の姫路城
江戸時代になると、「西国将軍」や「姫路宰相」と呼ばれた池田輝政が姫路藩を創設しました。
そして、姫路城を現在の姿に改築しました。
そして、冒頭に述べた通り、江戸時代の姫路は、西日本の大名の監視拠点として重要な役割を果たしてきました。
黒田官兵衛から秀吉、そして池田輝政へと、姫路城は日本の歴史の中心で、様々な人物によって受け継がれてきたのですね!
おわりに・姫路城まとめ
さて、今回は姫路城の歴史を、様々な角度から見てきましたが、いかがでしたでしょうか。
単なる美しいお城ではなく、日本の歴史を動かしてきた、多くの人々の想いが詰まった場所だったのですね。
黒田官兵衛や池田輝政といった、歴史上の有名人物たちによって、姫路城が現在の姿にまで守り抜かれてきたことを知ると、なんだか感動してしまいますよね。
次に姫路城を訪れる際は、ぜひ今回学んだ歴史を思い出しながら、ゆっくりと散策してみてくださいね!

コメント