赤穂線・相生~東岡山の鉄道旅と、赤穂線・山陽道・備前焼の歴史について、初心者の方にも、わかりやすく解説してゆきます!
赤穂線とは
今回は、兵庫県~岡山県の沿線の景色の魅力がたっぷり詰まった、赤穂線についてお話ししましょう!
すなわち、今回メインで扱う赤穂線は、
- 岡山県岡山市の東岡山駅
- 兵庫県相生市の相生駅
を結ぶ路線となります。

赤穂線・日生駅付近の景色(岡山県備前市日生町)
赤穂線は、瀬戸内海沿いを走る、まさしく風光明媚な景色が自慢の路線として、よく知られています。
車窓から美しい海を眺めることができる、とても素敵な路線というわけです!
また、赤穂線はもちろん単なる移動手段としてだけでなく、旅の目的や学びにもなる、たくさんの魅力を持った路線だと言えるでしょう。

赤穂線のおだやかな景色
赤穂線の位置
まず赤穂線は、先述の通り岡山県と兵庫県の県境をそれぞれまたいでいる路線となります。
具体的には、
- 西側は、東岡山駅から始まり、
- 東側は、相生駅(兵庫県相生市)において、山陽本線に接続
しています。

赤穂線の起点・相生駅(兵庫県相生市)
つまり、赤穂線は山陽本線のバイパス路線(=つまり、万一のときに迂回するための道)のような役割も果たしているわけです。
そのため、もし山陽本線に万一何らかのトラブルがあったときには、赤穂線がその代替ルート(代わりの道)として機能することもあります。
したがって、岡山や姫路方面へ向かう際にも、よく利用される、とても重要な路線というわけですね。
赤穂線の特徴
まず赤穂線の一番の特徴は、なんといっても瀬戸内海の美しい景色です!
例えば、備前市日生町にある日生駅周辺においては、まるで海の上を走っているかのような、素晴らしい景色が広がっています。

小豆島行きのフェリーも出ている、海に面した駅・日生駅(岡山県備前市)
さらに、歴史的な街として知られる、忠臣蔵の舞台、播州赤穂を走るのも大きな魅力ですね。

播州赤穂駅(兵庫県赤穂市)

忠臣蔵のふるさと・播州赤穂駅(兵庫県赤穂市)
播州赤穂については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

また、赤穂線では基本的に単線区間(線路が1本しかない区間)が多くなっています。
そのため、のんびりとしたローカル線の雰囲気を満喫できる、というのも大きな特徴です。
したがって、赤穂線は都会の喧騒から離れて、ゆったりとした時間を過ごしたい方には、まさにぴったりの路線であるといえるでしょう。
赤穂線の歴史
次に、赤穂線は、戦後に日本が徐々に復興しつつあった復興期にあたる1951年に、
- 相生駅から
- 播州赤穂駅まで
にあたる、いわゆるはじめの区間が開業したのでした。
つまり、最初はこの部分だけが、限定的に開業したわけです。
すなわち、はじめから全ての区間が一度に開通したわけではなかった、というわけですね。
そして当初の赤穂線の目的は、沿線にある鉱山や、海産物などの輸送でした。
すなわち、赤穂線は地域の産業を支えるために作られた路線だったのです。
その後、線路は西へ西へと延びてゆき、1962年に東岡山駅までが全線開通し、現在の姿となりました。
それ以来、岡山や姫路への通勤・通学、観光客の足として、多くの人々に利用され続けています。
大昔の道が、鉄道になった?赤穂線

赤穂線・西片上駅(岡山県備前市)
赤穂線は、江戸時代に使われていた「山陽道」という、とても重要な道の跡を、電車の線路にしたようなものです。
大名行列も通った山陽道
山陽道は、昔からある、京都から福岡までを、瀬戸内海のそばを通ってつなぐ、メインの大きな道でした。
江戸時代には、「西国街道」とも呼ばれていました。
この道は、偉いお殿様(大名)たちが、武士たちをたくさん連れて旅をする「参勤交代」という行事で、よく使われていました。
また、西国街道はたくさんのお坊さんがお寺を回る巡礼の旅でも使われた、にぎやかな道だったのです。
現代の道や、鉄道の元祖・赤穂線
山陽道は、
- 今の国道2号
- 山陽本線
- 山陽新幹線
など、たくさんある大切な交通ルートの元になりました。
したがって、山陽道は、昔から今まで、ずっと日本の大切な場所をつないでくれているという、なんともすごい道であるというわけです。
忠臣蔵と赤穂線
赤穂線は、先述の通り播州赤穂から備前にかけての場所を通るため、昔の山陽道とほとんど同じように走っています。
播州赤穂は、先述の通り「忠臣蔵」という、テレビドラマや映画でも有名な物語の舞台になった場所です。
忠義のために戦ったお侍さんたちが通った道の上を、今や電車が走っているなんて、なんだか感動してしまいますね!
不思議な名前!小豆島の名前の由来
小豆島という名前には、2つの説があると言われています。
ひとつめは、
- 「小豆のように小さな島」
という説です。
そして、二つめは、日本の一番古い本である「古事記」や「日本書紀」に書かれている「阿豆枳島」という名前が元になっている、という説です。
しかし、どちらにしても、とっても昔から大切にされてきたという、可愛らしい名前なのです。
赤穂線の沿線・備前市の名物・備前焼
備前焼とは
備前焼は、
- 岡山県備前市の伊部地区
を中心に作られる、日本の代表的な焼き物です。
およそ1000年以上の歴史を持つ、とても伝統のある工芸品ですね!

伊部駅(岡山県備前市伊部)
備前焼においては、釉薬という、ガラス質のうわぐすりを使いません(他の焼き物では、普通は使われる)。
そのため、土そのものの色や、質感を活かして焼き上げるというのが、最大の特徴です。
つまり、土の持つダイレクトな素朴な風合いが、備前焼にしかない、唯一無二の魅力なわけです。
焼き物とうわぐすりの関係
一般的な焼き物においては、釉薬という、ガラス質のうわぐすりを使うのが普通です。
なぜかというと、この釉薬を塗って焼くことで、焼き物の表面にガラスの層ができます。
つまり、この層が、焼き物の表面をツルツルにしてくれるのです!
その結果、
- 水が染み込みにくくなる
- 汚れもつきにくくなるる
という、様々なメリットが得られるわけです。
ここからさらに、
- 色をつけたり、
- 模様を描いたり
することで、美しい見た目にする効果もあります。
したがって、釉薬は焼き物の実用性を高め、さらには芸術性をも加えるための、とても重要な役割を果たしているわけですね!
備前焼にうわぐすりが不要な理由
しかし、備前焼がこの釉薬を使わない理由は、その土にあります!
備前市・伊部地区で採れる、いわゆるリッチな材料である備前粘土は、鉄分を多く含んでいます。
この粘土は、非常にきめが細かく、粘り気が強いのが特徴です。
そして、この粘土で成形した作品を、約1200度以上の高温で、長時間かけてじっくりと焼き上げるというわけです。
すると、土に含まれる成分が溶け出してゆき、ガラス質のような固くて丈夫な状態になるのです。
したがって、釉薬を使わなくても、水が染み込みにくい、固く丈夫な焼き物ができあがるのです!
まさに、自然の力だけで、素晴らしい頑丈な焼き物が生まれるわけですね。
備前焼のメリットと強み
このような釉薬を使わない備前焼には、たくさんのメリットと強みがあります!
「土の温かみ」をダイレクトに感じる風合い
まず、うわぐすりを使わない備前焼は、土そのものの質感が、ダイレクトに素朴で、なおかつ温かい風合いを生み出します。
これは、他の焼き物にはない、備前焼だけの魅力ですね!
丈夫で割れにくい
また、うわぐすり無しで高温で長時間かけて焼くことで、硬く丈夫に焼き締まります。
そのため、衝撃に強く、頑丈で割れにくいのが大きな強みです。
ビールが美味しくなる?
さらに、うわぐすり無使用の備前焼の表面には、わずかな凹凸があり、これがビールの泡をきめ細かく保ってくれると言われています。
これはまさに、ビール好きにはたまらないメリットですね!
これらの強みは、釉薬を使わない、備前焼ならではの特徴・強みだと言えるでしょう。
釉薬を使わない他の焼き物
備前焼のように、釉薬を使わずに、素朴な風合いを活かす焼き物は、実は他にも存在します!
代表的なのが、
- 信楽焼
- 伊賀焼
- 常滑焼
などですね。
伊賀焼については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。
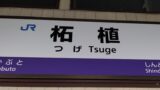
これらの焼き物も、それぞれの地域で採れる土の性質を活かし、高温でじっくりと焼き締めることで、独特の景色を生み出します。
つまり、土そのものの良さや、焼きながら窯の中で生まれるという、まさに偶然・ミラクルの美しさを楽しむという点では、備前焼と共通しているのです。
しかし、それぞれの焼き物には、土の成分や焼成方法の違いによって、異なる魅力があります。
こうした備前焼の持つ
- 「丈夫さ」
- 「素朴な美しさ」
は、他の焼き物にはない、ユニークな強みだと言えるでしょう。
伊部焼とは
また、伊部焼は、備前焼の中でも、伊部地区で作られたものを指します。
備前焼のほとんどは、この伊部地区で生産されているので、
- 「備前焼」=「伊部焼」
と考えても、ほぼ間違いではないと思われます。
この地域で採れる、良質な粘土が、備前焼独特の質感を生み出しているのですね。
したがって、備前焼の歴史は、伊部地区の歴史と深く結びついていると言えます。
伊部地区の職人さんたちが、代々受け継いできた技術と情熱によって、備前焼の伝統は守られ続けているのです。
そもそも「焼き物」とは
「焼き物」とは、粘土などを成形(形を作ること)し、高温で焼いて固めたものの総称です。
代表的なものに、
- 陶器
- 磁器
などがあります。
身近な例でいうと、
- お茶碗
- お皿
- 花瓶
なども「焼き物」です!
古代から、土器として人々の生活に欠かせないものでした。
現在では、単なる食器としてだけでなく、美術品や工芸品としても、世界中で愛されています。
土と火の力によって生まれる、まさにアートだと言えますね!
100均の食器との違い
ちなみに、100円均一の食器と備前焼の最も大きな違いは、やはり「素材」と「製造方法」にあります。
100均の食器では、大量生産が可能です。
むしろ大量生産しているため、安価で手に入りやすいのが特徴ですね。
一方で、備前焼は、一つひとつ職人さんの手で、丁寧に作られています。
さらに、窯の中で偶然に生まれる模様や、二つとない唯一無二の風合いを大切にする文化も違います。
すなわち、100均の食器が「実用性」を追求しているのに対し、備前焼は「芸術性」や「伝統」を重んじていると言えるでしょう。
備前焼と伊部焼の違い
伊部焼は、備前焼の中でも、
- 岡山県備前市の伊部地区
で作られたものを指す、別名のようなものです。
すなわち、
- 備前焼という大きなカテゴリ(分類)の中に、伊部焼が含まれている
と考えると分かりやすいでしょう。
備前焼のほとんどは、この伊部地区で作られているので、「備前焼」と「伊部焼」は、ほぼ同じ意味で使われることがほとんどです。
ただし、歴史的には、慶長時代(1596〜1615年)以降に作られた、ろくろで成形され、ろくろの跡が残らない薄手の作品を「伊部手」と呼び分けることもありました。
現代では、このような厳密な使い分けはあまりされず、備前焼の別名として伊部焼という言葉が使われています。
天下人に愛された備前焼
備前焼は、戦国時代から安土桃山時代にかけて、時の天下人である豊臣秀吉から、とても重用されていました。
特に、茶の湯の世界で、備前焼は
- 「侘」
- 「寂」
の精神に合うとされ、多くの茶人や武将に好まれました。
秀吉は、備前焼の技術をお金をかけてまでサポートし、さらには伊部地区の陶工たちを優遇したと言われています。
すなわち、備前焼は、単なる焼き物ではなく、権力者たちの社交や、文化活動を彩る重要なアイテムだったのです。
その素朴な美しさが、当時の武将たちの心をとらえたのかもしれませんね!
岡山藩と備前焼
江戸時代に入ると、備前焼は、今度は岡山藩からのサポート・優遇措置を受けるようになります。
つまり岡山藩は、備前焼の品質・クオリティを維持し、さらには発展させるために、様々な政策を行いました。
例えば、窯元の数を制限したり、厳しい品質管理をしたりしました。
これは、備前焼が藩の重要な産業であり、経済的な基盤となっていたからです。
また、藩主も、備前焼を贈答品として用いるなど、その価値を認めていました。
したがって、備前焼は、単なる工芸品としてだけでなく、地域の文化と経済を支える、大切な存在だったと言えるでしょう。
こうして、備前焼は、約1000年の歴史の中で、多くの権力者や文化人たちに愛され、大切にされてきたのです!
江戸時代、多くの旅人たちに買われた備前焼
備前焼は、江戸時代に山陽道(西国街道)を往来する旅人たちにとって、とても人気のある土産品でした。
備前市伊部地区は、山陽道のすぐそばにあり、街道を行き交う旅人たちが窯元を訪れることができました。
そこで旅人たちは、
- 花器
- 酒器
などの小さな備前焼を、記念や贈答用として買い求めたのです。
すなわち、備前焼は、単なる工芸品としてだけでなく、旅の思い出を形にする大切なアイテムだったと言えるでしょう。
このように、備前焼は、街道を通じて、全国へとその名が広まっていったのです。
旅人たちの手によって、日本の各地に、備前焼の魅力が届けられたわけですね!
備前焼は岡山藩の財源だった?
備前焼は、江戸時代に岡山藩にとって、重要な財源の一つでした。
岡山藩は、備前焼の生産と販売を厳しく管理し、生産者から「運上金」という税金のようなものを徴収していました。
つまり、窯元は、焼き物を売るたびに、藩に一定の金額を納める必要があったのです。
さらに、藩主や重臣たちが、贈答品として備前焼を用いることで、その価値が高まり、ブランド力も向上しました。
これにより、備前焼は、地域経済を支える、大きな柱となったと言えるでしょう。
まさに、備前焼は、藩の懐を潤す、大切な存在だったわけですね!
備前焼を、岡山藩が優遇・サポートした理由
岡山藩が、備前焼を優遇し、手厚くサポートした最大の理由は、経済的な利益に加えて、「藩の威信」をかけた重要な産業だったからです。
備前焼は、その質の高さと、歴史的な価値から、全国的に知られていました。
したがって、岡山藩が備前焼をサポート・支援・優遇・育成することは、岡山藩の文化的なレベルの高さを示すことにつながりました。
さらに、優れた備前焼は、将軍や他藩の大名への献上品としても用いられ、藩の外交を円滑にする役割も果たしたのです。
つまり、岡山藩にとって、備前焼は、単なる税収源ではなく、政治的・文化的な意味合いを持つ、戦略的な資産だったと言えるでしょう!
おわりに・まとめ(赤穂線・備前焼)
これまで、赤穂線と備前焼の歴史について、詳しく見てきましたが、いかがでしたでしょうか。
赤穂線が地域の生活や産業を支え、備前焼が日本の歴史や文化を彩ってきたことが、よく分かったと思います。
つまり、どちらも、単なる「鉄道」や「焼き物」ではなく、その土地の歴史や人々の営みを物語る、大切な存在だと言えるでしょう!
これらの深い歴史を知ると、次に赤穂線に乗って備前焼の里を訪れるのが、もっと楽しみになりますね。

コメント