鉄道唱歌 関西・参宮・南海編を、わかりやすく解説してゆきます!
津市に祀られる結城宗広などについて、やさしく解説してゆきます!
↓まずは原文から!
神は結城の宗廣と
きこえし南朝忠義の士
まもるか今も君が代を
さらに読みやすく!
神は結城の 宗広と
きこえし南朝 忠義の士
まもるか今も 君が代を
さあ、歌ってみよう!
♪かーみはゆうきの むねひろとー
♪きこえしなんちょう ちゅうぎのし
♪まもるかいまもー きみがよをー
亀山駅→一身田駅→津駅→阿漕駅→高茶屋駅→松阪駅→多気駅
(参宮線)
多気駅→田丸駅→宮川駅→伊勢市駅→二見浦駅(→至・鳥羽駅)
今回は、三重県津市および、英雄・結城宗広の話題
かつて津駅から出ていた、参宮鉄道
列車は、既に三重県津市の津駅に到着しています。

津駅(三重県津市)
三重県津市は、前回も紹た通り三重県の県庁所在地になります。
また、津駅からは鉄道唱歌の当時(明治時代)は
- 参宮鉄道
という、私鉄による鉄道路線が出ていました。
現代のJR紀勢本線の原型となります。
明治時代に、伊勢神宮への参拝客を乗せることを目的として出来た参宮鉄道
この参宮鉄道は、亀山駅から津駅まで延びてきた鉄道を、さらに伊勢神宮へ参拝されるお客さんをターゲットとして乗せるために造られた民間の鉄道です。
明治時代は、国で造る鉄道のほかに、民間の金持ちが投資して造った線路(民間の鉄道会社)も多かったのです。
当時はまだ自動車が無く、鉄道を造れば多くのお客様に乗ってもらえて利益が上がるからですね。
民間→(戦前)国有化→国鉄→JR線の流れへ
やがて日清戦争や日露戦争などが激化し、鉄道は軍事物資を運ぶために重要視されるようになってゆき、1906年に民間の鉄道は国有化されます。
それが戦後の国鉄時代を経て、現代のJR線に至っているのです。
当時の「参宮鉄道」と、現代の「参宮線」は異なる
参宮鉄道は、先述の通り現在はJR紀勢本線の一部となっています。
また、現代のJR参宮線は、もっと南(松阪よりも南)の
- 多気駅
から東となっています。
明治時代の「参宮鉄道」と、現代の「JR参宮線」を混同しないようにしましょう。
津市に鎮座ある、結城神社
前置きが少し長くなりましたが、鉄道唱歌の歌詞の本題に入ります。
三重県津市には、かつて鎌倉後期に後醍醐天皇に対して誠心誠意を尽くした武将である
- 結城宗広
を祀る、
- 結城神社
が存在します。
結城神社は、津駅よりもむしろ一つ先の
- 阿漕駅(三重県津市)
の方が最寄駅となっています。
しかし、その阿漕駅からも約1kmほど離れているため、青春18きっぷユーザーや徒歩で行く方々には若干きついかもしれません。
後醍醐天皇に忠誠心を尽くした武将、結城宗広とは?
結城宗広とは、鎌倉時代の終わりに後醍醐天皇とともに討幕のために戦った武将です。
彼と同じく後醍醐天皇とともに戦った武将として、
- 楠木正成
- 新田義貞
- 名和長年
- 北畠顕家
などの存在があります。
結城宗広は後醍醐天皇に忠誠を誓い、先述の楠木正成らとともに、鎌倉幕府討伐のために戦ったのでした。
後醍醐天皇の挙兵「笠置山の戦い」
鎌倉時代の終わり頃、鎌倉幕府の腐敗ぶりに不満を感じた後醍醐天皇は、「幕府を倒せ」と兵を挙げたのでした。
しかし、京都府木津川市の東にある笠置山にて敗北してしまったのでした。
そのため、後醍醐天皇は島根県沖の隠岐の島に流されてしまいます。
この「笠置山の戦い」は、鉄道唱歌 関西・参宮・南海編 第10番でも歌われています。

また、当時の元号(※)を「元弘」とよぶため、幕末の鎌倉幕府討伐のために行われた一連の戦いを、
- 「元弘の変」
といいます。
※現代の元号は、言うまでもなく「令和」ですよね。
鎌倉時代の終わりの当時は「元弘」だったのでした。
ここに、鎌倉幕府の滅亡へと向けた一連の戦いである、「元弘の変」がスタートします。
後醍醐天皇の隠岐脱出を助けた、名和長年
そして後醍醐天皇は隠岐の島を脱出し、
- 名和長年
に迎えられます。
名和長年が、天皇が脱出して乗ってきた舟(御船)を迎えた場所が、鳥取県の大山近くの、
- 御来屋みくりや</ruby(鳥取県大山町)
になります。
これは山陰鉄道唱歌 第20番でも歌われています。
詳しくは、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

鎌倉幕府の滅亡 建武の新政の失敗
やがて楠木正成や新田義貞らの活躍により、北条氏を滅ぼし、鎌倉幕府は滅亡したのでした。
1333年のことです。
しかし、鎌倉幕府を滅ぼしたはいいものの、問題はここからでした。
その後に後醍醐天皇によって行われた
- 「建武の新政」
は、公家ばかり優遇し、武士に対して冷遇するものでした。
足利尊氏の反乱
この「建武の新政」に不満を持ち、後醍醐天皇を打倒しようとした武士の筆頭格が、
- 足利尊氏
でした。
後醍醐天皇に忠誠を誓う楠木正成らは、足利尊氏を一度は(京都から)九州へ追い払います。
しかし、足利尊氏は九州で力を蓄え、再び巻き返して京都へと進撃してきます。
「もはや、これまで」と、最期を覚悟した楠木正成は、神戸の湊川において最期を迎えます。
これは鉄道唱歌 東海道編 第64番でも歌われている通りです。
詳しくは、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

後醍醐天皇は吉野へ 「南朝」のはじまり
足利尊氏に敗れた後醍醐天皇は、奈良県の南の山奥に存在する、吉野という地域へと逃げ込みます。
この吉野の山の中に、吉水神社という神社が存在します。
この神社に南朝という別の朝廷を築き、ここを拠点(皇居)としたのでした。
一方、それまでの京都にある既存の朝廷を「北朝」といい、歴史上まれにみる、「二つの朝廷が存在していた時代」となりました。
この時代を「南北朝時代」といいます。
この南北二つの朝廷は、1392年に室町幕府三代将軍・足利義満によって統一されます。
吉野については、鉄道唱歌 関西・参宮・南海編 第47番、第48番でも歌われています。
詳しくは、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。


結城宗広の功績と最期
吉野を脱出、地元の東北・白河へ しかし津で力尽きる
結城宗広はこのとき、後醍醐天皇と共に吉野に逃げたのでした。
しかしさらに、彼の元々の出身地である福島県の白河(現代の福島県白河市)へと向かおうとしたところでした。
吉野を出て地元の福島に帰る途中で、三重県の津市の辺りで力尽きてしまい、今、結城神社に祀られているところというわけです。
町(津市)の社(結城神社)に祀られている神様は、
「結城宗広」と知られている、
南朝・後醍醐天皇へ忠誠心を尽くした武将である。
彼は今もこの地で、この国の平和と安寧を守り続けているのだ。
結城宗広の家系・結城氏についての補足解説
茨城県発祥の結城氏
ちなみに結城氏は、その一族の発祥が、
- 茨城県結城市
になります。
結城市は、昔ながらの伝統工芸品である結城紬で有名です。
鉄道唱歌 奥州・磐城編 第8番でも、「紬産地の結城あり」と歌われていますね。
詳しくは、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。
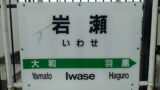
結城市の名産「結城紬」
紬とは、織物の一種です。
結城紬は、高度な技術によって造られるとても高級なものであり、なかなか一般人が買えるものではありません。
茨城から福島・白河へ移住した結城氏
その茨城県結城市発祥の結城氏が、
- 福島県白河市
へと移住し、その子孫として続いたのが
- 「白河結城氏」
ということになります。
結城宗広も、「白河結城氏」の一族に該当します。
次回は、阿漕・高茶屋・松阪方面へ
鉄道唱歌には、このように後醍醐天皇がらみの武将に関するエピソードが非常に多く存在します。
旅行で名所旧跡の探訪の際には、こうしたことも覚えておくと、旅の楽しみが倍増するでしょう。
次は、
- 阿漕
- 高茶屋
方面へ向かってゆきます!

コメント